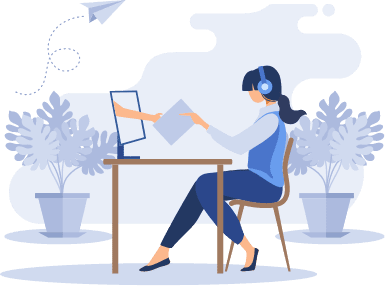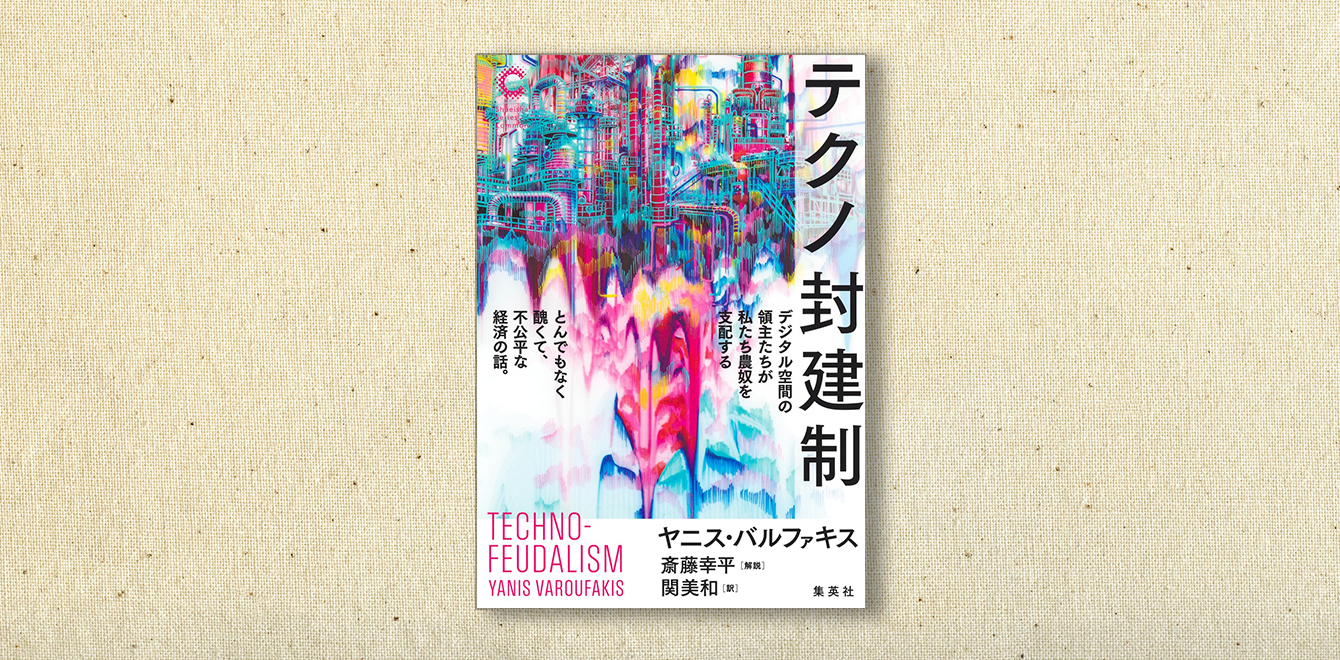
本書『テクノ封建制 デジタル空間の領主たちが私たち農奴を支配する とんでもなく醜くて、不公平な経済の話』(TECHNOFEUDALISM: What Killed Capitalism, 2023)は、資本主義が変容した現在的段階であり、ニクソン・ショックとリーマン・ショックという資本主義に変容をもたらした2つの大きな出来事について、さらには「クラウド・レント」(地代や家賃)をめぐる米中の対立、ビッグデータや個人情報といった情報資本の価値化など、フィンテックの発展やネットワークと金融の関係性など、情報技術や政治経済、労働をめぐる問題などが幅広く論じられます。
さらには、政府主導のフィンテックともいうべきスーパーアプリを使った統合的なネットワーク・システムやデジタル人民元を導入した中国の事例などが取り上げられ、現在的問題や貿易(実態のあるもの)と情報産業(実態のないもの)をめぐる米中対立関係など、トランプ現大統領(ならびにバイデン政権)が関税や対中政策に固執する背景を読み解くヒントが多分に含まれています。
著者のヤニス・バルファキスはアテネ生まれの理論派の経済学者で、2015年のギリシャ経済危機の際に財務大臣に就任するなど財政の専門家でもあります。現在はアテネ大学で経済学教授を担当しており、代表的な著作に『父が娘に語る美しく、深く、壮大で、とんでもない経済学の話。』(2019, ダイヤモンド社, 原著2013, 英訳2015)があるように、経済学や金融工学、財政に関する一般向けの解説にも長けており、その部分は『テクノ封建制』でも如実に反映され、内容の専門的な部分も非常に読みやすく、なおかつ平易に感じました。
多くの経済学やビジネス書とは異なり、著者のバルファキスは出身地であるギリシャに議論の主軸を置いており、それがリーマン・ショックに至るまでの変化の兆しや、ショック以降の金融危機や米中の対立をより第三者的な観点での分析に繋がっていると思われます。
もう一点印象深いのは、ヘシオドス(『仕事と日』)やホメロス(『オデュッセイア』)が引き合いに出されたり、本書における重要な概念のひとつに「ミノタウロス」(ギリシャ神話に登場する牛頭人身の怪物)もの名を用いるなど、古典や神話といったギリシャのルーツになぞらえて、現在の状況・解説してみせる文学的な鮮やかさですが、引用されるテクストに関する予備知識の有無で受ける印象も変わると思われます。
本書の第1章、第2章はイントロダクション的な内容で、第3章「クラウド資本」から本格的な分析やモデルの提示が行われ、政府主導のフィンテックが推進される中国の事例を中心に据えた6章「新たな冷戦――テクノ封建制のグローバルなインパクト」は非常に教に深く読めました。
結びとなる第7章「テクノ封建制からの脱却」、ユーザー(デジタル農奴)の搾取や不公平を助長するテクノ封建制を打倒すべきものと設定し、「団結」を呼びかけるメッセージで結ばれます。この点は、バルファキスの両親が左派的な思想を持ち、バルファキス自身も2015年の急進派左派連合(SYRIZA)政権の財務大臣を務めていたという来歴を持ち、それが彼の思想に色濃く表れており、訳者の関美和さんは「少数の人がそれ以外の人たちの行動様式とか生活の糧を握っている状態が非常に危険であるので、それ以外の“小作農”である私たち全員が数で団結することによって、経済的な自由かもしれないですし、もしかしたら行動の自由というものを、もう1回自分の手に取り戻しましょうというメッセセージなのかなと思います。」(「『テクノ封建制』」ヤニス・バルファキス著、関和美訳」, 読むらじる)と述べられます。
テクノ封建制の打倒を目指すか、利便性を享受するためにテクノ封建制に従属しつつも批判的な観点を保持し時には搾取構造を懐疑することを是とするか、難しいことを考えず便利で快適なサービスを満喫するかは人によって異なりますが、本書に興味を持つ方は、なにがしかの問題意識を持っていると思われますし、webサービスやSNSを利用している際に自身のデータが解析され、アルゴリズムが駆動することを強く意識することがある方には、一読を勧めたいと思います。
アメリカの事例を取り上げたロバート・B・ライシュの『コモングッド: 暴走する資本主義社会で倫理を語る』(2024, 東洋経済新報社, 原著2018)も、アルゴリズム支配によるフィルター・バブル(自分の好みや興味を持つ分野の情報に囲まれる状態)やデータ・マイニングに対する自衛意識や、個人情報を商品として集約するビッグ・テックに対する法規制の検討など、アクチュアルな問題が数多く扱われており、テクノ封建主義の領主つまりアメリカのビッグ・テックについて、より実践的かつ技術的に(加えてアントニオ・ネグリ/マイケル・ハートの『帝国』で展開された議論を踏襲した形で)論じたものがバルファキスの『テクノ封建制』であるという印象を受けました。
次に、「グローバル・ミノタウロス」「クラウド資本/クラウド農奴」「テクノ封建制」といった、独特の用語をとりあげながら、バルファキスの議論の大枠を見ていきたいと思います。
「資本主義のグローバル・ミノタウロス段階」
ギリシャ神話に登場するミノタウロスは、クレタ島のミノス王の妻パーシパエ(ポセイドンの呪いで牡牛と交わる)の子で、人間の身体と牛の頭部を持つ、ファンタジー作品などで馴染み深い怪物です。
神話ではミノス島の迷宮ラビリントスに閉じ込められ、繁栄や周辺諸国との関係維持のために生贄としてアテナイの若者が捧げられてきましたが、英雄テセウスによって倒されます。ミノタウロスは人間の貪欲さや内に秘めた獣性の象徴として知られ、バルファキスはブレトンウッズ体制の終焉後に立ち現れた新たな資本主義の暗喩として「ミノタウロス」の名称を用います。
その怪物はまずアメリカの貿易赤字として命を得た。ベトナム戦争、「偉大な社会」政策、そしてドイツと日本の工業の生産工場により、アメリカは海外に売りつけるよりも多くのものを買い入れるようになった。ヨーロッパやアジアからの輸入品がアメリカ中心部のショッピング・モールに流れ込み、人々はそれを貢ぎ物のように消費した。貿易赤字が増えれば増えるほど、ミノタウロスはアジアからの輸入品を欲しがった。しかし、その怪物にグローバルな存在感を与えたもの――アメリカだけでなくヨーロッパとアジアの平和と繁栄を約束したもの――はウォルマートとウォール街をつなぐ迷宮のような地下トンネルだった。
(66頁)
バルファキスが「ミノタウロス」とよぶものが姿を現し始めた時期は、ライシュが「コモングッド」の劣化や崩壊が始まったと指摘する時期(ライシュは1964年のトンキン湾事件を起点とする)と比較的重なっており、社会的道徳規範であるコモングッドにほころびが生じる中で、ミノタウロスのような貪欲さに突き動かされる資本主義が拡大してきました。
ミノタウロスが登場した時期にはバルファキスが「地下トンネル」と呼ぶ経済構造が打ち立てられ、諸外国にある工場を所有する外国籍のオーナー(おおむねアメリカ籍)が、生産によって得られた利益(現金)をウォール街に追加の貢物として投資することで、国としての貿易は赤字でも権力層は潤い、グローバル・ミノタウロスによって金融資本の還流や、正解の純輸出国の繁栄が支えられ、ブレトンウッズ後の世界秩序の形成と維持が可能になった(66-67頁)とされます。また、新たな世界秩序や体制は「グローバル化」や「金融化」と呼ばれることもあります。
バルファキスは新体制を「資本主義のグローバル・ミノタウロス段階」(72頁)と呼び、「グローバル・ミノタウロとは、アメリカが支えたグローバルな資金還流システムの暗喩だ。それが1970年代後半から2008年にかけて、現在の私たちが体験しているドラマの小道具――巨大金融機関、巨大テック企業、新自由主義、産業規模の格差――をお膳立てした。言うまでもなく民主主義の衰退も小道具のひとつだ」(79頁)と述べます。
バルファキスの分析では、1971年のニクソン・ショック/ブレトンウッズ体制の崩壊の後に、資本主義のグローバル・ミノタウロス段階に至ります。グローバル・ミノタウロス段階ではコンピューターや通信技術の急速な発展が経済や金融に非常に大きな変容をもたらしており、バルファキスは次のように記します。
2007年には人類の総収入の10倍以上の金額を金融業界は賭けに投じるようになっていた。この狂乱を支える侍女となったのは、アメリカのミノタウロスにとめどなく流れ込んできた莫大な資金、コンピューターが生み出す複雑な金融デリバティブ商品、そして市場は万能だとする新自由主義的な信念の3つである。
(76頁)
3つの信念に支えられて拡大を続けた新体制は、リーマン・ショック/グローバル金融危機によってミノタウロスが倒れることで転換点を迎え、コロナ禍における金融政策を足掛かりにしてビッグテック(GAFAM)やテスラが大規模な成長をみせ、資本主義がさらに変容して行きついた段階、すなわち現在をバルファキスは「テクノ封建制」と指摘します。
クラウド資本/クラウド農奴
資本主義の段階的変容としては、ブレトンウッズ体制の崩壊、グローバル・ミノタウロスの登場、リーマン・ショック、テクノ封建制という段階的な図式が提示される一方、インターネットも先の図式に寄り添うように変化を遂げており、第3章の前半部ではインターネットと資本主義の関係性の変容がまとめられています。
当初の用途や出自を忘れている方も多いと思いますが、元来インターネットは非商業的なネットワークとして登場し、冷戦期には中央集権型のネットワークではなく、分散型のコンピューター網へと発展しました。
分散型も当初は非商業的なネットワークであり、国防や西側で協力した体制を強化する目的で開発された初期インターネットは、共有地(コモンズ)としての性格を帯びていたとされますが、やがて市場原理や金融ビジネスに取り込まれ、現在は巨大テック企業が占有する領地となり、今日のテクノ封建制へと繋がっています。
次に引用する一文は、やや監視社会的なデストピア的要素を強調したような趣もありますが、クラウド資本とクラウド農奴の関係性を端的に描き出しています。
かつては私たちのデジタルコモンズだった場所で何をするにしても、今では巨大テック企業と巨大金融機関に対して、彼らが完全に掌握しているデータを使わせてください、とお願いしなければならない。お金を送るのにも、「ニューヨーク・タイムズ」を購読するのにも、デビットカードでおばあちゃんに靴下を買ってあげるのにも、見返りとしてあなたの一部を差し出さなければならない。ちょっとした手数料を払ったり、そうでなければあなたの好みについての情報を一部共有したり、だいたいはフィンテックの巨大なコングロマリットに今後も引き続き監視されること(そして最終的に洗脳されること)に同意させられたりする。そして、あなたがあなたであることを認証するには、巨大フィンテック・コングロマリットの助けが必要になる。
(101頁)
気付けば生活のあらゆるところに浸透しているアメリカのビッグ・テックの技術的恩恵にあずかり、国内企業では楽天銀行や住信SBIネット銀行(スマホアプリを使ってコンビニATMから引き出せるカードレスが非常に便利です)の各種サービスを活用している身としては、「見返りとしてあなたの一部を差し出さなければならない」「フィンテックの巨大なコングロマリットに今後も引き続き監視される」という記述に対して思い当たることが多数あるため、上記の引用部は非常にクリティカルなものとして響きます。また、そういう状況下において我々は利便性を享受〈している〉のではなく〈させて頂いている〉ということを念頭に置く観点が、情報ネットワークに取り囲まれた現状を批判的に考えるうえでは必要になるとも感じています。
クラウド資本は、コモンズとしてのインターネットの囲い込み(エンクロージャー)によって形成され、ユーザーはレント(地代・家賃)を払ってサービスを利用しながら、クラウド農奴として情報を生産し、献上します。物品の販売者はAmazon.comの途方もない規模のショッピング・モールに間借りすることでレントを支払い、ユーザーはアイテムの購入のみならず、商品を検索し、興味対象をクリックすることでもレントを支払っています。さらに、スマートフォン向けのアプリはiPhone 向けのAppstoreやAndroid端末用のGoogle Playの経由でしか流通させられず、販売やアプリ内課金にもレントが課せられるといったシステム、「クラウド・レント」が構築されています。
クラウド資本のハード面での構成要素は、「スマート・ソフトウェア、サーバー・ファーム、基地局、そして果てにない長さの光ファイバー」(113頁)であり、重要なコンテンツ部分は、身近なもので賄われおり、ユーザーは課金という直接的な行動以外でもクラウド・レントを提供し続けています。
クラウド資本に蓄積されたもっとも価値ある部分は、物理的なものではなく、フェイスブックに投稿されたストーリーであり、TikTokやユーチューブにアップされた動画であり、インスタグラムの写真であり、ツイッターのジョークや悪口であり、アマゾンのレビューであり、私たちの位置情報だ(グーグルマップで最新の渋滞情報もわかるが)。私たちは、自分の物語、動画、画像、冗談、そして行動を差し出すことで、どんな市場も経由せずにクラウド資本の蓄積を生み出し、再生産している。
(113頁)
搾取されていることに意識的・無意識的であれ、「それが不払い労働による生産であることには変わりない――クラウド農奴は、日々の自主的な勤労によって、カリフォルニアや上海に住む極少数の億万長者を潤している」(114頁)というバルファキスの指摘はなかなか辛辣で、言葉は強いですがユーザーを「クラウド農奴」と呼称する観点は強烈な印象を残し、YouTubeやインスタグラムでGoogleでの検索ワードに関連付けられた広告が繰り返し登場するのを目にし、広告をリコメンドするアルゴリズムがしっかり駆動していることに気づくと、「ああ、今日も情報を搾取されている」と思うことが多くなりました。
テクノ封建制
封建制(フューダリズム)は、単的にいえば君主が領地を分け与え、小作人/農奴は地代(レント)として、生産物や金銭を献上する、御恩と奉公の関係性です。バルファキスは封建制と資本主義の違いを論じるうえで、「レント」と「利潤」を用い、利潤がレントを凌駕する状態を資本主義、その逆を封建主義としたうえで、現在を「テクノ封建制」と定義します。
今、社会経済システムが利潤ではなくレントで動かされる時代になったという基本的な事実に基づいて、新しい名前でそれを呼ぶことが求められている。これをハイパー資本主義とか、レント資本主義として考えるならば、本質的で定義的な原則を見逃すことになる。そして、レントが主役として戻ってきた現実を表すには「テクノ封建制」という言葉以上にふさわしいものはない。
(170頁)
レントはこれまでに触れたように「地代」や「家賃」を主に指す言葉で、「肥沃な土壌や化石燃料を埋蔵する土地など、供給量が固定しているものへの特権的アクセス」(157-158頁)で生じ、利潤は「エジソンの電球やジョブズのiPhoneのように、投資がなければ存在しなかったものに対して投資を行った起業家の懐へ流れ込む」(158頁)という違いがあります。レントは市場の影響を受けにくく、利潤は外的要因や競争の影響で減ることがあり、利潤の例としてあげられるのは発明・登場時には莫大な利益を上げたソニーのウォークマンっです(1979年の初代が発売、1981年の2代目「WM-2」が世界的なヒットとなる)。
ウォークマンの登場以降は模倣品との競争が激化することでソニーの利潤は目減りしていき、「最後にアップルがiPodを引っさげて参入し、市場を独占した」(158頁)という結果に終わりました。
資本主義が栄えるのは、利潤がレントを凌駕している状態で、資本主義的企業(本書では、フォード、ゼネラルモータース、フォルクスワーゲン、トヨタ、ソニーなどが例としてあげられます)が台頭する一方、1950年代から1980年代頃までは「ブランド・ロイヤリティ」がレント的な企業、商品の価値となっていたとされます。
ブランド・ロイヤリティがあれば、ブランド所有者は顧客を失うことなく価格を上げることができる。価格のプレミアムを支払うことで、たとえばメルセデス・ベンツやアップル製品を持つ人は、安いフォードやソニー製品を持つ人よりも高いステータスを誇示できる。この値段のプレミアムの蓄積が、ブランドのレントになる。
(160頁)
1950年代にブランディングとして復活したレントが、2000年代に利潤を凌駕する契機となったクラウド資本の台頭であり、レントの劇的な復活を支えたのはアップルのブランドとその製品群(MacやiPad)や、iPhoneを軸としたクラウド資本(前述のApp Storeなど)とされます。
現代の主軸となる「クラウド・レント」は主にApp storeやAmazonに出品する利用料・手数料の支払いなどです。App storeについては手数料の妥当性や、クレジットカードなどの外部決済の利用制限(課金はアップルのアプリ利用に限定)についての訴訟が行われたことも記憶に新しい事例です。
圧倒的なシェアを誇るiPhone市場=アップルが囲い込んでいる領地にコンテンツを供給するためには、アップルの専制に従いながらレントを支払い続ける必要があり、もう一方の市場であるAndroidもGoogleが囲い込んだ領地となっています。
「テクノ封建制」を考える際、一番わかりやすい例がグローバルなスマートフォン業界で、二大巨頭たるアップルとグーグルは情報産業の代表的なクラウド領主です。その、一方ではプレカリアート(不安定な非正規雇用者、零細自営業者など)と業務を結ぶクラウド領主も登場し、こちらはスマートフォン業界よりも細分化され、グローカルな傾向を見せています。
グローバル・ノースではウーバー、リフト、インスタカートといった企業が、そしてアジアやアフリカではそれらを真似た同様のサービスが、膨大な人数の運転手、配達員、清掃員、レストラン経営者や犬の散歩代行をする人までをクラウド領土に引き込んで、給与所得ではない、出来高払いの労働者も稼ぎから一定額をせしめていた。これもクラウド・レントだ。
(163-164頁)
国内における同様のサービスは、コロナ禍を通じて定着したウーバーイーツや類似のフードデリバリー、アウトソーシングの仲介サービス、ココナラなどが代表的なスキルマーケット、近年では24年7月に上場したスポットワークのマッチングサービスを主業とするタイミーなどがあり、アプリや専用webサービスといった領地にクライアント、ギグワーカーやプレカリアートを囲い込み、クラウド・レントを献上させることによって多様な働き方はやスキマ労働が維持されていることを、改めて実感させられます。
クラウド・レントは会社の利益だけでなく、サービスの運営・維持にかかるコストにも充てられます。それゆえ、運営規模やクラウド・レントの徴収量、対価としてのサポートなどが適切なものかをジャッジされる必要がありますが、Amazon、Apple、Googleなどが特に目立つのはグローバルなクラウド領主であり、なおかつ同規模で競合・参入する他社のいない独占的な領地(Amazon.comやAmazon Web Service、iPhoneやMacユーザー、Android端末やYouTubeの利用者)にクラウド農奴を囲い込んでいるという特権的な権力構造に起因します。
様々なwebサービスやスマホアプリは国内において日常生活に欠かせないレベルにまで浸透しているためあまり意識されることが少ないかもしれませんが、それの大半はアメリカ企業によって運営・開発が行われており、グローバルなテクノ封建制は主としてアメリカがその支配権を掌握しています。
『人新世の「資本論」』などの著作を持つ斉藤幸平さんは本書の解説「日本はデジタル植民地になる」で「テクノ封建制のクラウド領主がいるのは、もちろんシリコンバレーを中心としたアメリカのデジタル帝国である。だが、その支配は世界全体に及ぶ。したがって当然ながら、地政学的な帰結をもたらす。GAFAMのような自前のプラットフォームを持たない日本やEUといったグローバル・ノースの国々も、アメリカのデジタル植民地になっていく」(295-296頁)と指摘するように、グローカルなテクノ封建制を敷く中国や一部の国を除けば、アメリカによるデジタル植民地は現在も領土拡張を続けています。
サイバーセキュリティ分野などでは、それまでは海外ソフトの使用が主でしたが純国産のセキュリティソフトへの転換が進み、ソフトの研究開発を手掛ける FFRIセキュリティの「FFRI yarai」が官公庁に広く導入されるようになり、7月1日には国家サイバー統括室が発足するといった、デジタル植民地化に甘んじない動きも見え始めています。
アメリカのテクノ封建制への対抗勢力として中国のテクノ封建制があり、それが米中関係を複雑化させる要因と繋がっています。特に象徴的な例はアメリカにおけるTikTok規制をめぐる問題で、日本においては2023年に機密情報を扱う政府の効用デバイスでのTikTok利用が松野官房長官の記者会見で示されたものの、アメリカほどの大きな問題にはなっていないという印象があります。
参考記事: 「公用スマホで『TikTok』含むSNSは禁止 松野官房長官が明かす」(2023年2月27日, ITmedia)
今では重要なインフラとして定着したLINEですが、2012年に登場したころは企画・開発会社であるネイバージャパンが韓国のネット企業の日本法人であっため、純国産アプリであるにも関わらず韓国製と勘違いされ、登場当初は(韓国は日本よりもネット先進国であることからか)韓国製アプリは個人情報を抜き取られそうで怖いという声が多く上がっていました。また、文字入力アプリ「SHIMEJI」が中国の検索エンジン大手Baidu(百度)の開発だったことや2013年に情報漏洩(入力情報が外部に送信される不具合)から、かつてのLINEのように情報を抜き取られるのではという憶測が広まっていました。
現在のSHIMEJIは外部機関の調査に合格するほかISO認証も取得し、一定水準の安全性は保持されているため、現在でも流布される危険性についてはあくまで噂の範疇にすぎませんが、データの収集・利用をオフに設定しなければ文字入力という行為を通じてクラウド・レントを中国に支払うことになります。
TikTokが中国製アプリであることや、動画の投稿や視聴や検索の傾向がマーケティングにとっての重要な資料として収集されている(TikTokに限らず大半のwebサービスで行われている日常的なこと)ことに対して、国内の反応はLINEやSIMEJIのときほど過剰な反応はなく、若者を中心に広く普及し、活用することで効果的な訴求力を高めることが可能な分散型メディアとして認知され、すっかり定着したという印象があり、2025年の参院選でも各党がTikTokの公式アカウントを開設し、若者や無党派層へのPRを展開しています。
参考記事: 「参院選で9党が競うTikTok動画 バズる3要素とは? 専門家分析」(鈴木悟, 2025年7月10日, 毎日新聞デジタル)
テクノ封建制時代の冷戦
象徴的な出来事として、バルファキスは2019年5月にトランプ大統領が署名した中国通信大手ファーウェイ(華為)のスマートフォンにGoogleのAndroid OSの搭載禁止や、バイデン政権時代の中国に対する半導体輸出制限などをあげます(184頁)。その理由は国家安全保障上の「懸念」のみならず、2008年以降の政府による投資促進政策でクラウド資本が力と付けた中国およびテック企業(アリババ、テンセント、百度、平安、東京商城)がアメリカのビッグ・テックやクラウド資本と競合するためとされます。
政府機関と直接結びついている中国のテック企業の詳細や、イーロン・マスクがXで実現したとされるイメージに近いオールインプラットフォームであり、ウェブインフラとしても機能する「We Chat(微信)」は第6章で詳しく述べられていますが、通話、ショッピング、送金、税金申請、健康状態証明等がWe Chatアプリのみで完結可能という点に驚ろかされる一方、個人情報や消費行動などが政府の監視下に置かれていることに対する懸念を抱いてしまいます。
アメリカでは国内で中国のバイトダンス(字節跳動)が制作したアプリTikTokのアメリカ事業売却や配信禁止措置など、日本からみると(防衛上の懸念はあれど)ヒステリックに騒ぎすぎではと思うところがあるのですが、2024年のデータでは、アメリカ人の実に4割がTikTokを検索エンジンとして利用したことがあるという結果がでており、米国のwebサービスで囲い込んでいたはずのクラウド農奴が4割も中国に流出していたと考えると、重大性がより理解しやすくなるでしょう。また、加えて、バルファキスはTikTokを通じてドル建てクラウド・レントを吸収できるという点も指摘しており次のように述べます。
TikTokはアメリカ市場向けのプロダクトを新たに製造するためにアメリカの顧客からドルを支払ってもらう必要はない。サーバー、アルゴリズム、光ファイバーはすでにそこにあり、中国国内の資金によって維持管理され、アメリカの顧客に向けて人気動画を投稿しても追加コスト(限界費用)は一切発生しない。これが決定的な違いだ。だからTikTokはアメリカの貿易赤字にもドルの覇権に頼らずに、アメリカから中国へとクラウド・レントを吸い上げることができる。クラウド資本を創出するのにドルを必要としないTikTokは、ドル建てのクラウド・レントを高速で直接かつシームレスに徴収できる。
(194-195頁)
その他にも、中国のクラウド金融に対するアメリカの警戒感も懸念材料とされており、2022年10月にバイデン大統領によって宣言された、中国への先端マイクロチップ製造の関連品目の輸出禁止もその一環(201頁)と指摘され、NVIDIAのAI用半導体の輸出制限なども同様の理由が大きくあると思われます。
本書ではデジタル封建制のもたらす搾取構造や不平等、米中によるグローバルなデジタル植民地、地政学的対立など今現在進行している様々な状況を批判的に読解するための本であり、問題提起の本でもあります。
警鐘を鳴らすような論調でもあるため、クラウド領主による支配構造を悪しきもの、打倒すべきものとして扱う論調が強いため、ネガティブな部分が先行して語られがちですが、今現在、そして今後も身近なレベルで対峙する問題が多数取り上げられているので、デジタル技術に対するリテラシーと高めるという点でも一読の価値があると思います。
関連記事
人気記事
まだデータがありません。