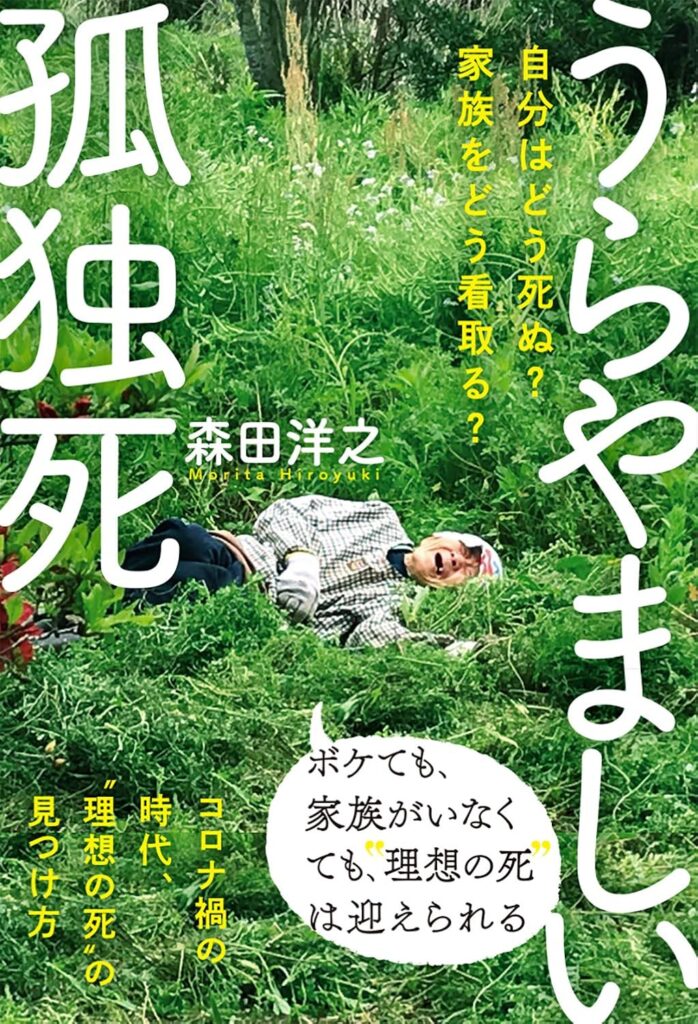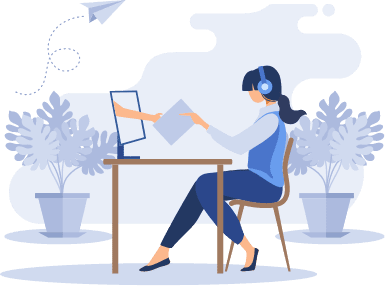佐藤舞『あっという間に人は死ぬから』
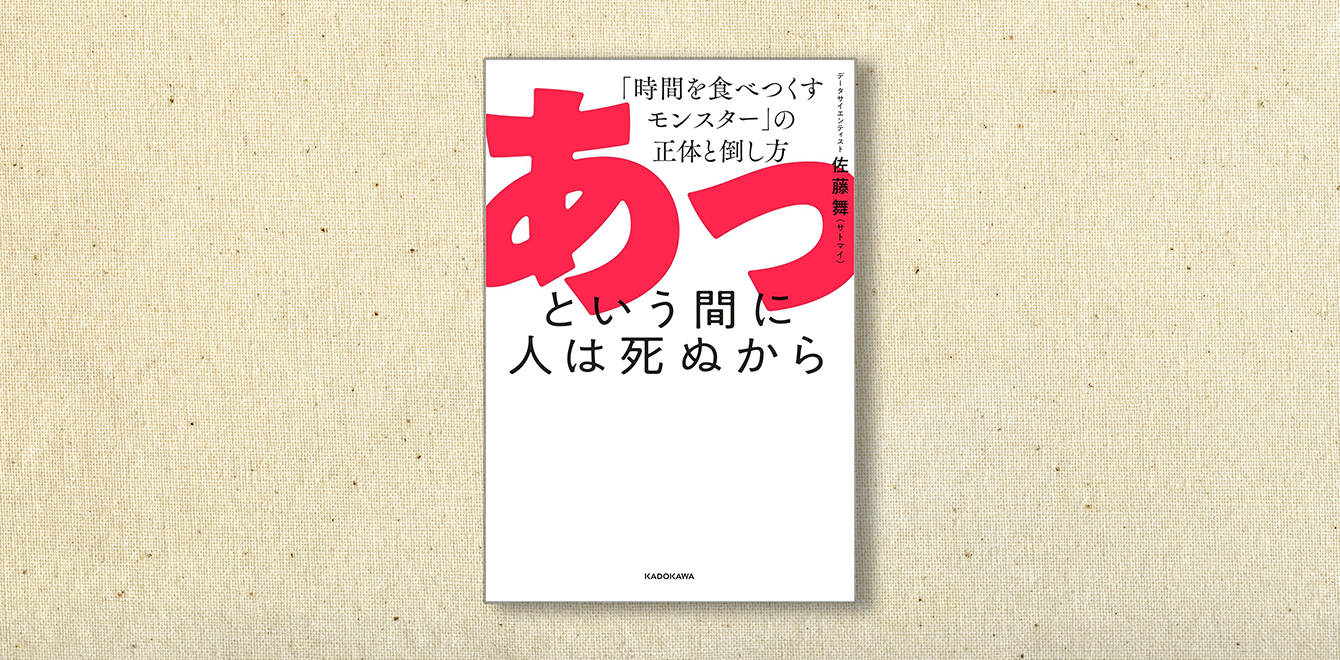
本書『あっという間に人は死ぬから 「時間を食べつくすモンスター」の正体と倒し方』(2024, KADOKAWA)では、時間にまつわる自己啓発やコーチングなどが扱われています。時間の使い方や捉え方、ライフスタイルの改善、内観的に自己を捉え直すためのアドバイス、認知行動療法(Cognitive Behavior Theory, 略称 CBT) やなどを幅広い観点や著者の専門分野である統計学の資料などを基に展開されます。
著者でありデータサイエンティストの佐藤舞さんはデータ分析・統計解析事業などを生業とするほか、YouTubeチャンネル「謎解き統計学|サトマイ」を運営し、統計学やマーケティングリサーチと専門知をベースに時事トピックの解説を行われています。その他にも、企業の勉強会に講師として登壇するほか様々なフィールドでも精力的な講演活動を行われています。
本書は『はじめての統計学 レジの行列が早く進むの、どっち!?』(2021, 総合法令出版)に続く2冊目の著作になり、「読者が選ぶビジネス書グランプリ2025」の自己啓発部門を受賞されています。余談になりますが、同グランプリの2025年度のリベラルアーツ部門では、三宅香帆さんの『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』(2024, 集英社)が1位を獲得し、2024年度のグランプリは田内学さんの『きみのお金は誰のため』(2023, 東洋経済新報社)がそ受賞されています。どちらも過去に本サイトで取り上げていますので、関心のある方はそちらもご参照頂けると幸いです(書評リンク一覧)。
時間経過が早すぎる……
内容紹介のキャッチコピーが「『1年たつのが早くなった』と感じるすべての大人に」とあるように、本書の主なテーマは時間です。冒頭では、小学校の頃は「20分」の中休み時間を目一杯使って運動や遊びに興じていた一方、大人になった現在では「20分じゃ何もできない」と思い込んでしまうといった、時間の捉え方に関する変化が指摘されます。
小学校時代の休み時間の「20分(もある)」と、大人になってからの「20分(しかない)」という差異は、本書で指摘されるまで全く気付かなかった点であり、冒頭から大きな感銘を受けた箇所でした。
大人になると時間の進み方が早くなる理由には諸説ありますが、本書では「行動のパターン化」がその中でも有力なものと述べられます。「行動のパターン化」は、繰り返される刺激になれてしまうと新しい刺激を受けたときよりも「時間が短い」と脳が錯覚してしまうというもので、本書では旅行の際に行きよりも帰りのほうが時間経過を早く感じてしまうという例が紹介されています。同様なものとして、日常的に使う電車の路線や区画と初めて使うあるいは稀にしか使わない路線・区画では、所要時間に大差はないにも関わらず後者のほうが妙に長く感じてしまう、という経験がある方は多いと思います。
佐藤さんは子供も頃と大人になってからの時間の感じ方の差異について、「大人になるにつれて、時間に対する知覚が歪んでいき、よくない思い込みによって有意義な時間の使い方ができなくなっている」(12頁)と指摘されます。巻頭にも「私たちの多くは『たった20分じゃ何もできない』と思い込み、手元のスマホで時間を浪費している」(7頁)とあるように、「20分(しかない)」への思い込みを解消して「20分(もある)」として正しく捉え直す事や、「行動のパターン化」による知覚の変化に気づくことが、まず最初のステップとなります。
佐藤さんは「私たちの身の回りは、生活を便利に楽しくしてくれるはずのテクノロジーや生産性アップのライフハックであふれているのに、なんとなく本質的な悩みが解決されないまま時間だけが過ぎていっている気がする。/このままではあっという間に死んでしまうのではないか」(15頁)と述べたうえで、現代人の課題を「有意義な時間の使い方」と設定し、本書の中で解決にいたるまでの流れを展開されます。
起承転結になぞらえた4章からなる本書は、佐藤さんの思考の流れを追体験する構成とされています。「人生の浪費の正体を暴く」1章、「人生の3つの理と向き合う」2章、3章で「自分の本心に気づき」、「本心に従って行動する」ことが4章で論じられ、各章では「問題提起」「原因特定、証拠」「損失回避」「解決策」という4ステップで考察を深め、解決策を導く(16頁)という系統的な構成となっており、各項目を読み直す際のインデックスとしても効果的に機能しています。
第3章、第4章は内的な問題の発見や自己認識の再確認など、読者によって異なるパーソナルなテーマが掘り下げられます。他の章よりも実践的かつ自己啓発要素もより色濃くなっていくので、人によって関心の有無は分かれると思います。その一方、第1章と第2章はアクチュアルかつ普遍的な話題を扱っているので、人を選ばず比較的読みやすい内容になっています。
時間を有意義に使うために
問題提起となる第1章では、生産性を上げるための時間術、いわゆるライフハックが中心に取り上げられます。紹介されるのはAIを使った教育辞事業を行う米企業フィルタードが発表した、時間内にタスクを効果的・効率的に片付けるテクニックランキングです。
上位にあるのはソーシャルメディアのコントロール、健康的な食事、TO DOリスト、作業タスクの優先順位付け、タイムボクシング(タスクを優先づけて時間割風にまとめる)などがあり、本書の中では佐藤さんが実践するノートや付箋を利用したタイムボクシングの例なども紹介されます。
とはいえ、タスクと時間の整理区分を行ったとしても人間の集中力には波があるため、予定通りに全てのタスクを完遂することは難しく、時間の制御には困難が伴います。また、時間との関係について佐藤さんは次のように述べられます。
時間術の本を読むと、あたかも、自分が何に時間を使うことができるのかをコントロールできるかのような錯覚に陥りますが、現実には難しいようです。ここが「お金の使い方」との根本的な違いでしょう。お金は使わなければ貯めたり増やしたりすることができますが、時間は、意図してなくても刻一刻と失われているのです。時間は貯金できないのです。
(Kindle版, 42頁)
執筆者は進歩史観よりも過去からの連続性や歴史を重視する保守思想や、ロラン・バルトが『明るい部屋』で写真の本質(ノエマ)と指摘した「それはかつてあった」ものごとや、痕跡/インデックスを記録するという機能や意味を持つ写真になどに親しんでいるためか、現在進行形の時間に対する関心が疎かになっていることが本書を読んで気づかされました。
さらに、「時間をコントロールできるかのような錯覚」という一文も、特定の作業をしている際「あと〇〇分したら、別の作業をやろう」と考えながら、作業の切り替えに至らず一つの作業に集中しすぎたことを後悔するような日々を過ごしがちな執筆者には、かなり辛辣に響きました。
「人生の3つの理」
本書では中世のモラリスト文学者ラ・ロシュフコーの「死と太陽は直視できない(Le soleil ni la mort ne se peuvent regarder fixement.)」(人間は受け止められる範囲のもしか見ようとしない)が本書における最重要キーワードとして紹介されます(46頁)。
「死と太陽」のように、今日の私たちが直視できないものとして佐藤さんは「人生の3つの理」(「死」、「孤独」、「責任」)を提示され、それを避けるための(本意とは異なる偽りの)行動を正当化することに手間をかけてしまうことで、間違った・浪費的な時間の使い方を生じさせると指摘されます。「人生の3つの理」については、それぞれ日常生活の中で思い当たる節が多々あるほか、「死」と「孤独」、「孤独」と「責任」といったように、理が複数に跨るケースも少なくないと思います。
佐藤さんが本書で展開されるのは読者自身の内面と向き合うためのコーチングですが、外部に目を向けてみると、理と向き合った例としての「孤独死」(一般的なイメージの孤独死ではなく、森田洋之さんが『うらやましい孤独死』(2021, フォレスト出版)で言及される在宅医療や地域コミュニティでも見守り等)、理から逃げた例としてオルテガが『大衆の反逆』で定義し批判してきた「大衆」(階級でなく精神性や態度に関わるもの)など、幅広い文脈に援用できる考え方とも思えます。
※森田さんの議論については、「持続可能性の時代における人間交際 -「きずな貯金」と「贈与」-」や、森田さんにご講演を頂いた「きずな貯金と信頼の本質」(第7回オフサイトセミナー)を。オルテガについては「『大衆の反逆』を活かした経営」、「21世紀に「貴族」であるとは」(第1回オフサイトセミナー)などをそれぞれご参照ください。
それぞれの理から逃避したり、理からくる不安を払拭するためには対処的な行動(コーピング)に依存しがちになってしまい、代替行動として、「死」では趣味や仕事といった何らかの物事に没頭や集中して不安を払拭するために、結果としてワーカホリックになってしまう例などがあげられています。「孤独」では友人やパートナーを求めて寂しさを紛らわせ、「責任」では他者任せの責任回避、周囲に同調して自分の意見を言わない、他者の評価での一喜一憂する(本書では言及されていませんが、過剰な承認欲求なども含まれると思います)などがコーピングの一例としてあげられています。
また、コーピングは合理的な振る舞いとして日常の則したものも多くありますが、重度かつ非合理なものになってしまうケースもあり、特にワーカホリックなどがその典型例とされています。
「人生の3つの理」から目を背けることは「幸福」から遠ざかるものとされており、「幸福」とは何かを考える際のエビデンスとして、第1章では統計データが用いられます。2万人の日本人を調査した2018年発表の実証研究(西村和夫・八木匡「幸福感と自己決定――日本における実証研究」)では、幸福感は中年期で落ち込み、所得の増加で増加し(1100万で最大値だが主観的幸福度と所得の上昇具合は連動しない)、健康・人間関係に以上に影響を与える変数として「自己決定」(進学先や就職先などの進路を自分で決めたか否か)があることが示されました。
「人生の3つの理」、対処行動的なコーピング(時間の浪費)、幸福感に影響を及ぼす「自己決定」といった論点を踏まえ、佐藤さんは「有意義な時間な使い方」を次のように定義されます。
本書が目指す「有意義な時間の使い方」とは、自分の人生の舵を自分で握ることとその覚悟、そして智慧を手に入れ、人生の3つの理(死・孤独・責任)を受け入れながら、自分の人生をコントロールしていくこと、と定義します。
(61頁)
問題提起にあたる第1章では、「人生の3つの理」という大テーマが提示され、第2章以降は理からの逃避やコーピングを解決するための思考実践として、ワークが登場します。本書に登場するワークは、佐藤さんが複数の論文を統合して制作したオリジナルや、認知行動療法(CBT)として広く使われているものや公開されているもの(236頁)が用いられています。
ワークの内容は「1,過去に起きた困難な体験は何ですか?」「2, 困難な体験から何を学びましたか?」「3, 困難な体験を通じて、何があなたにとって本当に重要だと感じましたか?」(170-171頁)というように、特定のテーマに関する連続した設問に対して自由記述で回答するような内容です。
過去の体験を思い出し言葉を通じた概念化を行い、それを客観視したり、プレゼンテーションを通じて認知や行動を改めることで、認知や行動とも相関関係にある感情や身体反応についても変化を促す(行動治療法のアプローチ)ことが、ワークの主な目的となっています。
いわゆるハウツー本や自己啓発本をあまり読まない身としては、序文や第1章が一番興味深く読めましたが、実践色や啓発的なアドバイスが色濃くなる第2章以降は、やや読みにくさを感じるところも多いほか、哲学者や思想家、文学者など、著名な先人の名前と、キラーセンテンスになるような一節がかなりの頻度で引かれる一方、その選別や配置がやや唐突であることから、箔付け・権威付けのためのつまみ食いのようにも感じてしまいました。
ですが、本書の主だった読者層は人文科学や思想等に親和性の高い層ではなく、自己啓発本やハウツー本に強い関心を持つライト層や、YouTubeチャンネルの視聴者(サトマイファン)が想定されていると思います。それゆえ、初学者に向けたつまみ食い形式になってしまうとはいえ、本書が雑学的な知識として著名人の名前や著作を知るための機会となりうることを一考すると、初読時はノイズのように感じてしまった散漫さも肯定的に捉えられるようになりました。
苦との向き合い方
第1章での問題提起に関する解決策として、第2章では充実する時間の使い方として「自分で変えられることに集中する」「自分の価値観など、内発的な動機を大切にし、行動する」「ストレスを自身の成長の糧にする」(93-94頁)という命題が、古典や心理学の先行研究を踏まえ「充実する時間(人生)の使い方」として提示されます。
ワークが登場する第2章以降は心理療法や認知科学の色合いが強くなり、人文書的な内容が色濃い第1章と比べるとかなり様相が変わります。特に注目したいのは「体験回避」に関わる箇所(109-113頁)です。体験回避は、一時的に生じるネガティブな体験を避けようとするコーピングで、ネガティブな体験、心理的な苦痛や感情体験を避け、本心とは異なる別の行動で不安を鎮めるような反応です。
例としてあげられているものでは、セミナーや企業研修での質疑応答が印象的です。質疑応答では手があがらない一方、終了後には質問の列ができ、同じような質問がくりかえされるというものでした。
「聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥」ということわざがありますが、仕事などでわからないことがあった時、「後できこう」と後回しにするほど、余計聞きにくくなったりすることがありますよね。
このような「体験の回避」は、回避すればするほど、苦痛が大きくなっていき、余計避けようとしてしまいます。そしていずれそれがコンプレックスになってしまいます。
(111頁)
向き合うべき物事や、優先的の行うべきタスクから目をそらし、自己欺瞞や自己正当化による体験回避での時間の浪費(特定の逃避行動による生活の質の低下)とコンプレックスの堆積という負のスパイラルの自覚や、認知行動療法に基づくワークを通じて「認知と行動を変えることで、感情や身体反応、そして結果を変えていく」(100頁)ことで、苦と向き合あえるように自身をコントロールし、本心(価値観)を明確にしながら主体的に行動することが とされ、第3・第4章で実践例が紹介されます。
情報の取捨選択を
統計資料、心理学、認知科学、行動や反応に対する心理・認知分野の専門用語(テクニカルターム)、先人の思想や名言、佐藤さん自身の来歴をベースにしたワークの実践など、本書は非常に多くの情報が詰まっており、初読の際には氾濫する用語に疲弊するかもしれません。
用語についても、やや多めな文章量の中でインデックス的に羅列される箇所が多い印象があるので、逐一理解しようと努め、がむしゃらに暗記しようと試みるのではなく、自身の問題関心や不安に刺さる用語(もやもやとした不安を言語的にカテゴライズし、具象化してくれる箇所)を重点的に読み直すことで、本書で提示されるアドバイスをより効果的に活用できると思います。
やや過剰という印象もある用語や人名の氾濫は、「知る」という点では読書行為に対してのコストパフォーマンスが高く知識の底上げにも有益ですが、高コスパがかえってノイズに感じてしまう可能性もあり、編集者の采配も影響しうる情報量のバランス維持は一筋縄ではいかないということを感じさせられました。
本サイトの記事でも取り上げた田中泰延さんの『会って、話すこと。自分のことはしゃべらない。相手のことも聞き出さない。人生が変わるシンプルな会話術』(2021, ダイアモンド社)は、ハウツーやビジネス本の括りではありますが、文字数や文量が少なく、「値段に対してコスパが悪い」というネットレビューも見かけました。
文量の少ない『会って話すこと』は、ハウツーや自己啓発本の王道的な本書とは対照的に、少ない量の中にある様々な要素の読解スキル、いわば能動的な読みが要求される側面があります。能動的な読みが求められるという工夫は、田中さんが「実質的な共著者」と呼ぶダイアモンド社の編集者であり、文章関連の書籍を多く担当してこられた今野良助さんの采配も影響しているような気がします。
一方、本書は受動的な読みでトリビア的な知識や自己認識に関するアプローチを学び、内省的な観点の獲得や自己啓発へと繋げていくため参考書としても側面が強くあります。冒頭で記したトピックに関心のある方や、時間の浪費や自己の在り方に不安があり、不安を説明する言葉や概念を知りたい(なおかつ、読書習慣があまりない方)という方が手に取りやすい内容になっています。
時間を浪費しがちな状態を変えたいと思いつつ、読書習慣もあまりないので一般的な自己啓発書やビジネス本は敷居の高さを感じてしまう……という方にも、ステップアップやリハビリのためのライトな読み物としても活用できると思います。
人気記事
まだデータがありません。