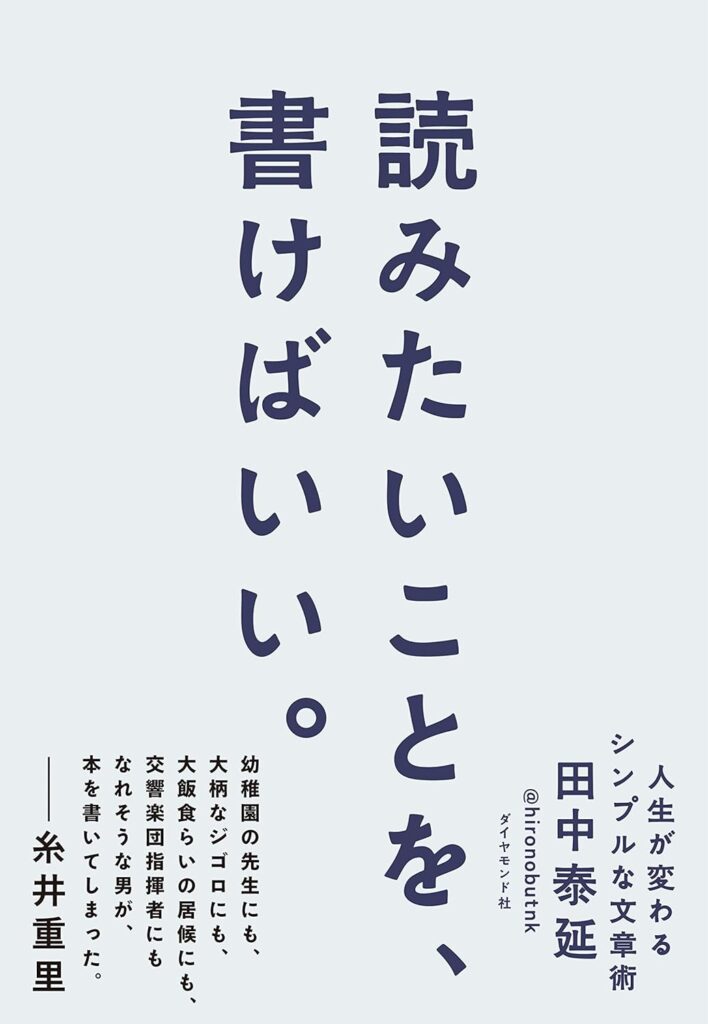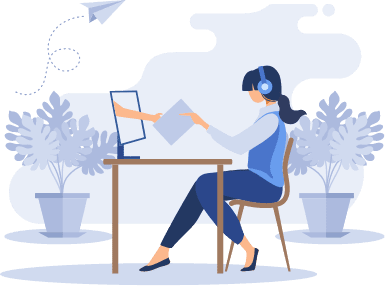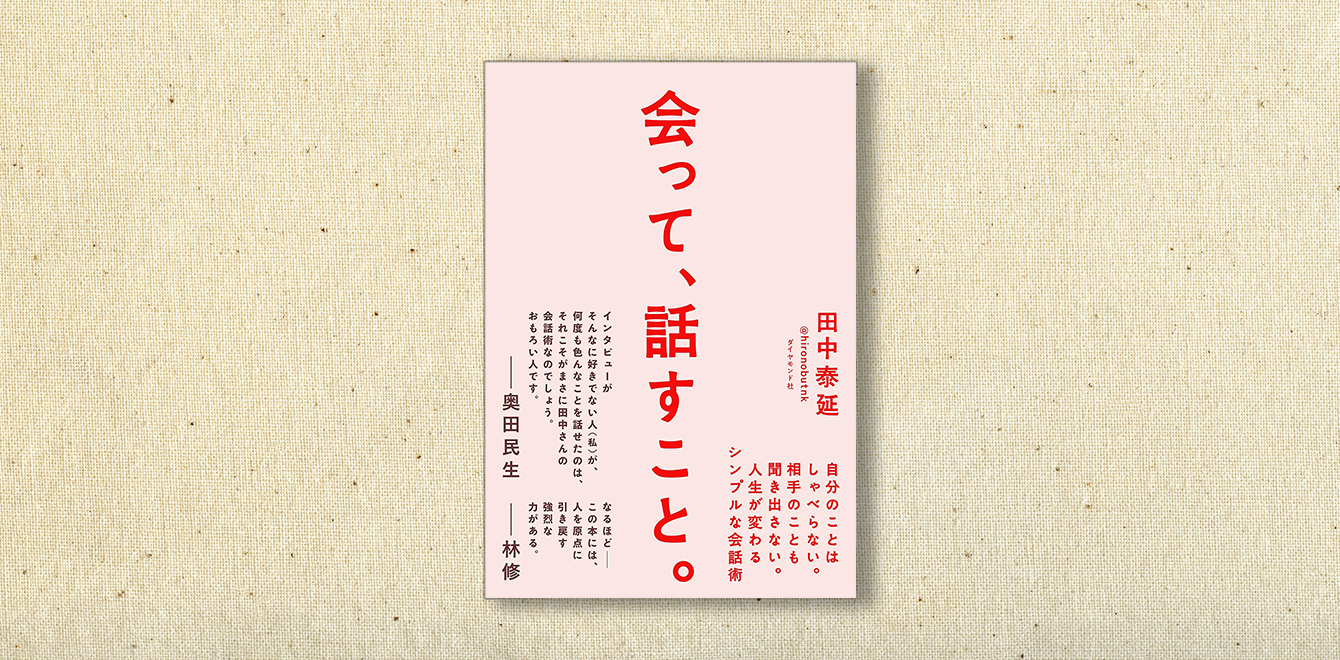
2020年4月に緊急事態宣言が発出された頃、在宅勤務やオンラインミーティングが急速に推進されたことで、ZOOMの操作をおっかなびっくり覚えたり、「会わないで、話すこと。」に対する違和感などを強く抱いていました。ですが、コロナ禍が収まって以降はさりとて違和を感じることもなく、今日では日常的なものとしてオンラインミーティングなどが定着し、「会わないで、話すこと。」に対する居心地の悪さも薄れていきました。
本書『会って、話すこと。 自分のことはしゃべらない。相手のことも聞き出さない。』(2021, ダイアモンド社)は会って話せない状況下であった2021年に刊行され、「会って話すこと」や会話について思索し、「会話することの意義と考え方と意義を問い直す本」(Kindle版, 6頁)です。
ダイアモンド社の編集者である今野良介さんが本書の巻末で「編集者が恐れることのひとつに『内容の陳腐化』があります。本をつくるなら、できる限り永く市場で生き延びてほしいから、時間が経って、内容が時代にそぐわないものになってしまうことを恐れます。(……)その可能性が高くなるとしても、どうしても入れたい情報があります。それが今回は感染症の話でした」(178頁)と述べるように、コロナ禍の最中に刊行されました。「三密」の回避やソーシャルディスタンスが声高に叫ばれた当時と現在では『会って、話すこと。』というタイトルから受ける印象もだいぶ異なると思われます。例として、執筆者の場合はコロナ禍とは別の関心から、2025年3月に本書を読み始めました。
本書を手にしたのは、『会って、話すこと。』というタイトルが「きずな」や関係性についての興味と結びついたのがきっかけであり、そのような興味を持った背景には医師で医療経済ジャーナリストとしても活動される森田洋之さんの提唱する「きずな貯金」に関する記事や、森田さんにご登壇頂いたオフサイトセミナーに関する記事の執筆がありました。
著者の田中泰延さんは電通在籍時にはコピーライターやCMプランナーとして活動され、2017年からフリーランスとして活動されています。最初の単著は2019年刊行の『読みたいことを、書けばいい。人生が変わるシンプルな文章術』(ダイアモンド社)で、本書『会って、話すこと。 自分のことはしゃべらない。相手のことも聞き出さない。』(2021, ダイアモンド社)は『読みたいこと』の続編的な位置付けです。 著者は田中さんの単独名義となっていますが、序章と巻末に文章を寄稿し、ダイアローグパートでは田中さんの相手を務めるなど、編集者かつ「実質の共著者」(182頁)である今野さん(田中さんに『読みたいこと』の企画をオファーした仕掛け人)も本書において非常に重要なポジションを占めており、本書の内容に入る前に共著者(実質)である今野さんについても触れておきたいと思います。
編集者兼(実質的)共著者の今野さん
最近は書籍の情報は新刊・既刊を問わずSNSで偶然目にした投稿で知ることが多くあり、SNSへの投稿も出版社や著者だけでなく、編集者からも行われています。つい先頃(2025年3月中旬)、偶然流れてきた投稿で興味を持った高橋久美子『いい音がする文章 あなたの感性が爆発する書き方』(2025, ダイアモンド社)で、今野さんが担当編集をされていることを知り、より興味を惹かれました。また、今野さんの担当最新刊である井上慎平『強いビジネスパーソンを目指して鬱になった僕の 弱さ考 』(ダイアモンド社. 2025) も3月に刊行されました。
今野さんを知ったのは、ワタナベアニ『カメラは、撮る人を写しているんだ。』(2024, ダイアモンド社)関連の投稿をXで拝見したのがきっかけでした。後に知るのですが、石黒圭『ていねいな文章大全 日本語の「伝わらない」を解決する108のヒント』(2023, ダイアモンド社)、田内学『お金の向こうに人がいる 元ゴールドマン・サックス金利トレーダーが書いた 予備知識のいらない経済新入門』(2021, ダイアモンド社)など、既に読んできた本も担当されており、タイトルに関心を持って購入した本書『会って、話すこと。』でも今野さんのお名前を拝見して驚かされました。
今野さんの手がけた書籍にはインタビュー(「編集者の時代 第6回」, 2023年11月9日, CORECOLOR.JP)でも触れられているように、文章あるいは言葉にまつわるものが多いのが特徴で、SNSに偶然流れてきた投稿とタイトルで興味を持った『いい音がする文章 あなたの感性が爆発する書き方』も、まさに文章についての本でした。
このほかにも、今野さんの特色といえばSNS(特にX)やnoteでの積極的な情報発信で、『カメラは、撮る人を写しているんだ。』(インタビュー内で触れられている「写真の本」)の刊行前後の頃、今野さんが新刊についての情報やご自身で撮られた写真を継続投稿されているのを拝見し、今野さんのお名前や活動が強く印象付けられました。
ビジネス書やハウツー本では会話術が人気のテーマ
本書は田中さんが執筆を担当される、「会話」の意義や効能について、会話術コラム、会話を円滑に進めるためのポイント・着目点などに言及されるメインパート、今野さんが編集者の立場から記した序文と巻末のサブパート、提起されたポイントを実例から読み解く実践パートともいうべき田中さんと今野さんによるダイアローグなど、複数のパートから構成されています。
「ダイアモンド社」から刊行された「会話について」の「ビジネス書」という括りになる本書ではありますが、構成は理論建てた一本道ではなく、とりとめのない話や脱線につぐ脱線(それこそが「会話」の重要なポイントです)が展開されるダイアローグなどは一般的なビジネス書に比べると非常にゆるく、仰々しさや成功のためのハウツーを啓発的な論調で展開することもありません。ビジネス書然とした内容を期待する人はやや面を食らうかもしれませんが、田中さんの軽快な文章技巧が冴えわたる内容となっているので、とてもスピーディーに読むことができます。
一般書の比べると文量や言葉は少なめなので(田中さんのインタビューによれば、「受け手に対する信頼」)、あまり本を読まないという人でも軽快に通読できると思います。また、部分部分には重要なポイントがしっかり織り込まれ、読み落とさないよう大き目のゴシック体で強調されるという親切なデザインになっています。
本書で展開される会話術のポイントは巷に氾濫する一般的なビジネス会話術の逆張りともいうべきアプローチで、田中さんは話し方の本にみられる傾向について次のように指摘されます。
どの本にも「聞き方が大事」「相手の言っている内容を理解する」「話を聞いていることを相手に伝える」「何言っているかわからなくても頑張る」「別に知りたくなくても必死に質問しろ」など判で突いたように書いてある。(……)他人の話を聞くということは、ここまで注意されて訓練を積まなければできないことなのだ。これは、「結局、人間は他人の話を聞きたくない」ということではないか。
(32-33頁)
田中さんが前提とするのは「わたしの話を聞いてもらわなければならない」「あなたの話を聞かなければならない」という考えを捨てる(33頁)ことで、そうすることで楽になるという心構えです。そのほかにも、第1章、2章では、田中さんがインタビューを受ける際や対談に臨む際に実践している法則が提示されます。本書の内容は会話を成功させる・失敗しないノウハウの紹介ではなく、会話の持つ効果や構造をゆるやかに分析していくというものです。
効果の分析の中で興味深いのは、ツッコミがマウンティングであるという指摘や、審査員にならないこと(誉めるも貶すも、マウンティングになってしまう)、会話・言葉が行為よりも重いという分析や、「何かの事象や、内面の心象を不完全に相手に伝えることしかできない『言葉』というものの本質」(96頁)が作用するため、どんな発言も誰かを傷つける可能性があるという指摘など、ゆるめな内容の中にシリアスかつ重要なポイントが時たま表れます。
本書における会話術は、ビジネス本やハウツー本に多く見られるような内的でポジティブな啓発よりも、相手にもたらす影響をセンシティブに分析しつつ、後に触れる「誠実」であることを読者に意識させるなど、内容は軽快である一方で言葉がもたらす作用について非常に思慮分別がなされているという印象を受けました。この点はコピーライターとして長らく活動されてきた田中さんと、文章関連の書籍を多く担当されてきた今野さ夫々の知見が存分に活かされていると思もいます。また、田中さんへの連載インタビュー第4回でも言葉によって傷つく/つけられる可能性について語られていますので、こちらもご参照ください。
本書はあちらこちらに迂回する入り組んだ構成になっていますので、会話術の参考やハウツー的に参照するのであれば、一通りの内容に目を通していただき、個々のトピックの中から自身に応用できる箇所を選別されるのが得策かと思われます。
特に着目したいのは、会話術の本に登場する「相手の話をよく聞く」「相手の立場になる」「いいタイミングで相槌を打つ」「相手の言葉を反復する」といったテクニックでは上手くいかなかった体験を踏まえて、田中さんが『読みたいことを、書けばいい。』で提示された、文章書く際の最初で最後の心構えである「正直であること」が会話においても重要となる(14頁)という指摘です。「正直であることは」、「誠実」とも言いかえられ、田中さんは「辞書にあるように、会話が「向かい合って話し合うこと」であるならば、向かい合った相手に対して、正直でいたほうがいい。それは誠実に接するということだ」 (同頁)と指摘されます。
誠実さを持って他者と相対することはビジネスにおいても非常に重要な心構えであり、メリルリンチの5プリンシパル “principal”を引き継いだ弊社の理念である「5バリュー」にも、「誠実さ(Integrity)」という項目があります。では何を持って「誠実」と考えるかは簡単にまとめられませんが本書においては相手に関心を持って接することが重要とされており、不誠実の例としては興味本位で根掘り葉掘りの質問を浴びせることや自分を理解させるため心の内面を相手に吐露することや、世渡りのための相手をおだて上げたり、自分の利益のために相手に「イエス」と言わせるテクニック(14頁)などがあげられています。
本書で論じられる「会話」は具体的かつ特定のシチュエーションに特化したものではないため、プライベートやビジネスといった大分類や、相手との関係性や心理的な遠近、役職や立場といった細かな状況に応じて援用できるもの、できないものは変わってきます。そのため、本書の内容のすべてを実践するなどの欲をかかず、自身に適した部分を取捨選択し、その他は「会話」について考える際の知識(「おもしろい会話」のためのベース)増やすために活用するのが良いかと思われます。
そしてもう一点、非常に興味深かったのは、オンラインミーティングに関するくだりです。
オンラインのダメさというのは、「身体がない」ということに尽きる。リアルでは、向かい合う人間が時間と空間を共有し、目線、表情、反応、間合い、タイミング、チャチャ入れ、ヤジ、無駄話、そういうものがタイムラグなしの情報として存在し、わたしたちはリアルタイムでそれに反応する。
それに対しオンライン会議では、そもそもなにかの「アジェンダ」を進行・解決する場として設けられることが多く、上記のように臨機応変に話が変化していくのではなく、「もはや異論のないこと」を確認する場になりがちだ。会って顔を見て頼み込みたいことも人間にはあるが、オンラインではやりにくい。(……)なぜかオンラインでは、「自分の顔」を画面に表示する設定が基本になっていることが多い。有史以来、人間が自分の顔を見ながら他人に話しかけることがあっただろうか。それもまた、妙な自意識に繋がって、話しにくい原因のひとつだ。かといって相手の顔だけ表示する設定にすると。オンラインでは意外に不安になる。
(151-152頁)
オンライン会議では、時候の挨拶も、今日の天気の話題もなく、冗談もなく、いきなり当日のアジェンダが話し合われる。ディスプレイの中、数センチ四方に表示された相手の顔。そしてなぜか表示される「話している自分の顔」。まるで人間が機械の一部になってしまったかのような気さえした。もう日常会話は不要。人間は生産性を高めるためだけにコミュニケーションしていればいい。
(180-181頁)
オンラインミーティングが日常的なものとなった現在では、いつのまにか「そういうもの」として納得していましたが、引用部にもある確認の場としての(いわば儀礼的な)会話という特性は、「会って、話すこと。」との比較によってより明確になります。加えて、緊急事態宣言下でZOOMを使うようになった当初、強烈に抱いていた違和感の原因が「自分の顔を見ながら他人に話しかけること」だったということに気づかされました。
その一方で、どうしても味気なくなってしまうオンラインミーティングに、本書で提示される会話的な工夫を意識的に取り入れるようにすると、アジェンタ確認の場として儀礼的になりがちなオンラインミーティングが多少なりとも和やかな空間になるかもしれません。
弊社は東京、名古屋、大阪にオフィスを構えているため、全体のミーティングや各オフィス間のミーティングはオンラインで行っておりますが、2023年3月より様々な講師をお招きして年3回ほど開催しているオフサイトセミナーでは、参加希望の社員・所属IFAが東京に集まり、懇親会などで「会って、話すこと。」に繋がっています。
オフサイトセミナーの継続開催は、講師の方の講演を聞いて見識をより深めていくことはもちろんですが、普段はオンラインでの会話が中心となる別オフィスのメンバーと顔を合わせて会話する機会を設け、交流やチームワークを促進させるという点でも弊社にとって重要な意味を持っています。
会話術本のような、自己啓発本のような
本書はハウツーを伝授してくれるシンプルなビジネス本とは異なり、能動的な読み方や活用が求められる部分があります。そういう点でも、掻い摘んでの再読や会話について何か思うところがあった際に通読し直してみると、思わぬヒントが見出るかもしれません。
おじさん2人(田中さん&今野さん)の仲睦まじい雑談の中(ダイアローグ)の中にも会話術の実践を見出し、会話の構造や影響を理解しながら「誠実」という精神性を獲得するための心構え、とりわけ万能感の錯覚に陥らないことや相手に対する気遣いを発見するなど、重要なポイントが多数あります。本書は軽快な内容で一気に通読できるほか、気になったトピックをつまみ読みできるような構成になっており、田中さんは冒頭で、次のようなことに苦しんでいる本書を読んでもらいたいと記されています。
・自分のことをわかってもらおうと苦しんでいる人
・他人のことをわかろうとして苦しんでいる人
・他人を説得したいと思って苦しんでいる人
・他人を思い通りに動かしたいと思って苦しんでいる人
・他人にもっと好かれたいと思って苦しんでいる人
・会話でもっと学びを得たいと思って苦しんでいる人
・会話でもっと笑いたいと思って苦しんでいる人
(15頁)
冒頭(33頁)では「人間は他人の話を聞きたくない」という前提が示され、「わたしも話を聞いてもらわなければならない」「あなたの話しを聞かなければならない」という会話術の本に多く見られる発想を捨てるという提案が記されます。
変な気負いをせずに会話に臨む・楽しむ柔軟性が苦しみの軽減に繋がっていくともいえますし、気負いを解消するためのノウハウが本書を通じて見出せるかも知れません。また、シンプルな読み物としても(特に田中さんと今野さんのダイアローグが)非常に面白い本ですので、まずは本書の刊行に絡めた田中さんのインタビューに目を通していただき、思うことがあったり、第3回・4回でのおじさん2人の掛け合いにクスッとしてしまった方にはぜひ推薦したい1冊です。
人気記事
まだデータがありません。