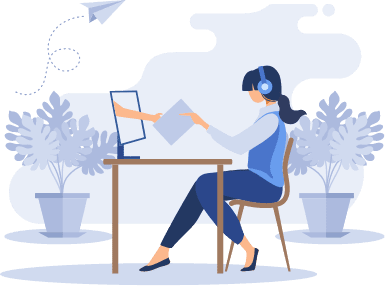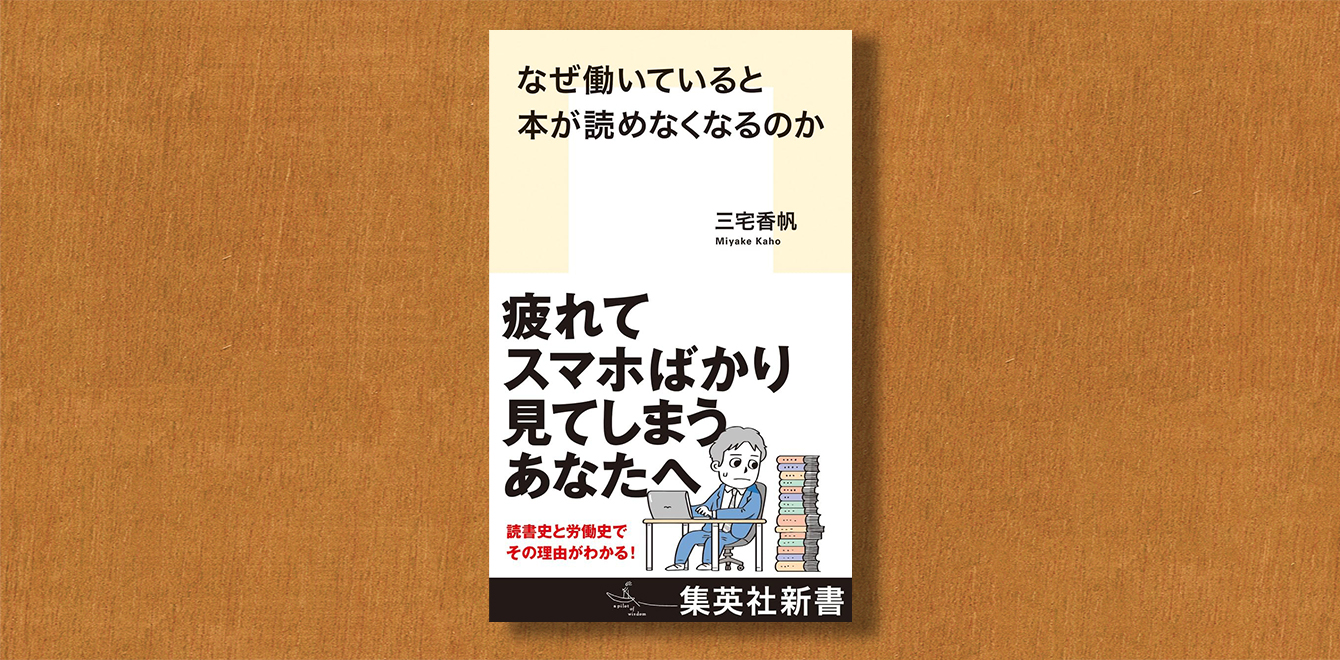
近頃は紙の本を読む習慣がめっきり減ってしまい、図書館や書店に通う頻度もだいぶ少なくなってしまったが、活字本も雑誌もマンガも、電子書籍ではとりあえず読み続けているという方は少なくないと思います。そういったモヤモヤを抱えている人に対して、本書のタイトルや帯のギャッチコピーが辛辣に刺さるものがあり、非常に気になっていた一冊です(筆者はKindle版を購入)。
本書のタイトルから、働きながらの読書習慣を復活させるためのライフハックやハウツー本のように思う方も多いかもしれません。ですが、本書は読日常生活に使えるトリビア集ではなく、近現代における「教養」の価値付けや、読書文化と労働との関係性を変遷に着目した社会史的な内容のを扱っているので、便利さや使用価値に対して過度な期待を寄せる方は、やや肩透かしを食らうかもしれません。
ですが、1970年代(第5章)~2010年代(第9章)にかけての、ベストセラーや労働環境、そして「教養」(特に80年代にブームとなったカルチャーセンター)や読書の機能や意味性のダイナミックな変化は非常に興味深く、各章で言及される年代の代表的なトピックが強く記憶に残っている方も面白く読めるのではないかと思います(まずは目次に目を通されたし)。
「教養」と「修養」
本書ではまず、大正期頃まではエリート階層のための「教養」と、労働者階級向けの「修養」(福沢諭吉の『学問のすゝめ』における「学問」は文学よりも実学を指し、「修養」に近いものともいえます)が個別なものであったことを確認し、戦後になって労働者階級が階級上昇を行うための手段に「教養」が結びついていく過程が論じられます。
明治から大正にかけてのベストセラーの代表格は、才能や階級に縛られない自助努力によるサクセス・ストリーを集めたサミュエル・スマイルズ『西国立志編』(中村正直 訳、1871年、原題は『自助論』)で、その中でCultivation、culture、cultivateなどの訳語として「修養」という言葉が使われました。また、当時の「修養」や『西国立志編』は男性の立身出世のモデルないしは自己啓発本的な役割を持ち、今日のビジネス系の啓発書の源流とも目されているそうです。
明治後半では『実業之日本』(1897創刊)や『成功』(1902創刊)など、「修養」をフィーチャーした雑誌が人気を博しましたが、主に〈労働者階級の男性〉が読者層とされていました。また、エリート階級は「修養」を主題にした労働者階級向けの雑誌があることを知らないというケースも、夏目漱石「門」(1910)の一場面を引いて紹介されます。
戦後は働きながら定時制高校に通う青年たちが「教養」を求める一方、定時制高校に通えない層は『葦』や『人生手帖』といった「教養」について語る「人生雑誌」を愛読し、同誌に投稿が掲載されることで、学歴のコンプレックスを和らげていたとされます。また、世間的にも「教養」熱は高まっており、1950年代初頭に(インテリアとしても)人気を博した文学作品の「全集」ブームや文庫本の普及もそれに拍車をかけました。その背景には用紙の割当制が解かれて紙の価格が高騰したため、新しい形態の商品を工夫する必要があり、大口商品である全集や、少ない紙で制作できる文庫版の考案などの工夫もあったといわれています。
時代を象徴するベストセラー
本書の前半~中盤では、時代による読書行為の効能・機能の変化や、「教養」と「修養」という2つの軸が、階級格差に基づいた対比的な関係から、(主に教養)が開かれたものになっていく過程を辿っていきます。
今でいえば新書のように手軽な内容かつ、多忙なモーレツ社員でも読みやすい内容かつ現代の自己啓発本のように直接的なタイトルの本が、高度経済成長期に人気を集めていました。三宅さんが取り上げた例としては、坂本藤良『日本の会社――伸びる企業をずばりと予言する』、1961、カッパ・ブックス)などで、そういったハウツー本はサラリーマン小説と共に、サラリーマンが電車の中でさらっと読める本として広まっていきました。
1970年代頃からは景気や時代も雰囲気を反映したような作品が人気を博していました。不景気な時代を背景に高度経済成長期へのノスタルジーが重ねられた作品として、立身出世の物語である司馬遼太郎『坂の上の雲』の〈文庫版〉のブームとなりました。その一方、経済不況や社会的不安が如実に反映されたとも解釈しうる五島勉『ノストラダムスの大予言』(1973)、小松左京『日本沈没』(1973)なども、時代を象徴するベストセラーとして取り上げられます。
80年代は「教養」を求める層のジェンダーバランスの変化、2000年代では労働観を通じた自己実現という命題の登場(村上龍『13歳のハローワーク』など)や、インターネットの普及・定着や社会的なヒエラルキーを転覆させる要素としての「情報」の収集・共有/提供・利用(中野独人『電車男』など)といった注目点もありますが、個人的に強い関心を持ったのは、1995年頃の転換点です。本書では時代を象徴するベストセラーを辿っていくため、社会的事件(95年でいえば阪神大震災やオウム真理教)への言及はありませんが、労働や経済に焦点を当てているため、高度経済成長、オイルショック、バブル崩壊、新自由主義との関連で、読書行為とその意味性の変化が分析されます。
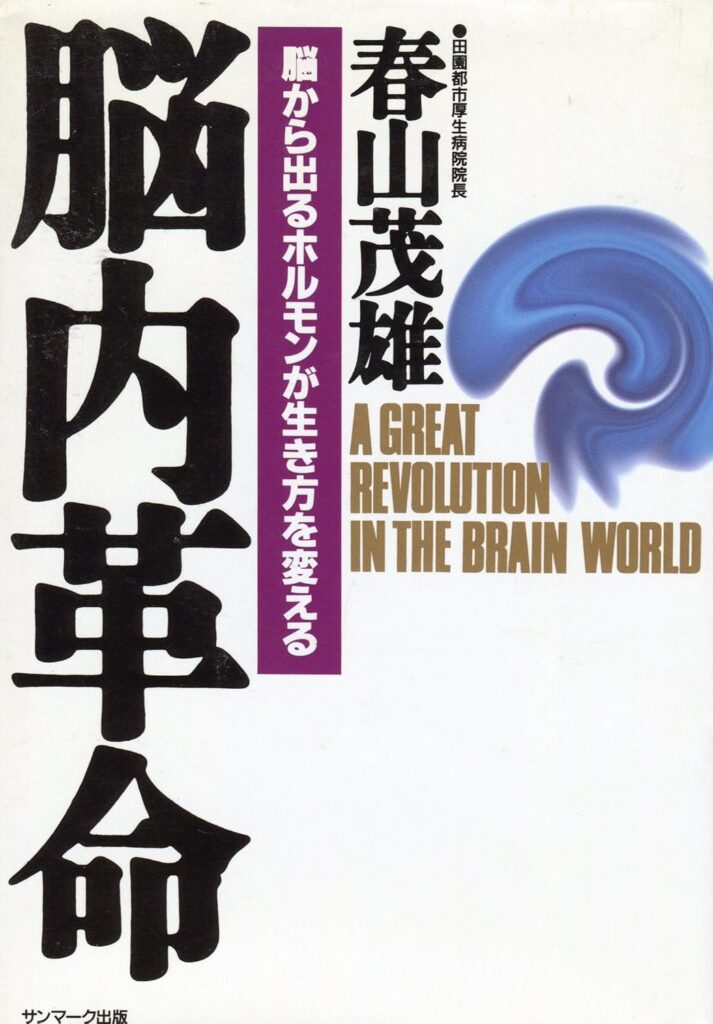
1995年は春山茂雄『脳内革命-脳から出るホルモンが生き方を変える-』(サンマーク出版)ベストセラーとなり、行動を促す自己啓発本のブームの嚆矢となったと指摘され、それまでの『西国立志編』や、『坂の上の雲』や『竜馬が行く』といった司馬遼太郎作品が「心構え」や「姿勢」、「知識」といった〈内面〉のありかたを説いたのに対し、90年代の自己啓発本は読者が取るべき〈行動〉を明示するという差異がありました(Kindle版131-132頁)。
三宅さんは内面から行動への転換が生じた原因を、経済や労働環境の変化に見出します。バブル崩壊の影響で、終身雇用制や高度経済成長期に整えられた日本型の企業労働モデルが、就職氷河期や非正規雇用の増加へと代わり、経済は自分たちの力では変えられず、変化の波に乗れるか否かが成否を分けるという感覚が広まる中で、システムを変えるような大きな力学ではなく、『脳内革命』というポジティブ思考の〈行動〉で自分を変える自己啓発書が人気を博しました。
時代による変遷を見てみると、階級上昇の手段としての読書=社会的な場への関心・参与が私的な空間への収束に変わり、近年になるにつれ、読書に求めるものがポジティブな〈行動〉を促すための情報接収から、コスパが良く、インスタントで、ダイレクトなハウツー本へと消費へと急速に変化してきたという印象を受けます。
自己啓発書とノイズ
多方面から読書離れの声が聞こえる今日においても自己啓発やハウツー本の人気は衰えておらず、インスタントかつ即物的な情報の氾濫に辟易することは少なくありません。経済やビジネス関連の書籍ランキングをAmazonで見てみると、言い切りかつ断定的なタイトル(YouTubeの動画タイトルのようにも似ています)が並び、タイトルの通りに行動すれば成功するというような勧誘を受けている気にさせられます。
本書の中で特に興味を惹かれたのは自己啓発本についてのくだりです。自己啓発本は「ノイズを除去する」という牧野友和氏の指摘(『日常に侵入する自己啓発―生き方・手帳術・片づけ』、勁草書房、2015)を引き、自己啓発本は自己の制御的(コントローラブル)な変革を促し、社会や他人といった非制御的な要素をノイズとして除去(あるいは自己認識世界の周縁へと追いやる)することが自己啓発本の特徴である一方、読書はノイズを招き入れる体験であり、外部と繋がる/外部を知るための手段でもあると、三宅さんは分析します。
自己啓発にのみ執心し、ノイズを徹底的に排除するような状態は、本サイトの記事でも頻繁に登場するオルテガ『大衆の反逆』の中で指摘された「忘恩」や「無根拠の全能感」といった「大衆」的な要素を抱きやすくなるという感想を抱いたのですが、そう思うこと自体がすでにノイズを取り込んだ状態であると言えるでしょう。
断片的な情報とファスト志向の現代
インターネットが主流となる2000年代の傾向について、三宅さんは「昭和的な一億総中流社会が崩れ去り、バブル崩壊やリーマンショックなどの景気後退、そして若者に貧困が広まる中で、『階級を無効化する』知識の在り方が求められていた。文脈も歴史も教養も知らなくていい、ノイズのない情報。あるいは社会情勢や自分の過去を無視することのできる、ノイズのない自己啓発書。それらはまさに、自分の階級の低さに苦しめられていた人々のニーズにちゃんと答えていた。」(158頁)と述べます。かつては階級によって隔てられていた「教養」と「修養」は現代ではハイブリッドなものとなり、それらを支える「知」よりも、前後関係や文脈といったノイズを排除した〈インターネット的情報〉が主流となっています。
三宅さんは情報を「ノイズの除去された知識」(160頁)と定義します。情報の効率的な処理(あるいは消費)といえば、「ファスト映画」(稲田豊史、『映画を早送りでみる人たち ファスト映画・ネタバレ――コンテンツ消費の現在形』、2022、光文社)や、速読などがあげられ、本書の序章でも速読についての言及があります。また近年では「ファスト教養」(レジー『ファスト教養 10分で答えが欲しい人たち』、2022、集英社)のようにタイパ(タイムパフォーマンス)重視の情報摂取/消費を象徴するような用語もなどもあります。
情報として簡素化されたものであっても、他の文脈に触れる事が自分の外側にあるノイズに触れる入口になる可能性が開かれているとして、三宅さんは情報消費者の潜在的能動性を肯定的に評しています。
2010年代はSNSの本格的な普及があり、それによって読書量が減ったと思われがちですが、上田修一氏の調査(「大人は何を読んでいるのか―成人の読書の範囲と内容」)によれば、読書量が減ったと答えた35.5%のうち、SNSの影響を挙げた人が6.2%、仕事や家庭が忙しくなったとあげた人が49%であり、仕事や家庭の忙しさが読書量の減少原因と考えていることが確認されました。

新自由主義時代における労働と時間
1980年代以前では、労働や社会的地位の上昇に役立つ「知識」を得る(ノイズに触れる)ための媒体だったので、長時間働く人も本や雑誌を読めていましたが、90年代以降は自分に関係のある情報を探し(ノイズの排除)、それを基にした行動が労働や成功に必要なものとなったと、三宅さんは分析します。
日本企業の残業を前提にした長時間労働は、高度経済成長期ではまだしも現在においては非効率的なものであり、長時間労働が本を読む時間的な余暇を奪っていると考えられます。ですが、長時間労働はあくまでも一側面であり、新自由主義社会下における個々人の心持ちや、追い込み・燃え尽きなども、読書に充てられる余暇を奪われてしまう要因のひとつと三宅さんは指摘します。
最終章では、新自由主義下の現在を読み解くためのキーワードや概念が、他の章に比べて多くでてくるため、用語に馴染みのない方はやや読みにくさがあるかもしれません。内容は成果主義、競争、主体(および自己責任)の捉え方などで、言葉を字義通りに捉えて考えるよりも、身近な事例や自分自身の経験を例にして考える=「知識」を活用して理解することが重要になると思います。
最終章で登場する主な用語は下記になります
・「疲労社会」(ヒンチョル・ハン、横山隆 訳『疲労社会』、2022、花伝社)
・「燃え尽き(バーンアウト)」症候群(ジョナサン・マレシック、古嶺英美 訳『なぜ私たちは燃え尽きてしまうのか――バーンアウト文化を終わらせるためにできること』、2023、青土社)
・「トータル・ワーク」(ヨゼフ・ピーパー、稲垣良典 訳『余暇――文化の基礎』、エンデルレ書店、1961年)
・「『全身』のコミットメント」(ジョナサン・クレーリー、岡田温司 監訳・石谷治寛 訳『24/7: 眠らない社会』、2015、NTT出版)
いずれも現代社会の様々なケースにあてはまる事例を取り上げており、その多くは競争原理や他者との比較などを通じて自分で自分を追い込んでしまう状態、本書の言葉でいえば「頑張りすぎてしまう」構造によって生じています。「『働きながら本が読めなくなるくらい、全身全霊で働きたくなってしまう』ように個人が仕向けられているのが、現代社会なのだ。」(194頁)と三宅さんがまとめられるように、「頑張りすぎてしまう」「働きたくなってしまう」という意識は、頑張らなければいけない=頑張れない/頑張らない/成果が出せないのは自己責任であるという、新自由主義的な競争原理から生じるものといえます。まず必要とされるのは「頑張りすぎてしまう」「頑張らない/成果が出せないのは自己責任」といった現代的な価値規範が、さも普遍的な常識であるかのように錯覚してしまう状態から距離を取ることであり、三宅さんは「全身のコミットメント」や「全身全霊」の信仰や、それを賞賛する潮流には批判的な立場をとり、「半身のコミットメント」=「働きながら本が読める社会」(読書も全力ではなく、半身の取り組みを肯定)をつくることを提言されます。
もちろん就業スタイルや賃金体系、職種によっては「半身」に移行することは容易ではありません。三宅さん自身も広く実現可能なアイデアを本書の中で提示することは難しということを踏まえたうえで、あくまでも読者への提言として、「半身のコミットメント」や「半身社会」のあり方の実践を促します。本書の主題が読書であるため、働きながら本を読むためのもとして半身の余暇は想定されますが、読書に限らず様々なものにコミットすることも合わせて説かれます。
冒頭でも記したように、本書は働きながらの読書習慣を復活させるためのライフハックやハウツー本を提案するものではなく、広い範囲に渡るノイズが入った本です。そのため、人によっては関心が刺さるトピックに差異があるとは思いますが、「教養」と「修養」を現在に置き換えて考えるための契機を与えてくれると思います。
本書は労働と読書の歴史を辿っていく内容であるため、情報量もかなりのものになります。最終章は他の章と比べややあちらこちらに焦点がぶれ気味な印象がありますが、三宅さんの文章は軽快かつ読みやすいので、読書習慣がなくなって久しいという方でもスムーズに読めると思います。
最終章で取り上げられた本の中でも、ヒンチョル・ハン『疲労社会』や、ジョナサン・マレシック『なぜ私たちは燃え尽きてしまうのか』は、キャッチ―なテーマが取り上げられているほかKindle版も配信されているので、本書で久々に読書をしたという方が次に読む1冊にも適していると思います。
追記
本書のあとがき部分では、労働と読書の両立するためのアイデアとしていくつかのライフハックが紹介されています。その1番最初に出てくるものが「iPadを買う」という提案です。
本サイト内の記事「雑誌とサブスクリプション」でも書きましたが、筆者の現在の読書環境は、7-8割型がiPadでの読書(ほとんどはKindle本)であり、電書化されてない古めの本や学術書などは、新品で手に入ることも少なく古書あるいは図書館で手に入れるので、必然的に紙での読書となります(最近古書で手に入れたものは2015年刊行の『別冊ニュートン 光と色のサイエンス』など)。
長年の読書習慣で、紙の本を読むための身体感覚に馴致していた身としては、持ち運ぶのにも一苦労な技術参考書(映像編集やデザイン関連)以外は。紙の方が……と思っていましたが、iPadと電書/Kindleの快適さ、特にタブレット端末1台の重量で大量の本を持ち歩けることに慣れてしまうと紙の本に手を伸ばす機会からも疎遠になってしまいます。とはいえ、紙と電書の違いはあれど本を読む・知識を得たいという欲に変わりはなく、むしろAmazonで商品を検索・注文するのと同じ手軽さで電書を購入できるので、頻繁に開催されるまとめ買いセールの際に、思わず買いすぎてしまうことも多々あります(物理的に積まれていないのですが、積読になります)。
そういった点では、iPadは労働と読書を両立するうえで非常に便利なツールであり、読書習慣を再度身に付けたいと考えている方の読書欲を支えてくれると思います。
執筆者: 鈴木真吾