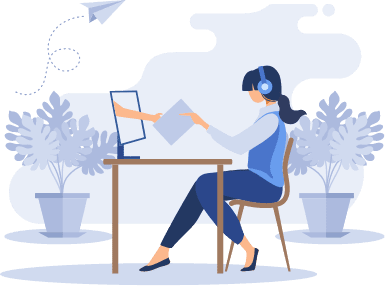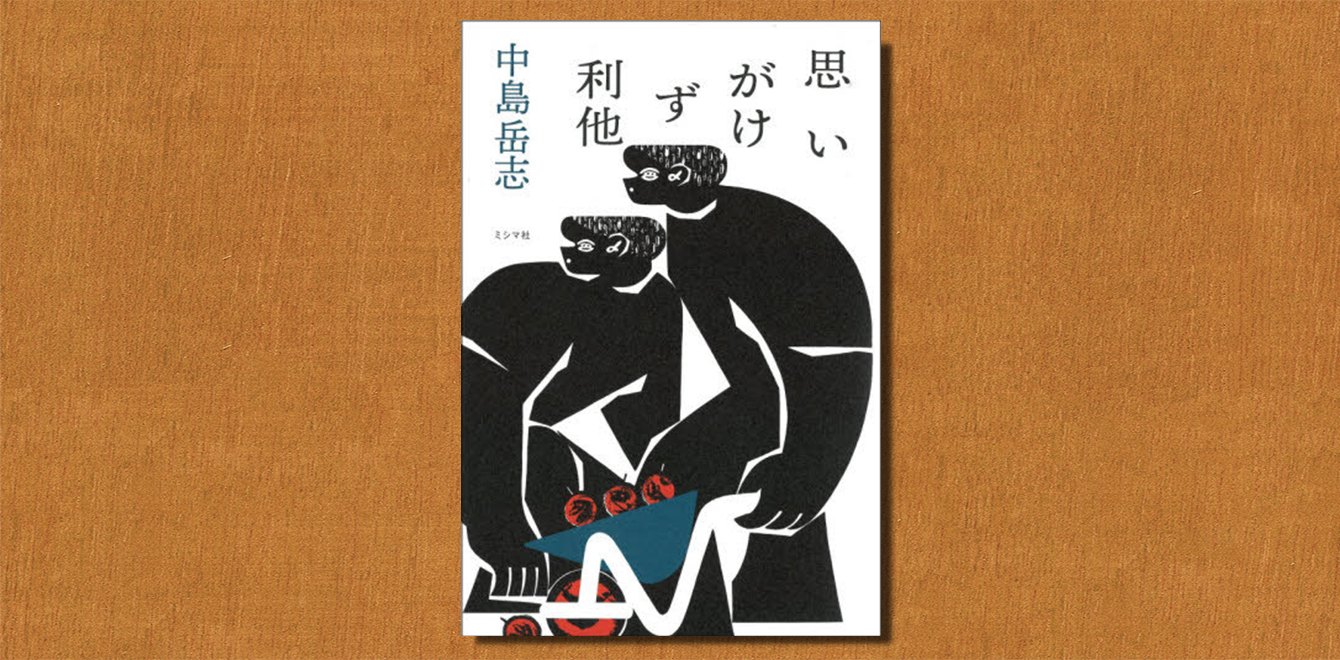
『思いがけず利他』は、東京工業大学 未来の人類研究センターの「利他プロジェクト」初期メンバーとして活躍された中島岳志さんによるweb連載エッセーを再構成し、書き下ろしを加えたものです。
利他をテーマにした本書は、落語「文七元結」に始まり、親鸞の思想、ヒンディー語における「与格構文」、料理論、ケア、偶然性など様々な切り口から取り上げられます。
※「与格構文」は、「私」を行為主体ではなく、行為や感情が留まる器のような客体として捉え、己の意思や力が及ばない領域から湧き上がってくる現象について表現する構文で、「私〈は〉~だ」は、「私〈に〉~が留まっている」と表現される。例として、「私は嬉しい」は「私に嬉しさが留まっている」と表現。参考記事: 中島岳志「利他的であること」(第8回 与格-ふいに その1)
近年はコロナ禍を通じて、利他的な行為やエッセンシャルワーカーに対する感謝への関心が高まりをみせているほか、中島さんも共著者として名を連ねる『利他とは何か』(集英社、2021)の中で、ビジネスだけでなく若い人たちの間、例えばファッションの世界においても、廃棄される衣服、染料による環境汚染、開発途上国の縫製工場における低賃金での労働などを背景に、利他主義への関心が高まりをみせるという事例が、同書の序論と第一章を担当された伊藤亜紗さんによって紹介されるように、近年は様々な文脈において利他への注目が集まっています。
中島さんはその状況を肯定的に捉えつつも、利他行為に内包される押しつけがましさ、権力性、偽善、打算などの負の側面を注視したうえで、利他の本質には「思いがけなさ」(人間の意思とは関係なく、偶然やってくるもの)があるといい、それは将来的な自利に繋がることを期待しての利他、つまりジャック・アタリが提唱した「合理的利他主義」(rational altruism)とは異なる「利他」を指します。
人類がサバイブするためには「合理的利他主義」という理想への転換が必要だとアタリは説きますが、中島さんは見返りや自利が戻る「間接互恵」な関係を期待する合理的な利他行為は自分が利他だと思う行為を相手が受け取ってくれるという前提に基づいており、利他の内包する負の側面が顕著になってしまいます。
本書で言及される利他は様々な面で「合理的利他主義」(未来への投資)と相反するもので、過去への感謝や、無意識(思いがけなさ)、偶然性などが特徴的なトピックとして取り上げられます。
全体としては平易かつ読みやすい内容で、落語や「NHKのど自慢」の伴奏など、身近なトピックも随所に登場します。とはいえ、第1、2章の後半部、4章の中~後半部は、思想や哲学的な議論の比重が増していくため、「主体」などの用語に馴染みのない方は敷居の高さを感じるかもしれません。ですが、自身のあり方(特に4章の「私が私であることの偶然性」に関するくだり)や、近年過剰に沸き立つ自己責任論を戒める「自分が他人であった可能性」に関する想像力への言及など、本書は日々の出来事を見つめ直し、世論の声に安易に流されないための意識構築に役立つような、気づきを提供してくれます。その中でも、過去からの贈与/現代における被贈与に対する感謝=死者との対話に関する箇所(131-134頁)は非常に興味深く、交通や生活にまつわるインフラに対してもこれまで見落としていた観点を示唆してくれるので、難解と敬遠せずに長期的スパンでの読解を薦めたい一冊です。
「利他」と「利己」
本書のテーマである利他は、「利己主義(egoism)」の対となる概念です。オーギュスト・コントが19世紀半ばに提唱した「利他主義(altruism)」は他人の幸福や利益を優先するだけでなく自己犠牲的なニュアンスをも含んでいます。ですが、伊藤さんがファッションを例にして述べるように、今日における利他は宗教的な価値観(浄土宗の「他力」、キリスト教の「隣人愛」など)との結びつきが薄まり、その輪郭も曖昧なものとして流布しています(『利他とはなにか』、20頁)。
「利他」という言葉から想像されやすい行動、典型例としてはボランティア、介護や援助、環境・社会問題への取り組み、寄付などは、利己的なもの・偽善的なもの、つまり「合理利的利他主義」に類似したものとして見なされることは少なくありません。
『思いがけず利他』における「利他」は、無意識的・情動的な行動原理でありつつも、「利他」の押しつけが強く出すぎた場合には「利己」に転じてしまうなど、「利他」と「利己」は相反/分割されたものではなく連続して存在するとされています。
現在、大手企業は「社会的貢献」を重視し、様々な取り組みを行っています。例えばSDGs(……)SDGsにかかわり、行動を起こすことはとても大切なことです。/しかし、どこかで「何かうさん臭いな」という気持ちを持ってしまうことはないでしょうか(……)私はそう思ってしまいます。特に「社会的貢献」の成果を、CMや広告でことさら強調されるとどうしても企業の「利己性」を感じてしまいます。 (103-104頁)
引用部は利他的な行動であるSDGsへの参画が、その社会的意義を十二分に理解していたとしても、利己的なものに転じて受けとられてしまうというケースです。中島さんが企業の取り組みに「利己性」を感じる理由に、引用箇所でみられるCMや広告における社会的貢献の強調(押しつけがましさ)があることは明白ですが、もうひとつ重要な点として、中島さんは「利他」は受け取られたときに発動する(与えることではない)=私たちは過去からやってくる他者の行為や言葉を受け取ることで、「利他」を生み出す/起動することができるため、「利他」の時勢は未来であることが指摘されます(129-131頁)。
CMや広告を通じた社会貢献の強調は〈現在〉の出来事です。それゆえ、私たちが企業の取り組みを実感できる形で享受し、それに対して感謝の念を持つ機会がくるまでは、企業の主張は押しつけがましく、単に利己的なものと感じてしまうのでしょう。それと同様、私たちが他人のために何かを成そうとしたとき「これは偽善や押しつけではないか」という自己批判的な意識を抱くかもしれません。ですが「思いがけず」にとった行動は、後になって相手からの感謝によって「利他」として起動するものであるため、「思いがけず」にやってくる行動や偶然性を、素直に肯定的に受け止める意識を持つことが重要になります。
利他の精神と「文七元結」
本書の冒頭と最後には、利他の精神を体現する作品として、落語の「文七元結」取り上げられます。同作は三遊亭圓朝による創作(人情噺のひとつ)で、1889年(明治22年)の『やまと新聞』に速記が掲載、成立は幕末から明治初期にかけての江戸といわれる作品です。
当時の江戸には薩摩・長州の侍が多数滞在しており、彼らに向けて「金離れがいい(宵越しの銭は持たない)」「人情家」「涙もろく正義感にあふれる」「いきでいなせ」といった江戸っ子気質を強調するような描写が多く見られるのが特徴とされています。
文量の関係であらすじ等は割愛させて頂きますが、単的にまとめると〈偶然〉に出くわした他者のために、主人公の長兵衛が見返りや返礼の期待することなく、〈思いがけず〉にとった行動(「贈与」)がまわりまわって利他の連鎖となり、最終的に長兵衛にとっての自利として還ってくるというのが物語の大枠です。
落語の演目は話し手の解釈によって登場人物の行動要因が異なることがあり、「文七元結」では、主人公の長兵衛が「贈与」を行う動機についての解釈に差異が見受けられます。
負債を抱える浪費家の長兵衛は、訪問先で預かった主人に戻す五十両をすられた(実際は訪問先に忘れてきた)と勘違いし吾妻橋から身投げして詫びようとする文七に、娘と引き換えの一時預かり金として借り受けた五十両を押し付けるのですが、その行為に至る理由は大きく2つの解釈に分かれます。
解釈Aは、死んで詫びようとする文七の忠義や「正直さ」「まっすぐな生き方」に長兵衛の心が動かされたとするものです。もうイ一方の解釈Bは、文七への共感ではなく「江戸っ子気質」を理由として明確な理由を提示せず、行動によって江戸っ子の気風が表現されています。
「文七元結」が演じられる際は解釈AとBの混合というパターンが多い一方、中島さんが分析対象として取り上げるのは立川談志が演じたものです。談志の解釈では、人情噺らしい共感の要素が強く含まれる解釈Aの要素を除外して「江戸っ子気質」繰り返し強調するものです。さら偶然に吾妻橋を通りかかったなどの偶発性や運命を贈与の理由し、〈思いがけず〉五十両を押し付けてしまうといったように、長兵衛が贈与を行う動機を人情的な「美談」にしない解釈がとられ、さらには橋に霧がかかり、他者の目がない状況での出来事であるとされます。
本書の中で複数回登場する「文七元結」には、自力、偶発性、業(どうしようもなさ)の肯定など、本書の核を成す要素が多数含まれているだけでなく、「利他」は大きな世界の中で不可抗力的に機能するものであることや、「利他」が「利他」と認識されない次元の「利他」(江戸っ子気質など)として定着しており、談志版の長兵衛はその特異的な位置に立っていることが重要とされます。
与えられたものへの気付き
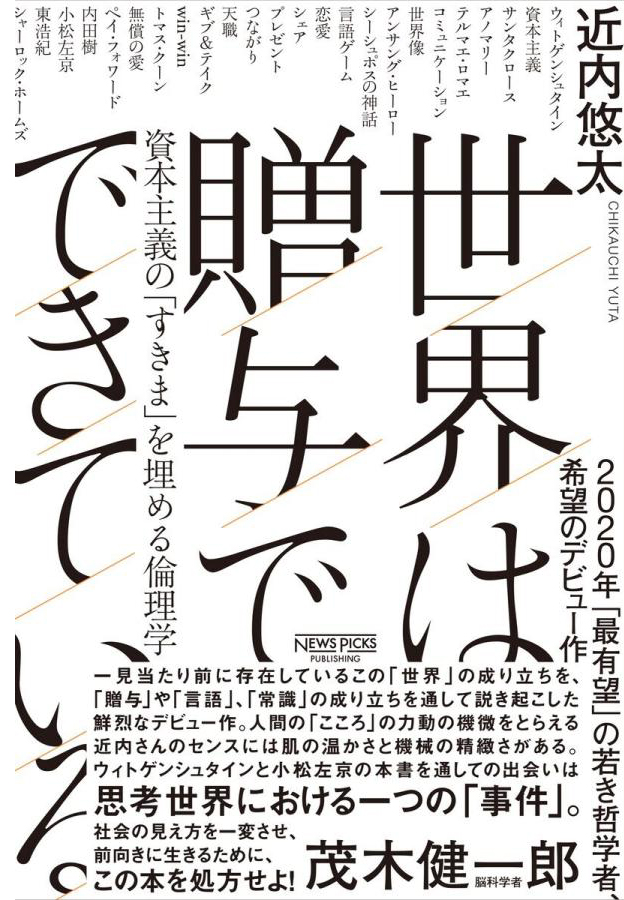
2023年の7月に開催した第2回オフサイト研修(講師: 浜崎洋介先生)や、本サイト内でも取り上げた田内学さんの『きみのお金は誰のため』(2023、東洋経済新報社)に登場する重要な言葉として「贈与」があり、いずれにおいても現代の様々な事象(プレゼント、年賀状、サンタクロースなど)に絡めて「贈与」の構造やその影響などを分析する近内悠太の『世界は贈与でできている』(2020、ニューズピックス)の名前が登場するなど、利他を考えるうえでも「贈与」は重要なキーワードになります。
利他的な行動の代表例としては、与えること(物に限らず、知識・時間など様々なもの)です。与えることは、浜崎先生の講演で取り上げられたエーリッヒ・フロムに倣えば「愛すること」であり、「贈与」でもあり、アダム・グラント『Give & Take与える人こそ成功する』(楠木 健 訳、2014、三笠書房)で取り上げられる「ギブ」でもあります。
いずれの用語も大部分では共通点があり、中島さんが取り上げる「利他」は後述する「与格的な主体」としての受動的な行動(〈私が〉与えるのではなく、私の中に湧き上がってくるものに「駆動させられて」/「思いがけず」与える)であるだけでなく、受け取る側の気付きや感謝によって起動するものとされます。
一般的に、能動的な主体の意思や行為によって「贈与」や利他が行われると捉えられがちですが、近内さんは「贈与」を行う側ではなく受け取る側に着目し、「被贈与の気付き」かによって受け取ったことに対するポジティブな負債感に基づく返礼としての「贈与」が続いていく(『世界は贈与でできている』、41頁)と分析します。中島さんは、自己が受け手(「与格的な主体」であることに類似)になることで利他を生み出すという点で、近内さんの分析した「贈与」は、利他と非常によく似ており、過去からやってくる多くの言葉や行為に気づくことが重要と指摘します(『思いがけず利他』、131頁)。
利他と贈与のいずれにおいても、受けとる側が与えられる(られてきた)ものに気づくための余白を持つ=器としての「与格的主体」になることが求められます。また、利他や「贈与」となる可能性を持った行為をするにあたっても、やはり「与格的主体」であることが必要となるでしょう。
「与格的主体」になること/「貴族」の精神をもつこと
利他的な行為は偽善・打算的かつ戦略的な行動とみられやすく、何かを贈る・与えるなどの行為も「押しつけがましさ」を含み、援助してもらった相手に「負債感」を背負わせてしまいます。さらに贈与に対する対等な返礼ができなければ、与える―貰うという上下関係や支配的構造を生じさせてしまいます。
ですが中島さんは、「思いがけなさ」や、自分の意志とは関係なく生じる超越的なものが利他の本質にあると捉え、「与格的主体」(「~が留まる」存在としての「私」)となること、あるいはそれを「取り戻す」ことや、自力に対する懐疑(無力さの自覚)に至ることが、利他の世界に至る第一歩である(97-98頁)であると指摘します。また、自力に対する懐疑については、当サイトの記事やこれまでのオフサイトセミナーでも取り上げられた古典、ホセ・オルテガ・イ・ガゼット『大衆の反逆』(1930)でも同様の指摘があります。
オルテガの分析する「大衆」は、自分を超えた者=上位規範=歴史に対する畏怖を失ったエゴイストの群れであり、無根拠な万能感、「みんなと同じ」であることを志向する凡俗性、過去に対する「忘恩」(歴史の忘却)が特徴とされますが、「大衆」と対になるものとして、「貴族」(階級的なものではなく精神的態度)、「高貴な生」、「卓越した人間」といった概念が提示されます。
それら「大衆」の対概念は、根拠なき万能感や全能感に支配されず、己の限界を自覚し、自然や歴史といった超越的な存在に仕える意識を持つとされるほか、中島さんが本書の中で分析する利他の精神や「与格的主体」との親和性が多くみられ、いわば非「大衆」的なものである「貴族」的精神や「高貴な生」「卓越した人間」を目標にすることが「利他」の世界を知ることにも繋がっていくと考えられます。
また、西郷隆盛も利他の精神を持つ人として知られています。彼は「天」という超越的な存在を信仰し、行動の論拠としており、「与格的主体」として利他的な行動を遵守することで、他者から信頼や尊敬を集めてきた人といえましょう(詳しくは、「西郷隆盛と動的宗教(2)」をご参照ください)。
東北戦争時に敵対していた庄内藩士に西郷が寛大な処置を施したことへの礼として、庄内藩の藩士らが鹿児島を訪れ西郷の言葉を記したものが、西南戦争で逆賊となっていた西郷の名誉回復後に『西郷南洲翁遺訓』として発刊され、上野公園に銅像が建てられたことも、西郷の利他が後年になって起動した事例といえるでしょう。
利他の支配的な側面
西郷は利他の片面、いわばポジティブな部分を象徴するような例ですが、冒頭でも書いたように、利他には支配や押しつけといった負の側面も存在します。
業界・業態の性質上(顧客との情報の非対称性など)から、顧客の最善の利益を追求するという利他的なものであるべき行動原則が、自社利益の追求や顧客に対する支配欲へと転じて利己的なものになりやすい金融業界を例にすると、リスクを考慮しない短期売買商品中心の勧誘、説明と理解が不十分かつ、勧誘・営業者が自身でそれを買いたいと思わない状態にもかかわらずEB債などの高リスク商品を強気で勧める事例などが思い浮かびます。
『思いがけず利他』の中では、頭木弘樹さんの『食べることと出すこと』における、おすすめの料理を振る舞う場面での共食圧力の例が紹介されます。こちらのケースでは振る舞う側が、自分が美味しく感じたので気にいってくれるという思い込みが、さらに強い圧力をかけることに繋がってしまいます。
「利他」行為の中には、多くの場合、相手をコントロールしたいという欲望があります。頭木さんに料理を勧めた人の場合、「自分がおいしいと思っているものを、頭木さんにも共有しほしい」という思いがあり、それを拒絶されると「何とかおいしいと言わせたい」という支配欲が加速していきました。相手に共感を求める行為は、思ったような反応が得られない場合、自分の思いに服従させたいという欲望へと、容易に転化することがあります。これが「利他」の中に含まれる「コントロール」や「支配の欲望」です(107-108頁)
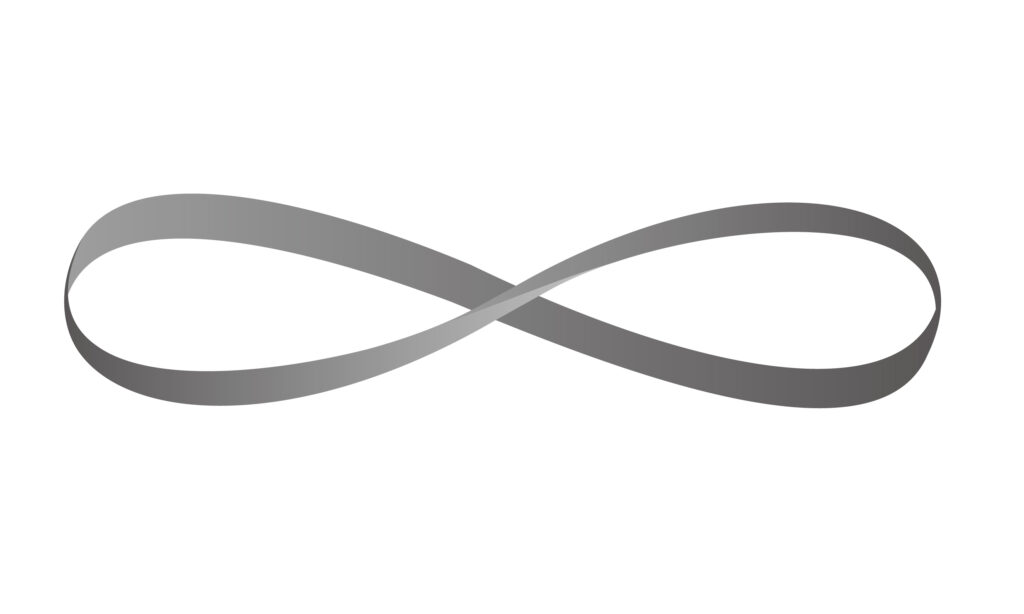
地続き地ものとして存在する「利他」と「利己」は、中島さんによればメビウスの輪のような、表裏一体の関係にあります。それゆえ、金融商品の勧誘にあたっては、「利他」が「利己」に接近しすぎていないかを内観することが非常に重要になると考えます。
ウェルスマネジメントにおいては、各ファイナンシャル・アドバイザーがビジネス的な関係に留まらない深いリレーションシップをお客様との間に構築し、個々のライフスタイルや人生設計・目標に寄り添うような姿勢(『思いがけず利他』では「NHKのど自慢」の伴奏が例に出されます)を意識し、「与格的主体」であることを今一度取り戻し、顧客重視(Client Focus)、個人の尊重(Respect for the individual)という、メリルリンチから引き継いだ弊社の理念と重なる部分も多い利他の精神を発揮する「器」(=「与格的主体」)になることも必要になるでしょう。
利他的であろうとして、特別なことを行う必要はありません。毎日を精一杯生きることです。私に与えられた時間を丁寧に生き、自分が自分の場所で為すべきことを為す。能力の過信を諫め、自己を超えた力に謙虚になる。その静かな繰り返しが、自分という器を形成し、利他の種を呼び込むことになるのです。/いま私は、利他をそういうものとして認識しています。(177頁)
上記の一文は『思いがけず利他』の結びからの引用です。『大衆の反逆』との関連で、これまでも幾度か取り上げてきた「貴族」や「高貴な生」といった精神性は、中島さんの論じてきた利他の精神と非常に似通っており、先の一文に記された人物像はまさに西郷隆盛その人のようだという印象を受けました。
利他の精神を持つこと
本書は利他を通じて「私のあり方」を考えるような部分を含む内容であり、2章以外の各章のハードルは低めです。とはいえ、各章の後半部になるにつれて少し難しくなる印象はあります。ですが、適宜身近な事例なども登場するので根気よく読み進めいけば、他者の利他的な行動を複数の観点で捉え直す、あるいは過去の利他を起動させる着眼点に気づいていけると思います。
FAは「お金のお医者さん」ともよく言われるように、お客様個々人に応じたきめ細かい診断に基づき資産運用の処方箋を提案します。本書で例に出された「NHKのど自慢」の伴奏者の他者の利に与するために寄り添う姿勢も、FAの理想像に近いものという印象を受けました。
「バック・ミュージシャンたちは、歌い手を支配しようとはしません。リズムが狂っていると、矯正するような演奏をするのではなく、その人のリズムに合わせます。(……)利他において重要なのは「支配」や「統御」から距離をとりつつ、相手の個性に「沿う」ことで、主体性や潜在能力を引き出すあり方なのではないかと思います。」(120頁)
「与格的主体」であることは、「貴族」的精神の獲得と非常に近いものを感じており、他者の利に与するビジネス、特にFAや営業職を担う方には、記事内で触れた『GIVE & TAKE』や『世界は贈与でできている』と合わせて読まれることをお勧めします。
人気記事
まだデータがありません。