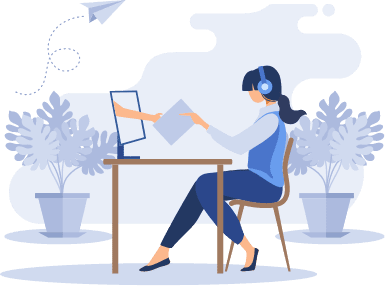5バリューアット株式会社は、日本のIFA(金融商品仲介事業者)を変えたいとの理想の下に、代表斉藤彰一が立ち上げた企業です。
当社ではお客さまと社会に役立つ存在を目指し、経営哲学・理念の共有や、精神性の修養に努めるべく、外部講師をお招きしての社内勉強会を定期的に催しております。
以下では、当社が開催した社内勉強会についてご紹介させて頂きます。
2025年9月19日、第9回のオフサイトセミナーを開催しました。第9回では『故郷を忘れた日本人へ』(2022, 啓文社書房)や『読めない人のための村上春樹入門』(2025, NHK出版)などの著作を持つ仁平千香子先生(文筆家、フリースクール東京y’s Be学園実学講師)にお越しいただき、「文学からお陰様を学ぶ ~なぜ今、文学なのか~」という演題でお話を頂きました。
前半部では、「なぜ今、文学なのか」という切り口を出発点に、今日の情報化社会におけるタイパ・コスパ至上主義や、自由であるからこそ受動的に差し出されるものに従属・依存しやすくなる危うさ、物事の「間(あわい)」やグラデーションを見たり、余白について思考することの重要性をお話いただきました。
後半分にあたる本記事では、主語をあいまいにしたがる日本語の特徴や、共感を重んじる日本的な気質や「私」と他者の「間(あわい)」、文学を読むための実践、「おかげさま」という概念を考えるための作品読解(芥川龍之介「蜜柑」)などを取り上げていきます。
客観的に日本語を考える
現代は「個性を発揮せよ」という要請が強い個人主義的な社会である一方、個性重視、自己主張、「私」の強調などが辛いと感じる人も多くおり、辛さを生じさせる要因のひとつとして仁平先生は日本語を話していること、という点を指摘されます。
日本語は主語を出来る限り避け、主語がなくても会話が成立する言語(英語は主語がないと成立しない)という特徴があります。また、仁平先生が外国人から指摘されて気づいたこととして、「I」や「You」だけでなく、相手の名前も使わずとも会話ができるという日本語の特殊性なども取り上げられました。
よく知られた日本語の特徴としては、自分の呼び方(一人称)が、身分、立場、場所、相手との関係性・距離感によって変わるというものがあります。仁平先生はその可変性について、日本人にはある意味で固定された「私」はなく、静止できない・切り取れない「私」があるほか、「自分」(ややカジュアルな一人称)という言葉は「わたし」を意味する一人称であり、「あなた」を意味する二人称としての「自分」(親しい同等・年下に対しての親密さのある敬意表現)にもなり、外国人にとっては「I」と「You」の境目がないというのが驚きの点になるそうです。
日本語は自動詞を好み「何がどうなる」を言いたがり、英語は他動詞を好み「誰が何をする」という言語という大きな差異があります。西洋圏は自然を支配し、戦争などを通じて「ああすれば、こうなる社会」を構築してきたという歴史・文化的な背景があり、その言語においても行為者(誰が)と行動(何をする)を明確にしたがるという構造がありますが、日本語は「何がどうなった」を表現したがる言語であるため、主語(誰)を曖昧にする傾向がみられます。この点は前半部で触れられたように、 行為者がいないため「何がどうなった」としか表現できない 自然災害に古来から囲まれ続けてきたという日本人の環境が言語的特徴に反映されているとも考えられます。
以下の例文は日本語(何がどうなった)と英語(誰が何をした)、斜体は日本語の文を「何がどうなった」のニュアンスに寄せた英語の比較になります。
▽例文(配布資料より引用)
・病気が治った。 I recovered from the illness. (The illness has healed.)
・子どもが生まれました。I (We) had a baby. (A child has been born.)
・お茶が入りました。I made tea for you. (Tea has entered.)
・結婚することになりました。I’m getting married. / I’ve decided to get married.
(The situation in which we will get married has happened.)
4番目の「ことになりました」は特に日本語的な言葉であり、「ことになりました」を用いる文章では主語が徹底的にぼかされるほか、自然な流れでそうなった(流れに巻き込まれた)というようなニュアンスも含まれています。それに対し英語では、「私」が「するに至った」「決断した」というように、行為者の意志が明示されています。その一方、例文にもあるように「ことになりました」を英語に置きかえた際は、「(私たちが)結婚を決意するような状況が生じた」という、巻き込まれたことを示唆しつつも回りくどいニュアンスになります。
日本語は文法がコンプリケイトで難しい
日本語における「は」はトピック/主題を示し、「が」が主語に相当します。英文法でお馴染みのS(subject /主語) V(verb/動詞) O(object/目的語) C(complement/補語)A(adjective /形容詞)で文例を示すと下記のようになりますが、「は」と「が」のニュアンスの違いや、「い形容詞/ナ形容詞」など、日本語の文法を知ろうとすると、母語として日本語を使っている際にまったく意識していない点が数多くあることを知らされ、その複雑さに驚かされます。
文例1
・I like sweets. : SVO(第三文型)
・[私/S]は[甘いもの/O]が[好き(na-Adj /ナ形容詞)]です(particle/助詞):
・I eat apple (SVO). / 私がリンゴを食べる(SOV)
文例2(配布資料より)
・(私は)甘いものが好きです: 英語では「好き(like)」が動詞ですが、日本語では「好きです」は形容詞に相当するため「好きます」とはならない。無理やり英語的に訳すと「(私について言えば、)甘いものはいいものです」となります。
・(あなたは)あの山が見えますか? →英語でいえば「Can You~」となりますが、日本語ではあなたが省略され「(あなたについて言えば、)あの山は見えるものですか」というニュアンスを持ちます。
れ
日本語は行為者をはっきり明示させることを嫌い、境界線を曖昧にしたがり(「間(あわい)」、「支配する私」よりも「巻き込まれる私」を伝えたがるという特徴があります。例文で登場した「(おかげさまで)〇〇することになりました」は、特に日本語的な表現であり、不可視なものである「陰」に「様」を付ける「お陰(かげ)様で」は、見えないものに感謝するという日本人の特徴が反映された言葉であり、大きな流れの中の陰にある何かが、物事がうまくいくように図らってくれる状態と仁平先生は述べられます。
加えて、「巻き込まれる」「うまくいくよう図らわれる」といった特徴を持ち、「私」の意志ではない結果として生じる「おかげさま」は、九鬼周造のいう「偶然性」(根拠ある必然性の否定で、偶然の積み重ねで「私」が存在するという人間観)に類似したものとも感じます。(私の)行動と結果の帰結として「私」があるという主体観ではなく、「『おかげさまで』/偶然に今の『私』がある」という意識を持つことは、後に道元の思想と絡めて語られるように、今日的な生きづらさを和らげる効果を持つかもしれません。
日本語において、「わかる」「見える」「聞こえる」「思える」「思い出される」といった動詞は可能系(「~れる」「~ます」「~られます」)にすることができず、そういった言葉は自分の意志ではなく自然に生じる感覚が表わされています。「わかりましたか?」という文章は英語で「Do you understand?」となり「私」が「理解する」というニュアンスになりますが、日本語では「私の行為」ではなく腹のあたりから「自然と湧いてくる」もの、というような意味合いが含まれています。
西洋的な確固たる主体・行為者と主体としての「私」をぼかすという点は、ヒンディー語の「与格構文」に近いものがあります。「与格構文」は第6回オフサイトセミナーの講師を担当頂いた中島岳志先生が著書『思いがけず利他』(2021)などで言及されているもので、「私」を行為主体ではなく、行為や感情が留まる器のような客体(巻き込まれるもの)として捉え、己の意思や力が及ばない領域から湧き上がってくる現象について表現する構文です。「私〈は〉~だ」は、「私〈に〉~が留まっている」と表現されます。例としては、「私は嬉しい」は「私に嬉しさが留まっている」という文章になります。
※参考記事: 中島岳志「利他的であること」(第8回 与格-ふいに その1)
与格構文では西洋・能動的な「私」ではなく受動的な「器としての『私』」が想定されており、「私」を曖昧にして大きな流れの中に位置づける日本語と比較的近い性質を持っています。
共感目的の日本語
仁平先生はベルギー人の知人(日本語が堪能で奥様は日本人)は「日本語は『ね』で会話ができる」ということに驚愕したお話をされました。「ね」という言葉は英語できれいに訳せず、なおかつ日本人は日常的かつ無意識に「ね」という言葉を使っているという指摘には非常に驚かされました。
例文としては「今日も暑いですね」などがあり、「ね」は共感を促すための言葉として用いられます。「おはよう(おはやいですね)」という言葉を例にみると、英語では向かい合って挨拶するようなニュアンスの「Good morning (I wish a good morning)」であり、共感志向の日本語は「(お)はやいですね」と一緒に共感を確認すると指摘されます。
お話の中では触れられていませんが、日本語持つ共感的な要素が特に表れた言葉として「かわいい」があります。街中で「あれ、かわいいよ〈ね〉」という言葉に対し「かわいい!」という返事が返されていたのを耳にしたとき、主語を曖昧にして共感を促す極めて日本語的なコミュニケーションであり、そのやりとりに「間(あわい)」が生じているのではないかという実感を抱きました。
そういった日本語(共感)と英語(向き合う)の差異が象徴的に表れたものとして、『東京物語』(1953)と『カサブランカ』(1942)があげられました。日本語は同じ方向を見て関係を感じ合うことで両者は「間(あわい)」の関係となり、西洋では向かい合うことで「私」と「他者」という個別の関係が成立します。
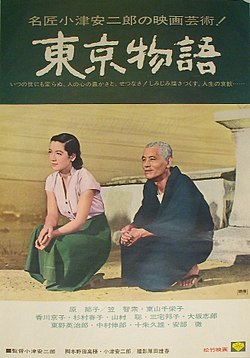

日本語は自己主張に使いにくい「間(あわい)」の言語であるため、日本人(日本語で考え、話す人)にとっては私とあなたの垣根を曖昧にする日本語を使いながら「私」を主張することに辛く感じることも多いと指摘されます。
日本語における「私」とは、大きな流れの中の一部(つながり/おかげさまの一部)であり、西洋的な個人として切り取ることが難しく、「自分らしさ」「個性の発揮」「自分探し」などが重視される現代における「私」であることの要請が生き苦しく感じてしまう(藤村操の「人生不可解」や、埴谷雄高が『死霊』で提示した「自同律の不快」も「私」を切り取ることへの拒絶とも考えられます)ではないかと仁平先生は推察され、「自分」の解放が幸福に繋がるという道元の教えを取り上げられます。
仏道をならふといふは、自己をならふなり。自己をならふといふは、自己をわするるなり。自己をわするるといふは、万法に証せらるるなり。万法に証せらるるといふは、自己の心身および他己の心身をしてっ脱落せしむるなり。
(「現成公案」『正法眼蔵』)
仏道とは「本当の自分」を学ぶことであり、本当の自分を学ぶことは、その「自分」という幻想を手放すこと。自分を手放すと、世界と一体になり、最後には、自己も他者も超えて、心と身体のしがらみを解き放つ「身心脱落」の境地に至る。
道元は仏道とは「本当の自分」を学ぶことであり、本当の自分を学ぶことは「自分」という幻想を捨て、世界や環境(おかげさま)と一体になると考えるほうが生きやすく、自己も他者も心と体の枠組み・しがらみから自由になる「心身脱落」に達することで真の自由に至ると説きます。また、仏教においては、「自分とは何か(小我)」という枠を外すと、「本当に自由な生(真我)」が始まり周囲と響き合い・繋がっているという感覚(=「間(あわい)」)を持つことができるともされています。
仁平先生は繋がっているという感覚を持つことで、他人を非難したり被害者意識を持つような「『ない』もの探し」が減り、与えられるもの/おかげさまに気づきやすくなる「『ある』もの探し」へと意識を向けやすくなるとまとめられ、理想論であるという断りをいれたうえで、日本語は「『ある』もの/おかげさま」に気づきやすく、日本語を話すということは「『自分』への執着を手放す『幸福』の実践」にも繋がっていると指摘されます。
国語力の低下がもたらす影響
国語力/日本語運用能力の低下が精神にもたらす影響は、横文字用語を日本語に置き換えずにそのまま使用したり、コスパ、タイパ、スマホのような略語の氾濫など、日本語を大事にしなくなるという姿勢に表れるほか、教育現場においては日本語をおろそかにした状態でとにかく英語をやるべきという風潮があります。
外国語を学ぶことは日本語を客観的に見るうえで非常に有益ではありますが、外国語の勉強は母国語のレベルに引きずられてしまうため、外国語を学ぶ前提として母語のレベルをしっかりと上げる必要があるほか、英語習得という目的ばかりが先行し、日本語という特色ある言語を深く知ろうとしないのはもったいないと感じる部分もあると、仁平先生は述べられます。
外国語を通じて母語を捉え直すという観点は非常に重要で、第二外国語を学ぶと名詞の性や格変化、「eu(オイ)」「oi(ワ)」といった発音変化や、フランス語の「h(アッシュ)」のような無発音などにハードルの高さを感じる一方、日本語は漢字ひらがなカタカナを並行して用い、人称は社会関係で変化し、主語がなくても成立するという特徴に改めて驚かされます。
さらには、語尾の使い分けでも性格や性別を表現が可能で、「河童(かっぱ)」のように漢字の組み合わせによって特殊な読み方を生じさせ、「ね」で会話ができ、文意によって無意識に「4(シ/よん)」や「7(シチ/なな)」のほか、「D51(デゴイチ)」、「エリア51(ごじゅういち)」「6D(ろくディー)」といったように数字の発音を変化させるなど、ハードルの高さを感じていた諸外国語にも引けをとらない複雑怪奇な言語であることを思い知らされ、第二・第三言語として日本語を学ぶ難しさの片鱗を感じたことがあります。
前半の記事で触れた「文学が教えてくれること、助けてくれること」での「国語力、語彙力、比喩を通した表現の深さ」は、自身を振り返ってみると文学に触れることで広げられてきたという印象が強くあります。また、作品分析のメインとして選ばれた芥川龍之介の「蜜柑」(初出: 1919/大正8年,『新潮』5月号 )は、非常に短い短編ながらも多くのことを学ぶことができるという点で、長らく文学や小説を読んでいないという方でも抵抗なく読める作品だと思われます。
芥川龍之介「蜜柑」を読む
仁平先生は読書会などで芥川龍之介をよく取り上げられ、その理由として芥川は近代化の当然となった大正時代(好景気で物がたくさんある時代)、作家であり、現代の価値観と大正時代の価値観にあまり相違がないことからも、芥川を重要視されるそうです。
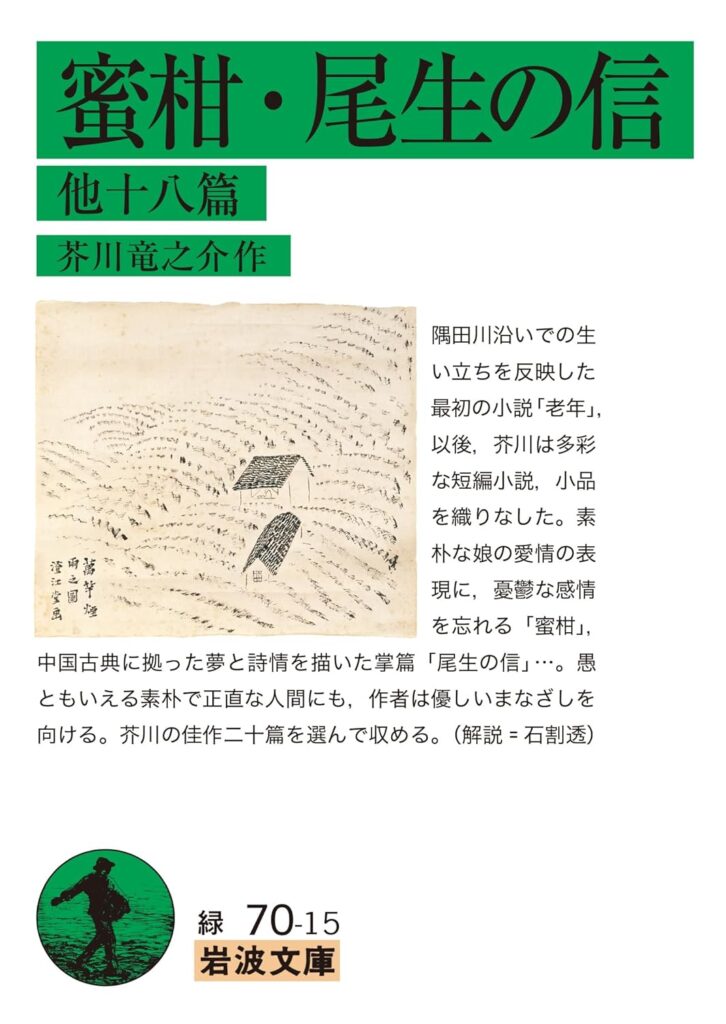
芥川龍之介の「蜜柑」は、疲労と倦怠を感じる「私」が、横須賀発の汽車(二等車両)で乗り合わせた田舎者の娘のみすぼらしい風体や、三等切符を手に持ちながら二等車両に乗りこむだけでなく「私」の眼前の席に座るふてぶてしさに苛立っていると、娘が窓を開け、故郷から奉公に出る娘を見送りにきていた弟たちに蜜柑を放り投げる様(「与える」という利他的な行為)を見たことで、男は「云ひようのない疲労と倦怠」、「不可解な、下等な、退屈な人生」を「僅かに忘れる事が出来た」と結ばれる短編です。
それは油気のない髪をひつつめの銀杏返しに結つて、横なでの痕のある皸ひびだらけの両頬を気持の悪い程赤く火照ほてらせた、如何にも田舎者らしい娘だつた。しかも垢じみた萌黄色の毛糸の襟巻がだらりと垂れ下つた膝の上には、大きな風呂敷包みがあつた。その又包みを抱いた霜焼けの手の中には、三等の赤切符が大事さうにしつかり握られてゐた。私はこの小娘の下品な顔だちを好まなかつた。それから彼女の服装が不潔なのもやはり不快だつた。最後にその二等と三等との区別さへも弁へない愚鈍な心が腹立たしかつた。
芥川龍之介「蜜柑」(青空文庫より引用)
少女の容貌に関する描写について、仁平先生は文学を読む際に、田舎の娘が二等車両内にいるという客観的事実よりも、男が見ているのはどんな世界かを注視することが重要な点となると指摘されます。引用の場面であれば「娘が田舎臭い」と思っている男がおり、その男の視点によって田舎者の娘が「表れる」という重層性(「誰がなにをどう語っているのか」)に意識を向けることが文学作品を読むうえで重要になると指摘されます。
配布資料に記載の設問では「娘の何が男を苛立たせるのか?」というものがあり、男が娘の外見や立ち振る舞いに苛立つ理由を考察することで、男の性格や価値観や心理などが鏡写しに表れてくるともいえます。
窓から半身を乗り出してゐた例の娘が、あの霜焼けの手をつとのばして、勢よく左右に振つたと思ふと、忽ち心を躍らすばかり暖な日の色に染まつてゐる蜜柑が凡そ五つ六つ、汽車を見送つた子供たちの上へばらばらと空から降つて来た。私は思はず息を呑んだ。さうして刹那に一切を了解した。小娘は、恐らくはこれから奉公先へ赴かうとしてゐる小娘は、その懐に蔵してゐた幾顆(いくくわ)の蜜柑を窓から投げて、わざわざ踏切りまで見送りに来た弟たちの労に報いたのである。(中略) 私は昂然と頭を挙げて、まるで別人を見るやうにあの小娘を注視した。小娘は何時かもう私の前の席に返つて、不相変(あひかはらず)皸だらけの頬を萌黄色の毛糸の襟巻に埋めながら、大きな風呂敷包みを抱へた手に、しつかりと三等切符を握つてゐる。…………
私はこの時始めて、云ひやうのない疲労と倦怠とを、さうして又不可解な、下等な、退屈な人生を僅に忘れる事が出来たのである。
芥川龍之介「蜜柑」(青空文庫より引用)
男は、娘が弟たちに蜜柑を与える姿を見て癒されるのですが、男と娘のコントラストが主題のひとつとなります。仁平先生は、男が娘の貧乏臭いところを執拗に気にすることも着目し、男はかつて貧乏であったと考えられ、自身のコンプレックスを思い出させる娘の貧乏臭さを感じさせる要素をあげつらうと述べられます。
娘が「持っていない」という部分にこだわることで、男は「持っている」ことに優越や安心を覚える(「所有したがる男」)のですが、娘は「持っていない」と思われていたが、持っていた蜜柑を与える(「与えたがる女」)という対比関係が重要となります。
読解のためのポイントとして「所有したがる男(切り離す)と、与えたがる娘(つながる)、どちらが孤独・不安か?」「なぜ蜜柑なのか」「なぜ娘の与える姿を見て癒されてしまうのか?」といった論点も、配布資料に記載されていました。
「蜜柑」のまとめ
娘がどう見えるか(見る「私」のありかた)という点には、「私」の心理が反映されており、男を苛立たせるものを子細に分析していくことで、男の内側にある何かが浮き彫りにされていきます。
「見る『私』」という「偏った存在」が作品内で「見える世界」を形成しているので、「私」を通じて語られる世界は客観的なものではなく、現実の「私」と娘(他者)の間にある「間(あわい)」によって世界が浮かび上がってくるとされます。
「男にとって不快なのは娘ではなく、娘に寄り添えない『私』、与えられない『私』」であり、最後の場面で娘が「与える」姿を見ることによって「私」は癒しを感じることができます。
与えることができないのは、持っていないからではなく、失うことが不幸になるという思い込み(資本主義マインド)であり、「私の幸せ」を実現しようとすると、失う(=与える)ことを恐れる人間となりやすく、そういったマインドの人にとっての「他者」は奪う存在と感じるようになります。
与える人(娘)にとっての「他者」は受け取ってくれる人/喜びを与えてくれる存在(おかげさま)であり、「私」は蜜柑をあげたという事実以上に、「与えたがる」娘の在り方に癒されたと仁平先生はまとめられます。
与える―受け取るという関係は「利他」的な行為であり、中島先生は「利他」は受け取り手によって起動すると指摘されています。「蜜柑」の例でみたように「おかげさま」を見出すうえでは受け取ってくれる人の存在も重要になります(中島先生が指摘されるように、利他的な「与える」という行為は、受け取る側が難色を示すと「ありがた迷惑」に反転してしまいます)。
中島先生にお越しいただいた第6回オフサイトセミナー「利他の構造」で取り上げられた作品に志賀直哉の「小僧の神様」(初出: 1920/大正9年, 『白樺』1月号)があります。こちらも与える―受け取るという関係が描かれています。同作は、貴族院議員のAが所持金が足りずに寿司屋台から出てきた丁稚の小僧さんに同情し、今度会った時に寿司を奢ると決め、後日にそれを実行できるのですが、奇妙なわだかまりを感じてしまうというものです。
Aは変に淋しい気がした。自分は先の日小僧の気の毒な様子を見て、心から同情した。そして、出来る事なら、こうもしてやりたいと考えていた事を今日は偶然の機会から遂行出来たのである。小僧も満足し、自分も満足していい筈だ。人を喜ばす事は悪い事ではない。自分は当然、或喜びを感じていいわけだ。ところが、どうだろう。この変に淋しい、いやな気持は。なぜだろう。何から来るのだろう。ちょうど人知れず悪い事をした後の気持に似通っている。
志賀直哉「小僧の神様」(『和解・小僧の神様 ほか十三編』、講談社)
Aの場合は娘のように「与えたいから与える」のではなく、小僧に同情し、出会った瞬間に与えるのではなく、次に会った時に(私は)与えたいという目論見を持った行為であるという差異があります。もし、最初に小僧に会った時Aが「与える」ことをふいに行えれば、「変に淋しい、いやな気持ち」を抱くことなく、小僧に喜びを与えてもらう「おかげさま」の関係が構築されたとも考えられます。
「蜜柑」はごく僅かな時間で読める短編ですが、「与えること」(贈与、利他、フロムのいう「『愛する』こと」)や、主観を通じた他者との関係性として現前する「間(あわい)」の世界、外見描写による対比関係や、舞台設定(横須賀から汽車に乗ることで海軍関係者であることが示唆)、「檻に入れられた小犬」「暖な日の色に染まつてゐる蜜柑」などの比喩表現など、文學の核のようなものが凝縮されている作品であるので、読解を学ぶためのテキストとしても大いに活用できると思います。
文学を通じた語り
文学の持つ力に関連して最後に取り上げられるのは、ティム・オブライエンの「レイニー河で」(村上春樹 訳, 『本当の戦争の話をしよう』, 1998, 文藝春秋 所収)です。前半部分は、1968年に食肉加工場で豚を解体する主人公が黙々と作業工程について語られ、最後には戦争への召集令状が届いていることが示され、作業工程がヴェトナム戦争のメタファーであることが露わにされます。
文学は戦場の光景を描写することもできますが、オブライエンはあえて戦場の兵士たちを工場で加工される豚になぞらえて描写されています。インタビューにおいてオブライエンは「戦場での体験を事実的に書いたとしても、体験したことは伝わらない」と答えており、本当にあったことをフィクショナルな要素や比喩を使って表現できるのが文学の力であると、仁平先生は述べられます。
戦争に関する新聞報道などは、事実的な要素(戦局・政局、使われた兵器、被害状況など)データが中心になってしまい、兵士一人一人が何を感じてきたかといいた部分はデータからは読み取ることができないため、戦争の残酷さを伝えるには比喩や物語が必要とされ、それを担うのが小説の役割と仁平先生は指摘されます。
日本の例では大岡正平らを筆頭とした戦後文学がそういった役割を担ってきたとも考えらるほか、「レイニー河で」はヴェトナム戦争の話ですが、仁平先生は大学時代に同作を読んで、日本における戦争の語りについても、考えを深めるようになったそうです。
戦場を経験してきた当事者たちが時局・政局的な理由などで戦争について語れないという状況においては、文学を通じて創造された作品を読むことで個々人が何を感じてきたということや、先祖が戦中を生き延びてくれたことで現在の自分が存在しているという点に、仁平先生は「おかげさま」を感じることができると述べられます。加えて、作品を通じて物事を考えたり想像力を働かせられるのは文学の力であり、は寄り添いや共感、日本語の世界でもある「おかげさま」や感謝は、想像力を使わなければ出てこない、とも指摘されます。
日本人は、共感しようという気持ちが強く、共感力を保持するためには文学を読み続けることが重要になります。「ああすれば、こうなる」という今日の脳化社会の中では日本語的思考から離れてしまっており、文学に触れながら日本語で話す「日本人」というものを思い出してみると良い、という提案で仁平先生のお話を締めていただきました。
▽関連記事
人気記事
まだデータがありません。