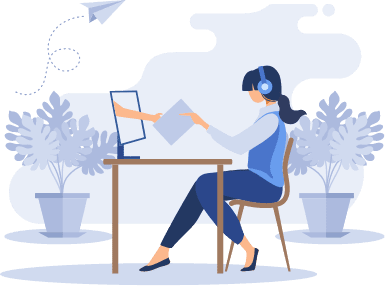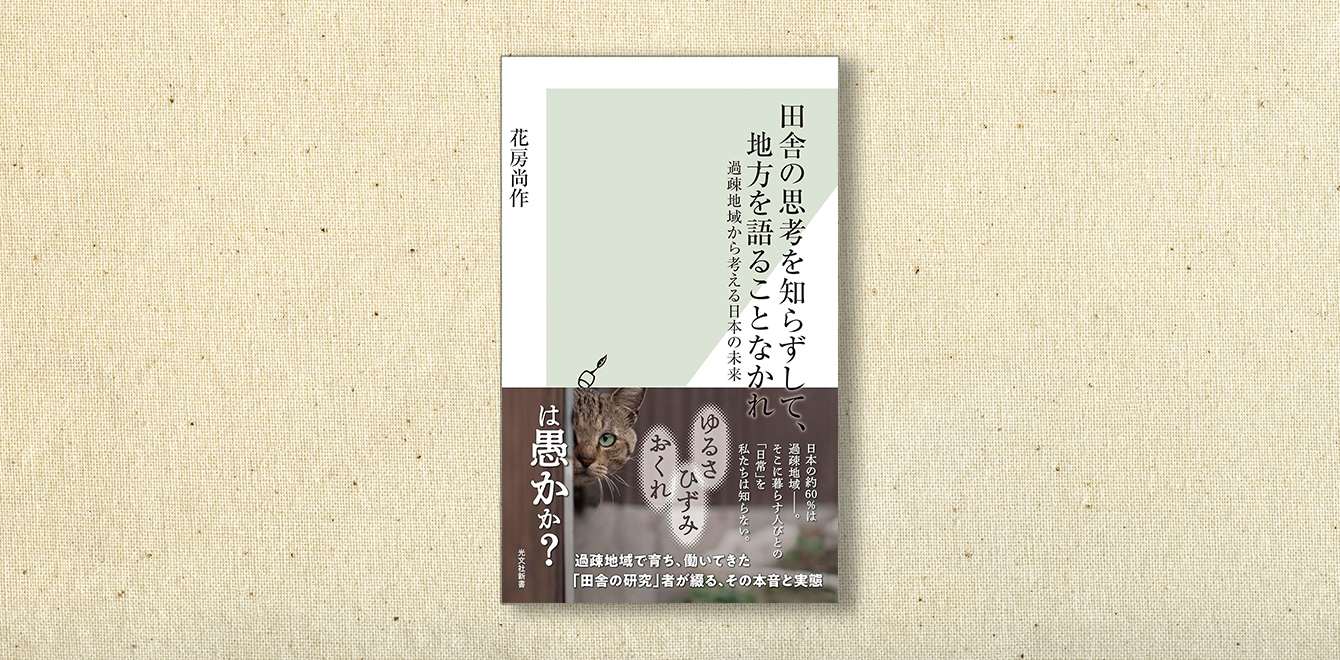
2024年の石破内閣の成立によって、2014年から始まった地方創生への注目が再び高まりを見せ、「地方創生2.0の推進」などの政策も発表され、そのベースには東京一極集中の解消、新しい地方経済の創出、DX・GXなどのデジタル技術の活用、「関係人口」の創出・拡大などの目標が掲げられています。
政府が標榜する「地方」という言葉の中に、どの程度までの地域が想定されているかについては不明確な印象がありますが、おおむね交通の利便性が高く、都心からも往来しやすく比較的発展した、『田舎の思考を知らずして、地方を語ることなかれ 過疎地域から考える日本の未来』(2025, 光文社)の著者である花房尚作さんの言葉を借りれば「最寄り駅がある」ような「地方」が想定されているように思えます。
花房さんはアメリカの都市論で広く参照される「都市=村落二分法(rural-urban dichotomy)」や、都市-市-町-村-村落という段階的な区分で地域を捉える「都市=村連続法(rural-urban continuum)」ではなく、都心-発展地域-停滞地域-衰退地域-田舎という、都市と田舎という2つの極点からの距離によって地域区分を定義する「都心=田舎区分法(Regional division of Japan)」という花房さん独自の概念を用いて、都市と地方を段階的に定義されます。
地域の区分は、発展地域・停滞地域・衰退地域の3つ。まず、発展地域は高次都市機能が立地し、都心へのアクセスが可能な地域だ。大学入学や就職等で周辺地域から若年層の転入が見込める。次に、停滞地域は基礎的な都市機能を有し、人口減少の速度がゆるやかな地域だ。成長志向と発展思考を持つ若者が地域を去る一方で、周辺地域から利便性を求めて若者の流入がある。最後に、衰退地域は基礎的な都市機能を持たない地域だ。若者の流出で高齢化が著しく、地域経済の衰退が続いている。
(107頁)
本書で主に扱われるのは衰退地域、田舎のいわゆる過疎地域(過疎地域対策法で規定された人口減少率・高齢者比率・若年者比率・財政力指数を満たす地域)です。ご自身も鹿児島の過疎地域に定住する著者の花房さんは、祖母の出身地である鹿児島県の大隈半島をフィールドにした調査研究を行っており、その内容は本書の後半部分で「特定の地域の事例ではなく、過疎地域のよくある事例」(166頁)として紹介されます。
研究テーマとして田舎や多様性を取り上げ、表現活動や劇団主宰、演出家、ナレーターなど多彩な分野を横断する花房さんの著作には『価値観の多様性はなぜ認められないのか』(2019, 日本橋出版 / 電書版,2019, ディスカヴァー・トウェンティワン )や、本書の前作にあたる『田舎はいやらしい~地域活性化は本当に必要か?~』(2022, 光文社)などがあります。
本書の冒頭では、「田舎」「文化人」「都心」という、3種の「いやらしさ」が登場します(2-3頁)。「田舎のいやらしさ」は絶対的な自身を持った価値基準の押しつけや、価値基準に従わない者に対する敵対視、「文化人のいやらしさ」は自身の知識や経験を高く評価し、他者のそれを低く評価する姿勢や態度、「都心のいやらしさ」は都市を「進んだ・優れた地域」と捉え、田舎を「遅れている・劣っている地域」と捉える姿勢や態度や、「都会風を吹かせる」ような行為や発言を指します。
田舎と都心の「いやらしさ」の背景が極端に違う理由として、花房さんは「思考様式の違い」をあげ、「首都圏の住民は『首都圏の思考様式』を『日本の思考様式』として捉えがちだ。過疎地域も首都圏と同じように発展したほうがよいと考えている」(3頁)と指摘されます。執筆者は地方創生関連の政策にはおおむね賛同しつつも、少し違和感を抱くことがあり、その違和感の原因は「首都圏の思考様式」が露骨に見えてしまうためかもしれません。
思考様式から考える、都心と田舎
本書の前半部は、過疎地域に対する「悲惨」というような紋切り型のイメージがあることや、都心と過疎地域にある認識のズレなどの問題提起や、「都会」「地域」「過疎」といった用語についての詳細な確認や定義が行われます。
認識のズレが生じる原因として、花房さんは「視座」(どの立ち位置から見るか)、「視点」(どの対象を見るか)、「視野」(表・中・深層どの程度まで見るか)、「視線」(批判・共感的な観点、現在・過去・未来を見るなど)のズレを指摘されます。
まずモデルとして提示されるのは視座と視点の組み合わせ(下記引用)で、①と④では視座/立ち位置と対象への視点が同一なので、日常の中で対象を把握できる(一例として、東京の繁華街についての調査研究は都市部に視座を置く政府や大学機関の得意とする領域となる)一方、視座と視点がズレる②と③では対象把握が難しくなります。
- 視座を「都市部」において、視点を「都市部」に向ける。
- 視座を「都市部」において、視点を「田舎」に向ける。
- 視座を「田舎」において、視点を「都市部」に向ける。
- 視座を「田舎」において、視点を「田舎」に向ける。 (35頁)
視野のズレは、広い・狭い、浅い・深いといった差異があり、花房さんは、視野を広くする「学習経験(表層的)」、視野を深くする「居住経験(中層的)」、視野をより深く・広くする「就労経験(深層的)」に分類されます(37頁)。
視線のズレは、批判や思いやりなどの感情的な視線、若者は目標や将来を見るのに対し高齢者は過去の経験から現在を見るといった年齢による視線の方向性に関する差異、調査研究を行う大学機関と政府機関の官僚のように所属組織によって過疎地という共通テーマを扱いながらも視線の方向性が異なる(38頁)といった例があげられます。
過疎地域で暮らしている当事者から見て、都市部の過疎地域研究はズレがあった。それは日本を扱う海外の映像作品見たときのズレとよく似ていた。そこにはいかにも日本人らしくて、日本人らしくない日本人が登場し、日本の街のようで日本の街でない街並みが映し出されている。そのようなステレオタイプのイメージに、ズレを感じた経験はないだろうか。
過疎地域を扱う首都圏の映像作品も同じだ。そこにはいかにも田舎者らしくて、田舎者らしくない田舎者が登場する。その田舎者たちは、首都圏の住民と同じような考え方を持ち、首都圏の住民と同じような行動をしている。演出・シナリオ・出演者等の制作側に、過疎地域についての視野が備わってないことで起こるズレだ。その作品を視聴したものは「過疎地域も首都圏と同じ思考様式を持っている」と勘違いする。過疎地域にまつわるズレの正体とは、そのような行為の積み重ねではないか。
(40-41頁)
本書における重要なキーワードは「差異」や「多様性」であり、特に「視座を『都市部』において、視点を『田舎』に向ける」際のズレから発生する田舎や過疎地域に対する「悲惨」「遅れている」という、一枚岩的なステレオタイプ=中央集権的な日本は中央の思考に準じた均質的な思考が望ましいので「都心の思考」が標準とされてしまう錯覚などを解消することが、目的のひとつとされています。
過疎地域については、過疎地域対策法で規定された人口減少率・高齢者比率・若年者比率・財政力指数を満たす地域という明確な定義があり、それを満たす地域の代表例として取り上げられるのは夕張市です(64-66頁)。
主産業だった炭鉱の閉山による人口と税収入の減少、主産業の切り替えを目指した観光施設の整備や新興への過剰な投資、不適切な財務処理など、複合的な要因が重なって2007年に財政破綻した夕張市は、2015年のデータでは47%を高齢者が占める日本一の高齢化地域となっていました。
財政破綻に至る要因は多々ありますが、花房さんは、役場主導の事業計画は地元名士や市町村議員の利益に与する(不利益な場合反対運動に繋がる)形で進められることが多いという利益誘導や地域のしがらみが財政破綻に繋がった(65頁)ことを指摘され、財政破綻は灰汁が出されたと肯定的に捉え次のように述べられます。
財政破綻の影響で市民税・水道料金・下水使用料・軽自動車税等が値上げした。役場職員の人員と給料も削減された。人口減少に伴って小中学校も統廃合になった。財政破綻で生活が厳しくなったように感じるが、そのぶん行政負担も減っている。日本の市町村である限り、政府が見捨てるようなことは決してない。
炭鉱町として栄えた多くの地域が衰退している中で夕張市が果敢に挑戦した経験は今後の糧になる。むしろ、儲けまくった既得権益者があらかた転出したことで地域の風通しがよくなる。いずれ田舎の未来を担う地域となると期待している。
(65頁)
本書の前半では都心と過疎地域の構造やその思考など、大枠となる部分を俯瞰的に分析されており、各地域の細かな事例分析などは、後半部において花房さんの調査地域である鹿児島県大隈半島を例に詳述されます。
夕張市については、財政破綻に伴う医療崩壊も当時問題視されており、北海道の僻地である瀬棚町の医療を立て直した実績を持つ村上智彦さんが夕張市からの要請で夕張医療の立て直しを指揮し、「在宅医療」「在宅介護・看護」を導入し、「急性医療」から「高齢者の生活に寄り添う在宅医療」への転換)を目指す医療改革を先導されました。
村上さんの活動は『村上スキーム―地域医療再生の方程式 夕張/医療/教育―』(2010, エイチエス) にまとめられているほか、村上医師の後継として夕張市立診療所の院長を勤められ、現在は鹿児島県南九州市の川辺町(鹿児島湾を挟んだ大隈半島の対岸薩摩半島に位置)でクリニックを営む森田洋之さん(南日本ヘルスリサーチラボ代表、ひらやまのクリニック院長)が『うらやましい孤独死――自分はどう死ぬ? 家族をどう看取る?』(2021, フォレスト出版 )などにまとめられているので、夕張市の状況に関心のある方はそちらもご参照ください。
首都圏と地方圏の比較分析で興味深いのは資本集積の違いで、花房さんは分析にあたり「経済資本」(預貯金、不動産等の金融資産)、「文化資本」(スキル、センス等の美意識)、「社会資本」(信頼、人脈などの人間関係)、「象徴資本」(注目・人気等の知名度関連)という4つの資本を設定されます。
統計資料(企業と大学の割合や、1人あたりの預貯金残高)を見ると、「経済資本」「文化資本」はいずれも首都圏と地方では大きな格差があり、「首都圏では各分野で資本の独占と集中が進んでいる」(93頁)状態にあります。格差は是正されるべきというのが一般論ですが、その格差は競争の結果生じた「資本集積の自然化」として受け入れられています。
本書の中では過疎地域によくあるエピソードのひとつとして軽く触れられていますが、少人数のコミュニティからなる過疎地域では、都心よりも紐帯の強い社会資本(社会関係資本、あるいはソーシャル・キャピタル)が形成されやすい傾向があり、一例として、次のような記述があります。
過疎地域では、役場の保険課に地域包括支援センターがある。直轄運営のため、都市部のような競争意識はない。予算や人員が乏しく、職員自ら地域の課題を見つけて対処する余裕もない。だからといって、高齢者が蔑ろにされている訳ではない。過疎地域の高齢者は朝早く起きて、あたりをウロウロして、よく喋る。暇さえあれば集まってワイワイガヤガヤしている。ハーモニカの演奏を突然始める高齢者もいる。その演奏は譜面がなく独特の音が鳴る。職員はそのような演奏に長々と付き合わされる。日本は都市部であれ、過疎地域であれ、元気な高齢者が多い。
(188頁)
このほかにも介護老人保護施設での生活よりも、自宅で一人暮らしをしていたほうが健康や生活能力の向上・快復が見られた例が紹介されます。花房さんの記述では触れられていませんが、過疎地域における地域コミュニティやご近所付き合いが心身にポジティブな影響を与えるケースが確認されており、森田さんは夕張に居住しての活動経験を基に「きずな貯金」(「ソーシャル・キャピタル」を森田さんが訳した造語)という用語を地域コミュニティや介護ケアなどの文脈に援用されます。
「きずな貯金」とは、いわゆる地域社会の繋がりの強さ(医療用語ではSocial Capitalと言う)のこと。つまり、地域社会の中で人々が互いに信頼しあい、繋がりを強め、良好な関係を基にしたコミュニティーを形成する、それこそが人々の心身の健康上の土台になる、という概念である。/この概念はアドラー心理学の中心的な概念と言われる」「共同体感覚」に近いだろう。アドラーは「家庭や地域などの共同体の中で人と繋がっているんだ、という感覚。人間はこの共同体感覚を感じられるときに幸福を感じるという。」 (「きずな貯金とSocial Capital」『表現者クライテリオン』, 2024年11月号, 128頁, 恵文社 )
花房さんの議論は俯瞰かつ構造的に展開されるため、森田さんのように近所付き合いや地域コミュニティの例を綿密に記述される箇所は僅かに留まりますが、「どこの地域にも高齢者を中心とした集まりがある。住民から『高齢者はいつも集まって話をしている』『高齢者の輪ができていて入り難い』といった話をよく聞く。そこにはよい意味でも悪い意味でもお節介な住人がいて、あちこち遠慮なしに割り込んで世話を焼いている。地域包括支援センターや社会福祉協議会の職員も高齢者の自宅を訪れる」(26頁)という記述もあり、濃密なコミュニティの形成や社会資本の存在を確認できます。
田舎に対する都会の視線と関係人口
注目したいのは、移住定住促進事業を取り上げる第7章「田舎の視線」で、地方創生における地方移住の話題にも触れられますが、ポジティブな話題として取り上げられる地方移住が指す「地方」の多くは「交通の便が整った地方の都市部」(226頁)であり「利便性が低く、昔ながらの因習が残る過疎地域」(同前)ではありません。
しばしば地方創生の文脈で登場し、近年は関連書籍も多く発行されている「関係人口」という用語があります(2025年8月に刊行された田中輝美さんの『関係人口の時代-「観光以上、定住未満」で地域と繋がる-』なども今後取り上げる予定です)。関係人口は「居住による定住人口や、観光による交流人口の枠組みを超えて、より幅広い形で地域と関わる者」(230頁)を指します。
総務省が「関係人口創生事業」を創設し、大旗を振っての舵取りをするのは「視座を『都市部』において、視点を『田舎』に向ける」典型例であるようにも思え、少々野暮ったさを感じますが、地方活性化の一形態としては興味深い取り組みでもありますが、過疎地域からの反応は歓迎的ではなく、花房さんも次のように批判されます。
関係人口という言葉は移住を決断できない都市部の住民にとって都合がよい。その裏には田舎のことを考えているという、免罪符としての役割が透けて見える。その根底に都心のいやらしさや、文化人のいやらしさを感じる。過疎地域で関係人口と言う言葉を使うのは、観光促進事業やふるさと納税の利害関係者くらいだ。
(230頁)
関係人口や地方創生については都会の思考様式によって駆動している部分や、「地方」を一枚岩のものとして捉えてしまい、衰退地域・過疎地域の特性や田舎の思考様式に目配せできていないという印象も少なくありませんが、関係人口に関する議論などはまた別の記事で扱う予定です。
田舎の思考と都市の思考
序章から第4章までは、問題提起、用語の定義、都市と田舎の比較、田舎が形成される歴史的過程、第5章から第8章までが花房さん自身の過疎地定住経験に基づく調査、いわば田舎から見た田舎に関する分析が中心になります。後半の中でも、デジタル化の進まない役場業務や、補助金事業、市町村議会や選挙戦など、「田舎のいやらしさ」が凝縮されたトピックについて論じられた部分ともいえる第6章「田舎の視野」は、参与観察者(参与観察者)ではなく内部に定住することで見える部分でもあり、興味関心を強く惹かれました。
結論部「田舎の思考」では、それまでの議論を踏まえたうえで概念化された「田舎の思考」(過疎地域の思考様式)と「都心の思考」(首都圏の思考様式)について論じられます。
少人数や同質性を基盤とする田舎の思考は、日常的な気楽さ・安らぎを重視する村社会的な性質を持つ「ディフェンシブ」な思考で、「現状維持を前提とし、昔ながらの伝統や慣習を守り続ける態度や一定の枠内に籠って変化を受け入れない姿勢を重視」(278頁)します。対する「都心の思考」は都市社会的な広いつながりを重視し、「現状打破を前提とし、コストに対する成果量の比率や少ない投資でいかに大きな効果を得るか」(同前)が重視されます。
「都心の思考」資本主義や立身出世や富の獲得に関連した修養と非常に相性がよい一方で過酷な競争や自発的な選択に囲まれ続けるに対し、変化を拒む田舎は保守性的(伝統や歴史を重んじる一方、自身の正当性に固執しリベラルな対話姿勢を欠きがち)な思考を基盤とします。
いずれも優劣や強さの順列を付けられるものではなく、花房さんは2つの思考のあり方を差異や多様性、それぞれの状況に対して合理化された思考を尊重することが重要と指摘されます。
そこにあるのは優劣では決してない。差異や多様性という面白味である。思考の方向性が違うだけで、どちらも合理的な知性が備わっている。田舎の思考と都心の思考では知性を行使する対象が違う。なぜなら、地域によって置かれている状況が違うからだ。最寄り駅がない地域と、電車できがるに移動できる地域では利便性が違う。(……)思考様式の違いはそれぞれの地域で暮らしていくための構造的な知恵である。その違いを認めて尊重するだけで、地域でのコミュニケーションがずいぶん変わる。
(280頁)
そしてもう一点興味深い箇所「田舎の思考の割合」(282頁)で、これは「都心=田舎区分法」的に思考の割合を考えるようなもので、統計的なエビデンスではなく、花房さんが「過疎地域で暮らし、首都圏で暮らし、地方の都市部で暮らし、海外で暮らし、田舎の研究を進める過程で、日本各地を巡って得た経験則」(282頁)に基づいた分析になります。
花房さんは、調査地域(鹿児島県の大隈半島)における実感としては9割ほどが田舎の思考で、首都圏では2-3割ほど(周囲に感化され思考転換する場合もある)、地方の大都市で4割ほど、都心の思考と田舎の思考が拮抗するのが停滞地域(282頁)と述べられます。
田舎の思考に基づいた生活や文化・慣習などは、都会の思考から見ると非合理的なものに見えることも少なくないと思いますが、中央集権的な均質性に基づいて田舎も都会の思考を受け入れることで合理化・進歩的になるという考え方を田舎や過疎地域にも啓蒙しなければならないという意識を持ってしまうことに気づくことも、本書の重要な論点になります。
田舎のイメージを捉え直す
本書は非常にロジカルな展開で、都心に視座を置いた際に抱きがちな田舎や過疎地域に対するステレオタイプを崩してくれるほか、後半部で展開される居住経験に基づいて論じられる田舎の思考や、過疎地域における共通であろうトピックが手短に紹介されます。
例としては小学校の統廃合(機能性よりも住民の思い入れで統廃合への反対が起きる)、役場のデジタル化(デジタルディバイドや変化の拒否、昔ながらの無難なスタイルへの信奉)、選挙戦(候補者は高齢者男性で占められ、賛成派と反対派が妨害活動を伴い敵対する)など、田舎の思考に基づいた合理的なものから、田舎の「いやらしさ」が凝縮された因習的なものまで幅広く紹介されており、田舎や過疎地域に対する一枚岩的なイメージを払拭してくれます。
問題提起にあたる前半で概念や用語の定義を綿密に行い、中盤では過疎地が形成される歴史的な過程、後半では居住生活に基づく内的な視点を通じた過疎地の調査研究と、非常にリニアかつロジカルな構成や展開で、後半の各トピックも短く読みやすい内容となっています。
前半部分は社会学や文化人類的なアプローチが強いですが、難解な専門用語や分野特有の概念などが登場することは、「資本」に関する部分以外は稀であると思うので、多くの方がスムーズに読み進められると思われます。加えて、執筆者のように生まれも育ちも都市部であり「視座を『都市部』において、視点を『都市部』に向け」ながら日々を過ごしている人にも強く訴求する内容であると感じました。
関連記事
人気記事
まだデータがありません。