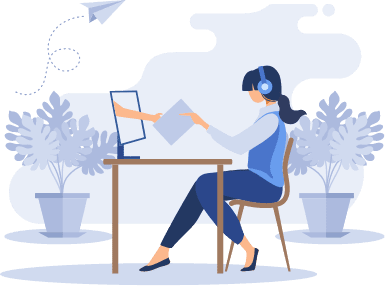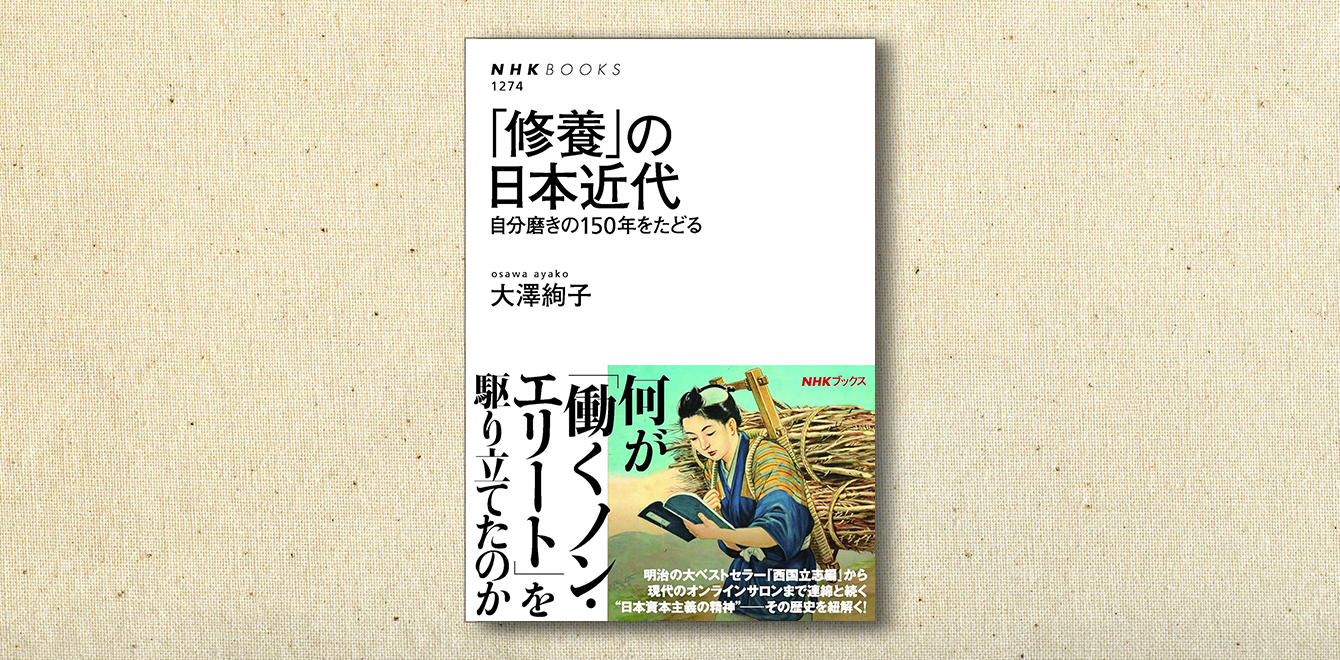
『「修養」の日本近代 自分磨きの150年をたどる』(2022, NHK出版)は、明治から現代に至る「修養」の変遷を論じた本です。「会社での働き方や経営理念、人材育成や社員研修など、より近代日本社会に即した形で、資本主義で働く人々の持つべき精神性」(253頁)であり、「自分の現状に満足せず、さらなる高みを求めようとする人間の欲望と願いの現れ」(同前)とまとめられるように、修養は近代日本で広まりを見せた時から階級・地位・経済的状況の上昇志向を伴うもの、いわば立身出世や自己実現に対する欲望という側面を含んでいます。
本書は明治時代から現在に至る修養の変遷を分析し、時代の変革期における修養への関心や、エリートに属する「教養」と大衆に属する「修養」の差異、松下幸之助率いる松下電器に代表される日本型の会社経営(個よりも集団を重視し、愛社・忠社精神を育む)における修養や、修養と不可分な関係にある宗教的要素などが論じられます。
内容は社会史・文化史的なものですが、松下幸之助や鈴木清一(不二家と並び、日本に初めてフランチャイズシステムを導入したダスキンの創業者)を取り上げた章では、修養を軸に構築された企業文化や研修実践、経営哲学などが子細に分析されており、かつての日本的企業文化が構築されてきた背景や、その特徴がまとめられています。とはいえ、その企業文化や経営哲学はエズラ・ヴォーゲルが『ジャパン・アズ・ナンバーワン』(1979)を記した時代に則する形で際立った成功を収めたため、価値観や雇用形態が多様化した現在にそのまま適応できるとはいえません。
そういう点では、本書は企業研究の内容を含みながらも、ハウツー的なビジネス書として直接的に修養に繋がりにくく、コストパフォーマンスやタイムパフォーマンスに優れた「ファスト教養」(レジー,『ファスト教養 10分で答えが欲しい人たち』, 2022, 集英社 参照)に適したものではない、というよりも修養に紐づけられたそういった書籍がなぜ今もなお人気を博しているのかを体系的に考えるための本となっています。
本書は大きく分けて社会・文化史的な部分パート(第1章、第2章)と、雑誌『実業の日本』のブームと新渡戸稲造の教育論(第3章)、松下幸之助とダスキンの創業者鈴木清一を例に会社文化における「修養」や、実践や思想にみられる宗教的要素(明治時代から修養と宗教、とりわけキリスト教は密接な関係にある)を分析するビジネス論的なパート(第4章、第5章)、1970年代の自己啓発ブームから近年のオンラインサロンを論じたパート(終章)で構成されています。
第1章「語られた修養――伝統宗教と〈宗教っぽい〉もの」、第2章「Self-Helpの波紋――立身出世と成功の夢」で取り上げられる時代は、三宅夏帆さんの『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』(2024)の前半部でも論じられており、同書を既読の方は「修養」と「教養」の違いや、自助努力によるサクセス・ストリーを集めた明治から大正にかけてのベストセラーであり、大澤さんが「近代日本初の自己啓発書と考えている」(12頁)と述べるサミュエル・スマイルズ『西国立志編』(中村正直 訳, 1871、原題は『自助論』Self-Help, 1859)についてや、『実業之日本』(1897創刊)や『成功』(1902創刊)など、「修養」に関連した大衆向け雑誌についての議論もスムーズに読み進められると思います。
三宅さんは読者の受容・関心や、本を読む目的などに着目して明治大正期の状況を論じられる一方、『「修養」の日本近代』で興味深いのは、『実業之日本』の編集にも深く関わっていた新渡戸稲造にフォーカスする論点で、その思想や教育者としての実践にキリスト教(クエーカー)と東洋思想のハイブリッドともいうべき独自性の高い考えが根差しています。また、序章「『自分磨き』の志向」の冒頭では、近代的な修養と、宗教との結びつきが強かった前近代的な修養の双方を包括しながら、企業精神やビジネスに複合的な修養を結び付けた松下幸之助への言及から始まります。
戦後の日本人に多大な影響を与えた幸之助だが、彼が驚くほど多くの宗教とかかわっていたという事実は、意外と知られていない。彼は、東京の浅草寺や京都の三十三間堂、和歌山の高野山金剛峯寺など、いくつもの寺社に多額の寄付をし、さまざまな宗教者とも宗派を問わず積極的に交流した。(……)「経営の神様」と呼ばれる彼のカリスマ性に、どこが「宗教者」に通じるものを感じる人もいるかもしれない。/ しかしながら、幸之助は何か一つの宗教を篤く信仰することはなく、特定の宗教者でもない。多様なかたちで宗教と関わる一方で、特定の宗教に深入りはせず、人間一般、とりわけ働く人々の生き方の理想を説き、企業という集団を導いた。
(9-10頁)
結びの部分でも「明治後期から大正期の修養がまさにそうであったように、自分を磨き、高めようと励む思考や行為が、信仰心とは別の形で宗教的なものと結びつくことは多い。現代の自己啓発書はポジティブ思考による成功を説き、自分を高める方法は、伝統的宗教の要素や〈宗教っぽい〉ことば・行為・人物によって指南される」(254頁)と記されるように、修養や自己啓発などは、教義をダイレクトに押し出すものや、〈宗教っぽい〉要素と切り離すことはできないという指摘が非常に印象的なものでした。
日本人が持ちやすい「宗教」に対する忌避感は、オウム真理教のイメージが未だ根強いカルト(人によっては太陽寺院、ライフスペース、法の華三法行、パナウェーブ研究所などを思い出すかもしれません)、霊感商法、ねずみ講やマルチ商法といった極端かつネガティブ要素からきていると思われます。とはいえ、〈宗教っぽい〉ものは日常の様々な領域に浸透しており、松下幸之助のように、宗派を問わず様々な宗教に関わりながらも自身は特定の宗教にコミットしないライフスタイルを無意識に実践している人も多くいると考えられます。
修養は宗教と密接な関りがあると聞くと、「宗教」に対する紋切り型の忌避感から眉をひそめる人もいるかもしれませんが、身の回りにある言葉・行為・人物が帯びている「〈宗教っぽい〉」要素を認識し、それらは特別視すべきものではなく、修養や自己鍛錬を通じて身近に定着しているものと捉えるための手引書としても本書が活用できると思います。
「教養」と「修養」
「教養」(education, culture)という言葉は、現在でもまだまだ広範囲で使われていますが、「修養」という言葉は日常で使われることは稀なことかと思います。修養(self-cultivation, self-improvement, self-disciplineなどが英語での相当)は「主体的に自己の品性を養ったり精神力を鍛えたりすることで、人格向上に努める思考や行為」(11頁)を指します。
幕末から明治初期においては「通俗道徳」(自己鍛錬や勤勉、倹約を重視する倫理規範で、二宮尊徳や石田梅岩らの思想がその代表格)が日本社会に生活規範として根付いており、大澤さんはその時代の修養を通俗道徳の延長として捉え、自分を磨き高めようとする努力は、それ自体が目的となり価値を帯びる(14-15頁)と指摘されます。
近代的な修養(精神的成長を目指す主体的な努力)は、サミュエル・スマイルズの『自助論』(Self-Help, 1859)を中村正直が翻訳した『西国立志編』によって、(吉田松陰や藤田東湖らが説いた武士の倫理に重なる部分も多く見られたことも要因となり)日本国内で広まったとされます。
そういった明治以来の近代的な修養(現代では「自己啓発」に相当)は、明治20年代頃から松村介石らキリスト教系の論者によって、明治30年頃からは仏教系の論者によって説かれてきました。また、教育現場においても修養の必要性が説かれ、明治後期では松村介石が代表格とされる「宗教家」が修養の代弁者となり、松村は、宗派を問わず様々な学説を自らの修養論に取り入れ、キリストのみならず、儒教、仏教、哲学などをも混成させた修養が論じられてきました(46頁)。
修養は宗教(キリスト教や、仏教由来の座禅や読経といった修行と結びついたもの)に関連するほか、伝統宗教のみならず松村らの例で見たように「いくつかの宗教を融合させたり、折衷したり、信仰心とは別の目的で宗教に接近したりする〈宗教っぽい〉もの」(40頁)を組み合わせたブリコラージュとも捉えられます。
日本に資本主義が根づき始める明治後半頃からは、立身出世を目指すノン・エリート層に支持された人気雑誌『成功』や、同士の創刊者であり「『西国立志編』が説く自助努力を富の獲得へと結びつけ、修養を通した成功を解いた象徴的人物」(67頁)である村上俊蔵の影響で、「修養は、それ自体に価値が置かれ、目的とされるとともに、ノン・エリートが金銭を獲得し、社会的に成功するための手段となっていった」(同前)と、修養の変質が指摘されます。
大正期においては、修養と同じカテゴリーにあった「教養」が、読書を通じて人格形成を目指す「教養主義」として分離し、修養は大衆的な日常実践、教養は学歴エリートや知識人の身に付けるものとして、それぞれ定着していきます。
戦後は、経済的な上昇を目指す修養よりも、通俗道徳に近い自己鍛錬や階級上昇、知的権威などを実感するためのシンボルとして「教養」が求められ(文学作品の「全集」ブームや、百科事典の訪問販売など)、教養としての歴史ブーム(司馬遼太郎作品)、1995年の『脳内革命』以降の自己啓発本ブーム、という変化を辿りました。三宅さんは『西国立志編』や、『坂の上の雲』や『竜馬が行く』といった司馬遼太郎作品が「心構え」や「姿勢」、「知識」といった〈内面〉のありかたを説いたのに対し、90年代の自己啓発本は読者が取るべき〈行動〉を明示するという差異が見られると指摘されます(『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』,131-132頁)。『「修養」の日本近代』で取り扱われる修養の多くも内面の在り方に関わっており、テクニックやライフハックの伝授などが全面に押し出された近年のマニュアル本や自己啓発本とは趣が異なっているという印象を受けます。
本書の中で議論される修養は宗教(伝統的なものと「〈宗教っぽい〉もの」)と非常に密接にかかわっており、大澤さんは「多様なかたちで宗教と関わる一方で、特定に宗教に深入りはせず、人間一般、とりわけ働く人々の生き方の理想を説き、企業という集団を導いた」(11頁)松下幸之助という存在を捉える際、宗教との結びつきの強い「修養」が手掛かりになると指摘されます(同前)。
特に松下幸之助の特徴的かつ宗教色が強いメソッドは「〈宗教っぽい〉もの」という観点で微視的に分析され、終章では近年のオンラインサロンの隆盛とそこに含まれる「〈宗教っぽい〉もの」(松下電機やダスキンのように、会社の成員としてではなく、私的な個としてクローズドなサロンに参加することで「〈宗教っぽい〉もの」に接するという差異がある)や、「日本人が抱く『宗教への拒否感』」なども取り上げられます。
お盆やクリスマス、初詣にバレンタインなど、ある時節が来ると当たり前のようにこれらの教行事の参加する日本人は、完全に無宗教というわけではない。仏教、神道、キリスト教に対してあまり抵抗なく関わっている人も多くいる。一方で、特定の宗教を熱心に信仰したり、教団の活動に打ち込んだりするような態度は、周囲からも特異なものだと受けとめられ、「宗教だ」といって眉をひそめられる傾向すらある。自分を磨き、高めることを集団の中で目指すオンラインサロンは、時に宗教的な色合いは帯びることはあっても、それ自体は宗教と同じものではない。宗教ではないからこそ、人々はオンラインサロンに安心を感じて集い、オーナーを頂点とするコミュニティが作られるのだ。
(250頁)
松下幸之助のメソッド=松下電器の企業文化として取り上げられるのは、会社内組織「歩一会」(一致団結するため、融和親睦や福祉増進を図り、文化活動などに取り組む)の活動や、個よりも集団を重んじる「綱領」「信条」からなる経営方針、「七精神」(幸之助から社員に伝えられた「産業報国の精神」、「公明正大の精神」、「和信一致の精神」、などの七項目)の朝会での唱和や社歌の合唱、PHP(Peace and Happiness through Prosperity)運動とPHP研究所や松下政経塾の設立などで、大澤さんは松下幸之助がそういった修養や訓育を導入した背景を、「聖典講義」や「朝の修養」「宗教の時間」といったラジオ番組や、大阪の船場商法(元禄から享保期に生まれた船場商人の精神性を指し、社会的責任を重視する)からの影響を指摘されます。
新渡戸稲造の教育メソッド
本書で特に興味を惹かれたのは新渡戸稲造を取り上げた第3章「働く青年と処世術――新渡戸稲造と『実業の日本』」です。新渡戸といえば、現在流通する樋口一葉/津田梅子の前の五千円札(1984-2007年までのD号券)で馴染み深く、『武士道』(英語原著, 1899)を記し、国際連盟事務局次長や太平洋問題調査会理事長なども務めた国際人として知られています。その一方、『修養』(1911)、『世渡りの道』という、『実業之日本』への寄稿をまとめた修養書も出版しており、エリート層である新渡戸が大衆・通俗誌である『実業之日本』で発表した修養は、富を得るための成功法や処世術とは異なっていた(104頁)とされます。
新渡戸の寄稿は修養をテーマにしていますが、その修養の中に東西古典を読む教養が含まれており、後の大正教養主義に繋がっていくというのが新渡戸に関する一般的な見解ですが、大澤さんは「エリートである彼がノン・エリートに向けて書いた修養」(105頁)に着目されます。
働く大衆の教育に関心を寄せる新渡戸は、表面的な成功や富の獲得を目的とする自己中心的な修養を問い直し、「東西の思想家のことばや、自身の体験談を盛り込み、義務教育しか受けていない者でも容易に理解できるよう語りかけた」(111頁)と言われるように、雑誌の性質や性質や読者層に合わせ、オブラートに包むような表現を重視し、上流であるエリートが立身出世を目指す下流に対しマウンティングを取るような言説を避けたという点が特徴です。
クリスチャンである新渡戸は大衆向けの修養論においても聖書からの引用やキリスト教の教えを援用しましたが、東洋思想(儒学や陽明学)なども織り込み、「キリスト教や聖書の言葉だけでなく、神道や儒教や和歌、天皇の御製や戊申詔書までも引用し、それらを場合によっては使い分け、時にそのいくつかを結合しながら、働く青年に向けて修養を説いた」(117頁)と大澤さんは指摘されます。
加えて、『西国立志編』を訳した中村正直も四書や陽明学に親しみ、『西国立志編』の刊行から三年後にキリスト教徒になりつつも儒者であることを公言していました。中村が新渡戸と同じくキリスト教と東洋思想のハイブリッドとして、その思想や修養論を展開してきたこと、あるいは日本が近代化・西洋化を進める過程おいてキリスト教の影響が非常に大きいことは着目すべき点かと思います。
新渡戸は、国際人であり、『武士道』の執筆者であり、東京女子大の初代学長を務めたといった功績が語られがちですが、リベラルな観点で教養や宗教、そして大衆教育に結び付け、上からではなくノン・エリート/働く青年と同等の目線に立っての情報発信を『実業之日本』の誌面や著作を通じて修養論(教養だけでなく、礼節や生活態度など、通俗道徳に近い内容も含まれる)を広めてきたという、もう一つの顔についての分析が非常に興味深い点です。
さらには新渡戸が関わっていた『実業之日本』を愛読していたのが松下幸之助であり、そこで展開された修養論(特に複数の宗教への寛容性など)と独自の経営哲学が縫合されたものが松下電器の企業文化といえます。
教養へと再び合流する修養
本書は広範囲な時代を扱うため、単的にまとめきれない部分が多くありますが、新渡戸稲造(『実業之日本』)から松下幸之助に連なる線や、両者のリベラルな宗教観が修養論や経営哲学に反映されているという指摘は非常に興味深く読みました。
加えて「修養」と「教養」は、新渡戸の修養論や大正教養主義の展開などを経て、分けて考えられるようになりましたが、教養の中にも修養的な成功や上昇への欲望が含まれており、修養という言葉があまり聞かれなくなった今日において「教養」という言葉・概念の中には再び修養が復活しているという印象があります。
例えば「ファスト教養」という用語においても、成功や上昇など自身の修練のみならず利益に与する(修養としての側面)ことを期待して、言い換えれば「何かについて知らないことは損をする」(=上昇や成功の契機を逃すという錯覚)という意識から、質よりも量的でタイパに優れた教養(あるいは「情報」)を求めるといったケースが見られます。
また、ハウツー本やマニュアル本の変わらぬ人気は、早急に理解や答えを求めるポジティブ・ケイパビリティ(帚木蓬生『ネガティブ・ケイパビリティ 答えの出ない自体に耐える力』, 2017, 朝日新聞出版を参照)と深い関連性があり、三宅さんは指摘されるように、それらの本はわからないことに対する不安を鎮めるだけでなく、修養的な上昇感を満たす効果を持っています。
昭和的な一億総中流社会が崩れ去り、バブル崩壊やリーマンショックなどの景気後退、そして若者に貧困が広まる中で、『階級を無効化する』知識の在り方が求められていた。文脈も歴史も教養も知らなくていい、ノイズのない情報。あるいは社会情勢や自分の過去を無視することのできる、ノイズのない自己啓発書。それらはまさに、自分の階級の低さに苦しめられていた人々のニーズにちゃんと答えていた。
(『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』, 158頁)
大澤さんが「個人の営みである修養は、宗教者やインフルエンサー的存在、自己啓発書やカリスマ的経営者たちによって教えられ、指導されて行うという受動的なものである」(253頁)と指摘されるように、マニュアル本や自己啓発本(特に権威者、専門家、インフルエンサー、著名人が全面に押し出されたもの)は「〈宗教っぽい〉」要素が色濃く表れやすく、それが様々な不安を鎮めることに大きく寄与しているとも考えられます。
書店やネットのランキングを見る際、「なぜ『教養』という言葉が全面に押し出されてあり、自己啓発本やマニュアル本が人気を博すのだろう」と考える際、「修養」という概念やその歴史などを知ると、それらの本が求められる背景などにも理解が広まるほか、かつての代表的な日本企業の経営哲学の根底にある諸要素ついてもビジネス論や経営論とは異なる観点から学ぶことができるので、本書は幅広い興味関心に訴求力を持つ1冊です。
人気記事
まだデータがありません。