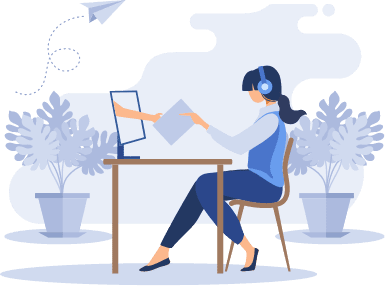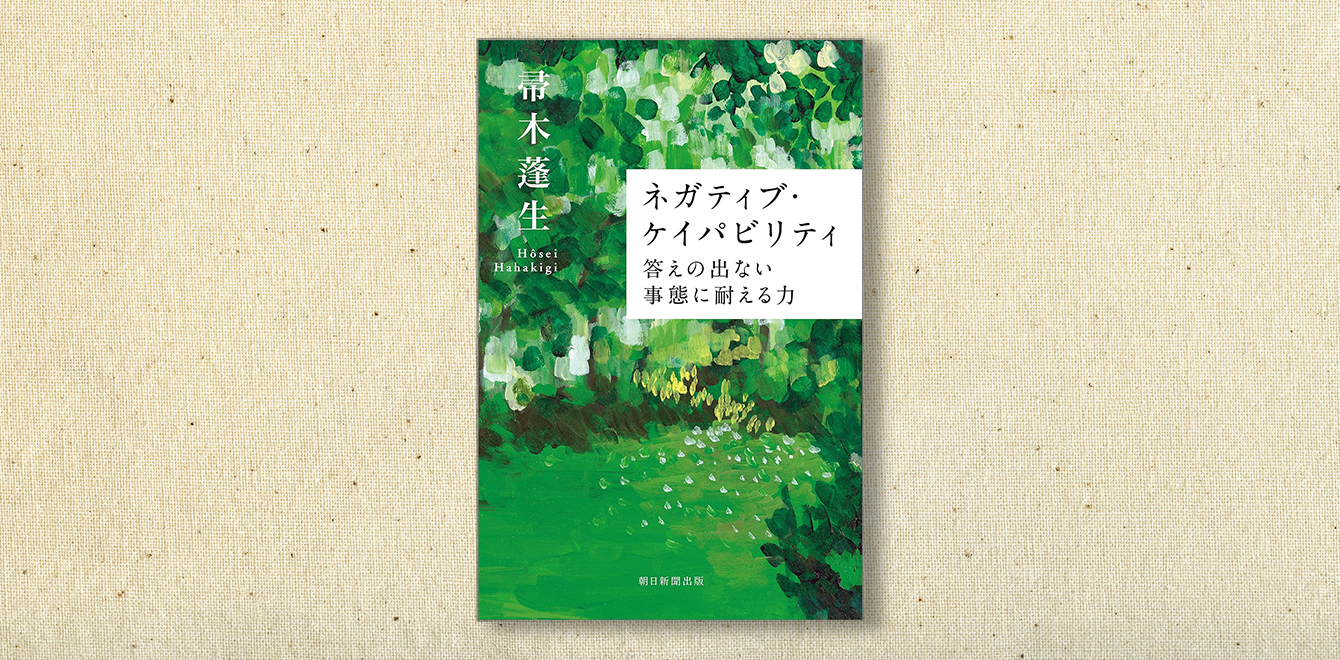
「ネガティブ・ケイパビリティ(negative capability)」とは「どうにも答えの出ない、どうにも対処のしようにない事態に耐える能力」(帚木蓬生『ネガティブ・ケイパビリティ 答えの出ない自体に耐える力』, 2017, 朝日新聞出版. 9頁)や「性急に証明や理由を求めずに、不確実さや不思議さ、懐疑の中にいることができる能力」(同前)を指します。
この用語を知ったのは佐藤卓己さんの『あいまいさに耐える――ネガティブ・リテラシーのすすめ』(2024, 岩波書店)で、佐藤さんはSNSなどを通じて真偽の入り混じった情報が急激に拡散される現象である「インフォデミック」が、コロナ禍を通じて顕著になった今日の状況について、読書論に由来する「見過ごし」「読み飛ばし」や「やり過ごす」能力である「ネガティブ・リテラシー」(消極的な読み書き能力)が重要となると指摘されるほか、類似的な概念として「理解」や「理由」を早急に求めず、あいまいさに耐えるネガティブ・ケイパビリティを取り上げられます。
精神医療の現場では、病院を不明のままにしておく方が患者にとって望ましい場合も少なくないようだ。何もしなくても時間経過で自然に治癒する場合もあり、主治医は不安な患者を「しかと見ている」ことが大切だと帚木は言う。こうしたネガティブ・ケイパビリティの臨床側からメディアリテラシー教育が学ぶことは少なくないはずだ。(……)メディアリテラシー教育でも問題解決を強調すべきではない。イエス/ノーの世論調査、すなわちON/OFF、白/黒のデジタル思考への抵抗力を高めること、あいまい情報の中で事態に耐える人間力こそが、AI時代に求められるリテラシーだからである。/あいまい情報をやり過ごし、不用意に発信しない思考がクリティカルシンキングであるのならば、それは「耐性思考」とでも呼ぶべきなのではあるまいか。
(佐藤卓己『あいまいさに耐える』, 172頁)
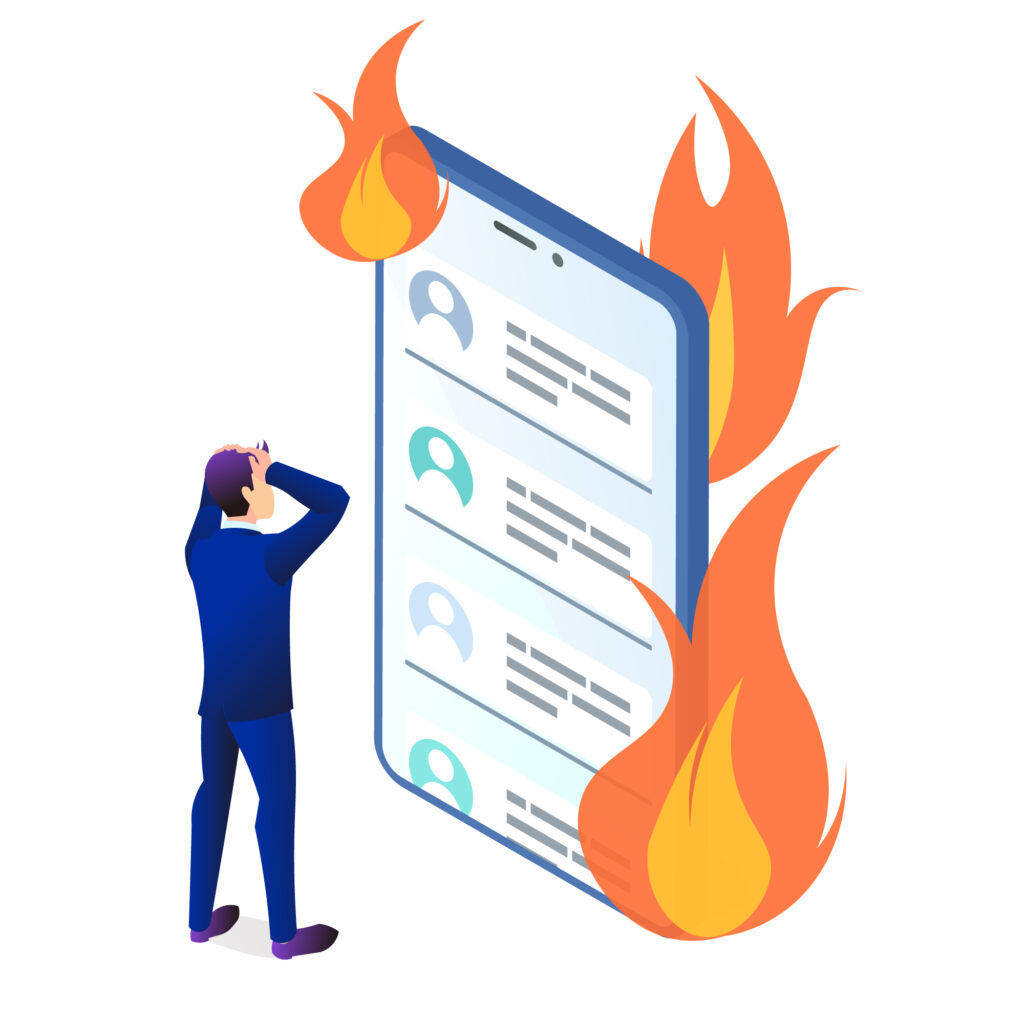
ネガティブ・ケイパビリティは佐藤さんが指摘するような耐える力のみならず、帚木さんが重要視する共感や寛容にも大きく関わっています。また、近年では寛容さが失われつつある近年の世相を象徴するような事例として、SNS上での不用意発言による「炎上」があげられます。
炎上は、相手のことを考えず、(内に留めて口外する必要のない)単なる好き嫌いを自分本位で主張したり、自分の考えや価値観が正しいという思い込んで安易な断定を行ったり、絶対的な答えのでないあいまいな問題に答えを提供しようと一方的な介入を行うこと、いわばポジティブ・ケイパビリティの過剰発露によって発生・拡大していく傾向があります。
寛容性や「不用意に発信しない思考」を欠いたポジティブ・ケイパビリティの発露などには、後にも触れるオルテガ『大衆の反逆』で論じられた「大衆」(階級ではなく精神性や態度を指し「平均人」との呼ばれる)の特徴である「万能感/自己完結」や「制限のない欲求」などが見て取れるほか、炎上のきっかけとなる発言に多く見られる「こらえ性のなさ」などに、共感や寛容、他ものに対する想像力、そしてネガティブ・ケイパビリティの欠如が見いだせることが多くあります。
ネガティブ・ケイパビリティはロマン主義詩人ジョン・キーツによって生み出され、精神科医ウィルフレッド・ビオンに再発見された用語であり、帚木さんはビオンの「Toward empathy: the uses of wonder.(共感に向けて。不思議さの活用)」という論文でその概念を知ったと述べられます。また、論文のタイトルにもあるようにネガティブ・ケイパビリティは「共感(Empathy)」(「相手を思いやる心」)にも強い関わりを持ち、ビオンは「創造を通じて共感に至る」(11頁)と記し、帚木さんは「不確かさの中で事態や状況を持ちこたえ、不思議さや疑いに中にいる能力――。しかもこれが、対象の本質に深く迫る方法であり、相手が人間なら、相手を本当に思いやる共感に至る手立てだと、論文の著者は結論していました」(13頁)とまとめられます。
本書は大きく分けるとネガティブ・ケイパビリティの歴史(キーツの生涯やビオンの活動)、福岡でメンタルクリニックを営んでおられる帚木さんの臨床経験に基づいた事例分析とネガティブ・ケイパビリティとの関わり、創造行為におけるネガティブ・ケイパビリティや文学論(シェイクスピア、紫式部、エラスムス、ラブレー、モンテーニュなど)という三つの柱で構成されています。
専門書ではなくエッセー調であるため本書の内容は平易なものではありますが、精神分析はもとより文学に関する知識(特にシェイクスピアの四大悲劇)がある程度前提にされている部分も少なくありません。とはいえ、臨床に基づく分析や身近な例を題材にする第5章「身の上相談とネガティブ・ケイパビリティ」や第9章「教育とネガティブ・ケイパビリティ」、トランプ大統領とメルケル首相を例に不寛容/寛容の際などが論じられる第10章「寛容とネガティブ・ケイパビリティ」は、前提知識があまりなくとも十分に読みやすい内容かと思われます。
ネガティブ・ケイパビリティの重要性
キーツのネガイティブ・ケイパビリティがビオンによって再発見されたのは精神分析の領域であり、まず精神分析において重要な概念と見なされてきました。ネガティブ・ケイパビリティの反語であるポジティブ・ケイパビリティは、早急に理解を求める、わかろうとする、曖昧なグレー状態に耐えられないといったもので、佐藤さんはポジティブ・ケイパビリティについて次のようにまとめられます。
私たちはあいまい情報に直面した場合、このネガティブ・ケイパビリティを意識しない限り、早く「分かろう」「理解しよう」とするのが普通である。ケイパビリティ(能力)とは、ポジティブ(積極的)であるのが普通である。帚木はその理由を「分かりたがる脳」に求める。その正常な脳を快適状態に保つために、専門家は何ごとであれ標準化・体系化された手引書を用意する。医療現場ではまずマニュアルが用意される。なるほど、私が患者だとしても、病院では速やかに病名を指摘され、はっきり説明されることを望むはずだ。マニュアルを使わず「よくわかりませんね。経過をみましょう」と言われて、安心できる患者は少ないだろう。
(『あいまいさに耐える』,171 頁)
前頭葉を大きく発達させた人間の脳は「分かりたがる」性質を持ち、文字、数字、図形、絵文字といった記号を発達させたり、物事に法則性や因果関係を当てはめて解釈したり、納得するとされ、マニュアルは「分かる」ための最大のツールなるため、ハウツー本への人気が集中する構図を、帚木さんは次のようにまとめられます。
目の前に、わけのわからないもの、不可思議なもの、嫌なものが放置されていると、脳は落ち着かず、及び腰になります。そうした困惑状態を回避しようとして、脳は当面している事象にとりあえずの意味づけをし、何とか「分かろう」とします。世の中でノウハウもの、ハウツーものが歓迎されるのはそのためです。
(『ネガティブ・ケイパビリティ』, 14頁)
帚木さんは「分かりたがる脳が、何か分けのわからないものを前にして苦しむ実例」(70頁)として音楽と抽象絵画をあげ、分かることを拒否するものに耐えて感覚的な訴求力に達しすることで感じる高揚感について、「脳はまたそこで、自分が一段と進化した喜びを味わっているかもしれません」(71頁)と指摘されます。
加えて、タイムパフォーマンス(タイパ)とコストパフォーマンス(コスパ)が重視されるパフォーマンス至上主義が根付いた今日の情報化社会では、すぐにアクセスできる断片的な情報が「正解」と錯覚する傾向があります。物事の重層性や多様性についての意識、いわば提示された情報の余白や重層性に対する想像力や推察力を欠いてしまい、それによって0か1/好き・嫌いという安易な断定や決めつけを求めてしまうのが現代の特徴と考えられています。
古典芸能、例えば能楽などは上演作品の内容や能楽の形式(夢幻能や現在能)などの予備知識を持ってポジティブに鑑賞する場合と、ほとんどの予備知識なしにネガティブに鑑賞するケースがあると思われます。小学校の授業で〈見せられた〉能と狂言の映像(子供の目にはあいまいなものと映るほか、授業の一貫なのでさらに退屈さが増す)なども、ある意味ではネガティブ・ケイパビリティを育む機会となっていたような気もします。
現代アートやパフォーマンスを鑑賞する際も「何か分けのわからないものを前にして苦しむ」ことがよくあります。その体験を「小難しいもの」と一蹴するのではなく、タイパや効率性は悪くなりますが、ネガティブ・ケイパビリティを修養と考えながら接しようとする意識を持つことで、深い洞察力や感受性を育むうえで重要になると思われます。
精神分析においては。症状とその要因に関する分析・理論の蓄積がマニュアルとして存在していますが、ビオンはマニュアル第一主義がネガティブ・ケイパビリティ獲得の妨げになるとみなしていたそうです。
帚木さんによれば、医学教育ではポジティブ・ケイパビリティが最重要視され、SOAP(Subject/患者の症状, Object/診察や検査で得た客観的データ, Assessment/SとOからの判断評価, Plan/治療方針 )に基づいた治療が実施されたり、「医師は何が正常で何が異常かを峻別する訓練を受け、解決策を頭の中に叩き込まれます。医師は病気を見つけそれを、治療する責任があるという意識を植え付けられます。異常があれば発見し、大事に至らないうちに正常に近づけるのを天職と心得る」(76頁)とされます。
特にネガティブ・ケイパビリティの効果が発揮されるのは終末医療や緩和ケアの領域で、類型化・マニュアル化できず個々人で千差万別である「正常な精神状態」で死の不安を抱える終末期の患者と相対する際、「目の前の事象に、拙速に理解を合わせず、宙ぶらりんで解決できない状況を、不思議だと思う気持ちを忘れずに、持ちこたえていく力がここで要請されます」(80頁)と述べられます。
解決法が見つからず、手の施しようない身の上相談などにおいても耐える力としてのネガティブ・ケイパビリティが重要(第3章「身の上相談とネガティブ・ケイパビリティ」参照)となり、解決策を提案する「治療」ではなくケアとしての「トリートメント」を心がけることも指摘されます。
ネガティブ・ケイパビリティは拙速な理解ではなく、謎を謎として興味を抱いたまま、宙ぶらりんの、どうしょうもない状態を耐え抜く力です。その先には必ず発展的な理解が待ち受けると確信して、耐えていく持続力を生み出すのです。
(73頁)
芸術の理解や臨床の現場における「分からなさ」や、答えの曖昧な状態(宙吊り感)を肯定したり不思議がる(興味関心を持つ)こと、腰を据えて向き合うといった態度などは、ある意味では自分の積極的な能力(ポジティブ・ケイパビリティ)を懐疑し、謙遜的な姿勢をとるようなことにも繋がると考えられます。
答えや理解を積極的に出そうとするポジティブ・ケイパビリティの難点について、「『分かった』つもりの理解が、ごく低い次元にとどまってしまい、より高い次元にまで発展しないのです。まして理解が誤っていれば、悲劇はさらに深刻になります」(14頁)と指摘されるように、自分は「理解している」「正しいと」いう錯覚、いわば万能感を持って積極的に介入することが返って逆効果や混乱を招くケースは日常に多く見られます。
ポジティブ・ケイパビリティの過剰発露は、『大衆の反逆』でオルテガが取り上げた「大衆」(他者との同調、進歩・努力の放棄、過去や歴史の軽視、万能感/自己完結、制限のない欲求などと特徴とする)の特徴を有する一方、積極性的な行動や意識を一端宙吊りにするネガティブ・ケイパビリティは、状況を客観視し、他者への理解や共感を高めること(リベラル/寛容性)にも繋がるほか、オルテガが「大衆」と対を成す精神性として定義した「貴族」の中にもネガティブ・ケイパビリティに類似した要素が含まれているようにも考えられます。
寛容性とケイパビリティのネガポジ
リベラルな精神にとって重要な寛容はヒューマニズムを土台にしており、その歴史を辿るとエラスムスの『愚神礼賛』、『ガルガンチュア物語』を記したラブレー、『エセー』のモンテーニュに連なるユマニスト(ルネサンス期の人文主義者, 神・教義から人間中心主義への転換を図る)の系譜が浮かび上がるとされます。
寛容は大きな力は持ち得ません。しかし寛容がないところでは、必ずや物事を極端に走らせてしまいます。この寛容を支えているのが、実はネガティブ・ケイビリティなのです。
どうにも解決できない問題を、宙ぶらりんのまま、何とか耐え続けていく力が、寛容の火を絶やさずに守っているのです。
(190頁)
現代のユマニストの例として帚木さんが取り上げるのはドイツのメルケル首相(在任2005-2021)は、2015年のギリシャ危機では救済策と改革案を突き付け、ロシアのクリミア半島への侵攻では迅速な経済封鎖を行い、中東からの避難民受け入れの決断という、EUが直面した3つの危機への対処を決断した根底には人道主義(ヒューマニズム)があると指摘されます。
東ドイツで育ったメルケル首相は牧師の娘であり、キリスト教の精神と不自由な監視社会でもあった旧東ドイツでの体験がメルケル首相に寛容とヒューマニズムをもたらしたと指摘します。一方、寛容の対極として上げられるのはトランプ大統領(第一期目)です。
アメリカ第一主義、防衛費の不均衡な負担の是正、排外主義、中国との対立、移民排斥などに関連した発言の多くは二期目である現在においても変化はなく、自分の意に応じない他者・他国に対する不寛容のさらなる増長が日々のニュースで報じられています。。
トランプ大統領に限らず、日常のあらゆる領域で不寛容さが目立つ今日の状況は、新自由主義と自己責任論の蔓延、コモングッドの崩壊(ロバート・B・ライシュ『コモングッド』を参照)、アルゴリズムに扇動されたフィルター・バブル、佐藤卓己さんの『あいまいさに耐える』で議論された、メディアリテラシーあるいはネガティブ・リテラシーの衰退、「大衆」化、そしてネガティブ・ケイパビリティの乏しさなど、様々な要因が絡み合った状態で生じています。それゆえ、「なぜ今日のような状況になってしまったのか!?」ということを深く考えるうえでは、タイパは極めて悪くマニュアル化もなされていませんが、先に上げたようなトピックに関する知識や議論を広く渉猟ことが必要とされると思われます。
ネガティブ・ケイパビリティを習慣付ける
本書はネガティブ・ケイパビリティを体系的にとり上げたものではなく、エッセー調かつ臨床の現場から日常のものごと、文学、政治と様々な文脈にネガイティブ・ケイパビリティを援用したものです。
帚木さんが冒頭で「ネガティブ・ケイパビリティの概念を知っているのと知らないのでは、人生の生きやすさが天と地ほど違ってきます。なぜなら、世の中にはポジティブ・ケイパビリティに対する信仰ばかりがはびこっているからです」(16頁)と述べるように、ネガティブ・ケイパビリティについても、理解して実践するというよりも頭の片隅に置いておくべき概念(ポジティブとネガティブの併存も可能)であり、ふとした時にネガティブ・ケイパビリティ的なものの見方や、他者に対する共感を意識するような習慣をつけることが重要となります。
執筆者の場合は佐藤さんの『あいまいさに耐える』でネガティブ・ケイパビリティを知ったので、主としてメディアリテラシーの文脈でこの概念を捉えていますが、本書で議論されるネガティブ・ケイパビリティは広範に渡っています。それゆえ、議論の展開がやや散漫な印象があるほか、第十章の後半部は (作家としての帚木さんは戦争をテーマにした作品を多く手掛けている影響もあり) やや飛躍が大きい印象を受けましたが、臨床現場におけるネガティブ・ケイパビリティや、第8章「シェイクスピアと紫式部」も非常に興味深く読めました。
各章毎にがらりと趣が変わるので、一本筋の通った本に慣れている方はやや煩雑さを感じると思いますが、様々な分野についていることができるという点では得るものが多く内容も平易なので、一般的な読者層にも取っ付きやすい本であると思います。
参考記事
・「何とかするのではなく、何とかなる。精神科医の帚木蓬生さんに聞く『ネガティブ・ケイパビリティ』とは」(2020年3月6日, セゾンのくらし大研究)
・「複雑な課題を解くカギは『耐える力』にある? ネガティブ・ケイパビリティの技法を学ぶ」(2020年3月19日, WIRED)
関連記事
・21世紀に「貴族」であるとは? (第1回オフサイトセミナー)
・文学からお陰さまを学ぶ (第9回オフサイトセミナー)
人気記事
まだデータがありません。