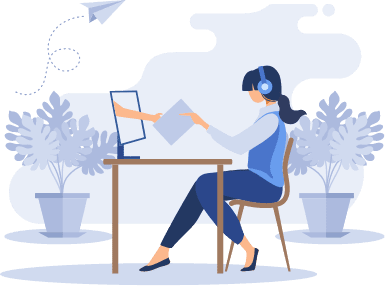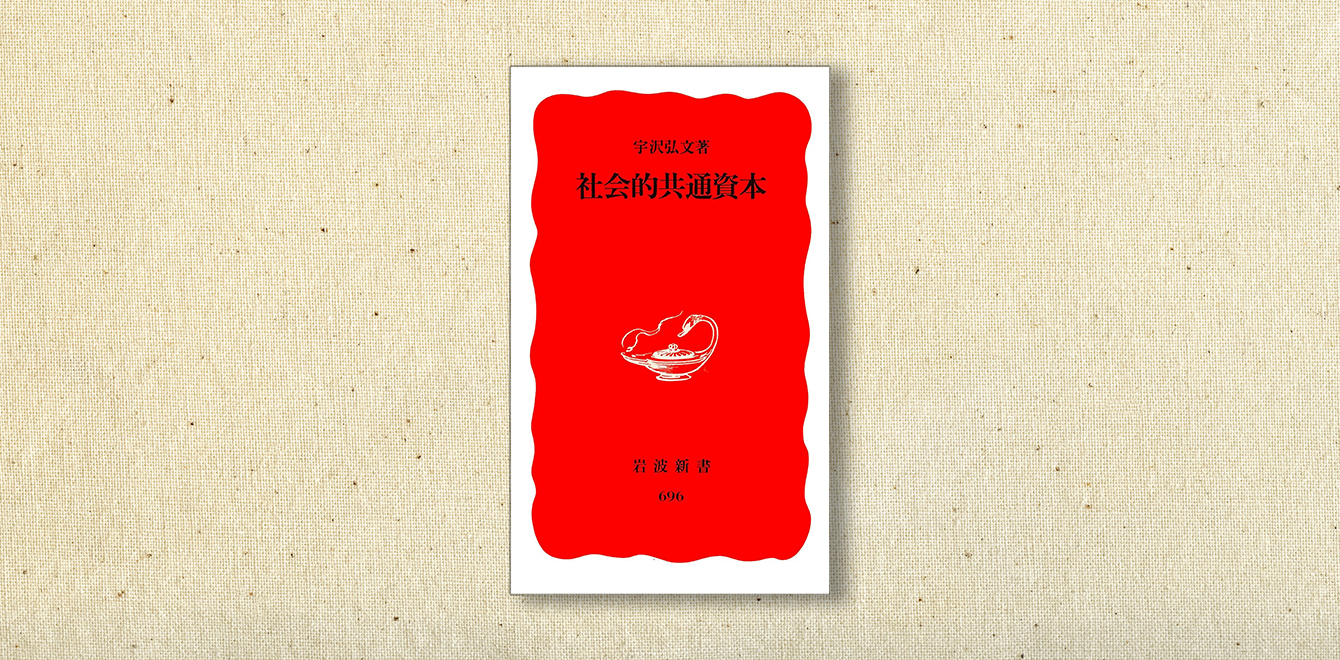
タイトルにもなっている「社会的共通資本」とは経済学者の宇沢弘文さんが提唱された概念であり、英訳では”Social Overhead Capital”や”Social Common Capital”と表記されます。”Social”と”Capital”の語が含まれていますが、主に人やコミュニティの繋がりを分析するために用いられる「社会関係資本」(Social Capital)とは異なる概念です。
1956年に渡米し、1968年代の渡英を経て帰国した頃から宇沢さんが構想されていたとされる「社会的共通資本」は、公害・農村破壊・過度な都市開発といった高度経済成長の歪みに対し経済学者としてどう向き合うかという課題が構想の出発点になった(若森みどり, 2022, 34頁)と言われています。その後、宇沢さんは車社会の諸問題を取り上げた『自動車の社会的費用』(1974)筆頭に著作・論文を精力的に刊行されてきました。
東京大学退官後の1989年から逝去した2014年までの25年間は「社会的共通資本」の思想展開が結実した時期 (若森, 2022, 35頁)とされ、教育、地球温暖化、森、都市、医療といった様々なテーマが「社会的共通資本」という概念に寄せて論じられてきました。
本書『社会的共通資本』(岩波書店, 2000)の各章の内容は1970年~1980年代にかけて発表された論文や著作に加筆・訂正を行ったもので、「農業と農村」、「都市」、「学校教育」、「医療」、「金融制度」、「地球環境」といったテーマが各章に割り振られています。
新書形式であるため比較的読みやすい内容ですが、章によっては新古典派経済学からソースティン・ヴェブレンら制度学派経済学(institutional economics)への主流の移行、ジョン・デューイの教育論やプラグマティズムに関する議論や経済史など専門的な要素も含まれています。そのため、経済思想や実用主義、社会学等に馴染みのない方は初読時に敷居を感じるかもしれませんが、近代経済学史(特に新古典派~ヴェブレンへの転回)の概説書的な側面もあります。また、各章は主に個別のトピックを扱っているので関心のある章から順に読むほか、副読本として新書形式の入門書(中村隆之『はじめての経済思想史 アダム・スミスから現代まで』など)を準備すると理解が円滑に進むと思われます。
「社会的共通資本」という概念
宇沢さんの経済思想の中心概念である「社会的共通資本」は、大気、森林、河川、水、土壌などの「自然環境」、道路、交通機関、上下水道、電力・ガスなどが含まれる「社会的インフラストラクチャー」、教育、医療、司法、金融制度などの「制度資本」という3つの大カテゴリーに分けられ、都市や農村は「社会的共通資本」から成立し、その利用やサービス分配によって国や地域の社会・経済的構造が特徴づけられるとされます(Kindle版, 3頁)。一般に馴染みのない「制度資本」という分類は、社会的な制度(国や地域の倫理、社会、文化、自然といった文脈によって異なる多様なもの)を(共通)資本として考えるアプローチで、「制度資本」のなかでも宇沢さんは特に教育と医療を重要視されています。
「社会的共通資本」としての医療は様々な医療分野の雑誌や講演会で多く取り上げられるテーマであり、『社会的共通資本としての医療』(宇沢弘文・鴨下重彦 編, 2010, 東京大学出版会)というタイトルの書籍も刊行されています。そのほかにも、財政破綻によって医療状況の変革を迫られた夕張市での在宅診療に関わった経験を持ち、後期高齢者に対する過剰医療(療養病床での入院看護、経鼻経管栄養法や胃ろう)の問題や、膨大に注ぎ込まれる医療費と世界一の病床数を持つ日本の医療の関係などを取り上げる森田洋之さん(南日本ヘルスリサーチラボ代表、ひらやまのクリニック院長)も、著作や寄稿などで繰り返し「社会的共通資本としての医療」について言及されています。
宇沢さんは20世紀の世紀末的状況は、資本・社会主義の各国が「社会的共通資本」の管理・維持が適切に行われてこなかったことに起因すると指摘し、21世紀では「社会的共通資本」の問題が大きな課題になると述べます(14頁)。今日において最も明確な課題としてあげられるのはやはり環境問題であり、SDGs(Sustainable Development Goals)の考え方が定着してきた近年においては、環境保全、気候変動、健康福祉、教育機会の平等など「社会的共通資本」が内包する諸要素は比較的イメージしやすいと思います。
本書の序章においては、21世紀の社会が目指すべきものとして「ゆたかな社会」という概念が提示されます。「ゆたかな社会」とは「すべての人々が、その先天的、後天的資質と能力とを充分に生かし、それぞれの持っている夢とアスピレーションに相応しい職業につき、それぞれの私的、社会的貢献に相応しい所得を得て、幸福で、安定的な家庭を営み、できるだけ多様な社会的接触を持ち、文化的水準の高い一生をおくることができるような社会」(9頁)とされ、宇沢さんはそういった社会に必要な諸条件を5つ提示されます。
(1) 自然環境の安定的・持続的な維持
(2) 快適・清潔な生活を営める住居と、生活的・文化的な環境
(3) 子供たちが資質や能力を伸ばし、発展させ、調和の取れた人間として成長しうる学校教育制度
(4) 疫病・傷害に際して、時々の最高水準の医療サービスの享受
(5) 希少資源が、1-4の目的を達成すために効率的・衡平に配分されるような経済的・社会的制度の整備
「社会的共通資本」の考え方は後にSDGsやESG(Environment Social Governance / 環境・社会・企業統治)に多大な影響を与え、「ゆたかな社会」や5つの諸条件は両者に重なる部分が非常に多くあるので現在的な課題としてより理解しやすいと思われます。加えて、「ゆたかな社会」と対極に位置づけられるものは、社会のセーフティーネットが充分に機能せず自己責任論が声高に叫ばれがちな新自由主義とも考えられます。
「社会的共通資本」の考えは、1970年代後半~80年代終わりにかけて米国を中心に勃興した新自由主義の市場原理主義的な批判を基盤にしています。「社会的共通資本」としてカテゴライズされるものは、文字通りの社会的なインフラストラクチャー(土台や基盤)であり、それらは市場原理とは切り離されたものとして位置づけられる必要があります。その点で、新自由主義とは真逆な考え方である一方、持続可能性と資本主義の両立という新しい社会のありかたを模索する手がかりが、「社会関的共通資本」という概念に含まれています。
本書では個別のテーマについて、「社会的共通資本」という観点から現状分析や問題提起、改善案(新自由主義から持続可能な資本主義への転換)の一例が論じられており、中でも関心を惹くのは金融制度(第6章)と地球環境(第7章)です。
金融制度を社会的共通資本として考える
第6章「社会的共通資本としての金融制度」では、アメリカ(金融危機と大恐慌)と日本(住専問題など)が取り上げられます。アメリカの事例では、大恐慌後の経済学の展開(合理的期待形成仮説、反ケインズ経済学、マネタリズムに基づく変動為替制の導入など)、「社会的共通資本」としての金融制度に関して、管理方法や政府の監督・チェック体制などについて示唆を与える例として、1984年にコンティネンタル銀行の(事実上の)破綻事例が取り上げられます。
アメリカの事例 (大恐慌~ニューディール)
1920年代中頃から投機的な動機によって生じた米国の金融バブル(投機対象は土地、金、美術品など)が株式市場へと波及し、空前の株価上昇が生じました。その後、1929年10-11月にニューヨークの株式市場で株価の大暴落がおこり、世界的な大恐慌へと拡大しました。
1920年代の米国金融バブルに対し、当時のフーヴァー大統領は正常な経済活動であるとの見解を示し続け、経済政策に影響力を持っていた経済学者アーヴィング・フィッシャー(株価上昇はアメリカ産業の繁栄の証左と解釈)が見解を支えていました。その後は1933年にルーズベルトの大統領就任し、銀行法(グラス=スティーガル法)の制定、ニューディール政策などの広く知られた経済政策の提案が続いていきます。
宇沢さんは銀行法とニューディール政策の中心事業であるテネシー河流域開発計画(巨大ダムの建設、農業・工業の発展促進、雇用と生活の安定確保)を「社会的共通資本」の形成例とみなし、次のように述べます。
1933年の銀行法は、銀行制度を一つの社会的共通資本とみなして、その経営に社会的基準をもうけて、一国ないしはある特定の地域の経済活動が円滑に機能し、人々が安定した生活を営むために銀行の果たすべき本来的な機能が充分に発揮できるような条件を整備しようとするものであった。同じような意味で、テネシー河流域開発公社は、テネシー河の全流域の総合的な開発を促進し、産業の発展と市民の生活の安定を可能にするような社会的インフラストラクチャーの形成を目的としていたのである。ともに、社会的共通資本の形成を通じて、アメリカ経済のかつてない規模と強度を持った大恐慌に対して有効な対応策を打ち出そうとしたわけである。
(161頁)
ニューディール政策(特にテネシー河流域開発公社)に対しては、本来は民間が担うべき事業に政府が関与したという旨で違憲判決を受けましたが、基本的な機構を変えることで、かろうじて内容を維持されたとされています。同政策を推進したのは新古典派経済学を否定したヴェブレンを中心とした制度派経済学であり、ヴェブレンの論じる制度を具体的に表現したものが、銀行制度や社会的インフラストラクチャーといった「社会的共通資本」ですが、「社会的共通資本」が経済学の中に位置づけられるには先のこと(161頁)、とまとめられます。
国内の事例 -住専問題-
日本の例としては、金融崩落のきっかけとなった住専(住宅金融専門会社)問題がとりあげられ、「住専問題は一言でいえば、日本の特異な金融行政の産物であるが、もっと一般的には戦後50年にわたって日本の経済・社会を支えてきた制度的諸条件がすでに陳腐化して、新しい時代的要請に応えることができなくなってしまったことの象徴」(170頁)とされます。
宇沢さんは破綻や落伍を出さないことを念頭に置いた護送船団方式が、日本の金融機関における金融的節度の欠如、社会的倫理観の喪失、職業的能力の低下をもたらし、それらが1986-1990年にかけて顕著な形となったものが住専問題である(169-170頁)と指摘。
節度や倫理観の喪失、いわば「社会的共通資本」の機構に携わる受託者が、自らに必要とされる職業的な規範や意識を欠くという状況が住専やその他の問題を生じさせ、結果的に農村や自然といった他の「社会的共通資本」の棄損へと拡大するという悪例が、日本、当時の金融行政から浮き彫りになります。
日本の事例ではもうひとつ、住専と合わせて日本の金融システム不安を広く認知させ、ジャパン・プレミアム(日本の銀行が海外市場で資金調達を行う際の上乗せ分金利)を要求される契機となった大和銀行NY支店での巨額損失事件(1995)なども取り上げられます。
こちらに関しても「社会的共通資本」の管理・運営に携わる受託者の倫理規範や職業意識に関わる問題であり、宇沢さんは国内事例について次のようにまとめられます。
金融という、高度に専門化し、経済的、社会的、政治的要素ときわめて複雑に交錯している社会的共通資本の場合、その職業的規範を明確に定義し、金融にかかわるさまざまな市場について、その構造的、制度的条件を整備し、経済循環の安定性を確保することは至難のことである。しかも金融制度が、広範な広がりを持つとき、この問題の困難度はいっそう高まるものと言わざるを得ない。
(172頁)
近年の事例では、2023年の米シリコンバレー銀行(SVB)の破綻や、クレディ・スイス(CS)の経営危機などが記憶に新しいかと思います。どちらの事例においても、危機に至った直接的な原因、その後の救済処置・財務処理(特にCSではAT1債も問題となりました)といった対処法の比較分析は「社会的共通資本」としての金融のあり方を考えるための参考になると思います。
持続可能性を模索する
これまでに触れたように「社会的共通資本」はSDGsやEGSのベースとなる概念であり、新自由主義とは異なる政治経済のあり方(「ゆたかな社会」)、あるいは経団連の掲げる「サスティナブルな資本主義」を考えるための出発点にも相当する概念で、社会の土台部分を支えるものでもあります。土台、すなわち「社会的共通資本」をも市場原理に巻き込む新自由主義とは異なり、土台を市場原理から切り離し、規律ある専門家によって担保される制度的安定性を確保したうえで持続的な資本主義を追求していくことが、今日求められる資本主義のあり方の一例であるといえます。
本書の中で宇沢さんが繰り返し強調するのは、高い規範を持つ職業的な専門的による管理・運営・維持であり、「社会的共通資本」に関わる人に求められるもの中には「利他」や「贈与」の精神があるようにも思えます。特に医療や教育など、ギバー(与える人)としての献身性が重視される領域では、その精神性がより強く求められるでしょう。
本サイトの記事では、これまでにも「利他」と「贈与」を重要なキーワードとして考えてきました。記事内で著作を取り上げた中島岳史さん(『思いがけず利他』)は宇沢さんについて新聞メディアへの寄稿のほか、ラジオ番組でも宇沢さんについて言及されるほか、成長それ自体が目的化し、「Up or Out(成長か退場か)」のような潮流を持つ資本主義とは異なる、SDGsやEGSの流れを組む新しい資本主義を検討する清水大吾さん(『資本主義の中心で、資本主義を変える』)は宇沢さんを題材にした講演(「宇沢弘文を読む―社会的共通資本から現代の課題を考える」, 2024年3月5日)などに登壇されるなど、これまで取り上げてきた議論のインフラ部分に「社会的共通資本」が根差していることを実感させられます。
本書の諸部分はやや専門的な内容を含みますが、「社会的共通資本」という観点を知ることで、様々な事象やSDGsやEGSに関する解像度も高くなるでしょう。加えて、本サイトの記事で取り上げてきた哲学・思想(特に「利他」、「贈与」/「ギブ」、保守思想など)についても、前述のように「社会的共通資本」の概念が源流にあると思しきものが多くあると考えられるため、知識の枠組みを補強するという点からも、一度本書に目を通してみることを強くお勧めします。
参考資料
「宇沢弘文の『社会的共通資本』の展開: 思想史的アプローチ」(若森みどり, 2002,『経済学雑誌』, 1号123巻, 31-76頁, 大阪市立大学 )
「コモンズとしての社会的共通資本とそのマネジメント」(間宮陽介, 2016, 『水資源・環境研究』29号2巻, 水資源・環境学会)
「サステイナブルな資本主義に向けた好循環の実現~分厚い中間層の形成に向けた検討会議 報告~」(一般社団法人 日本経済団体連合会, 2023年4月26日)
「半世紀も前に導入した『社会的共通資本』がなぜ今、共感を呼ぶのか」(Forbes JAPAN編集部, 2023年4月14日, Foebes JAPAN)
人気記事
まだデータがありません。