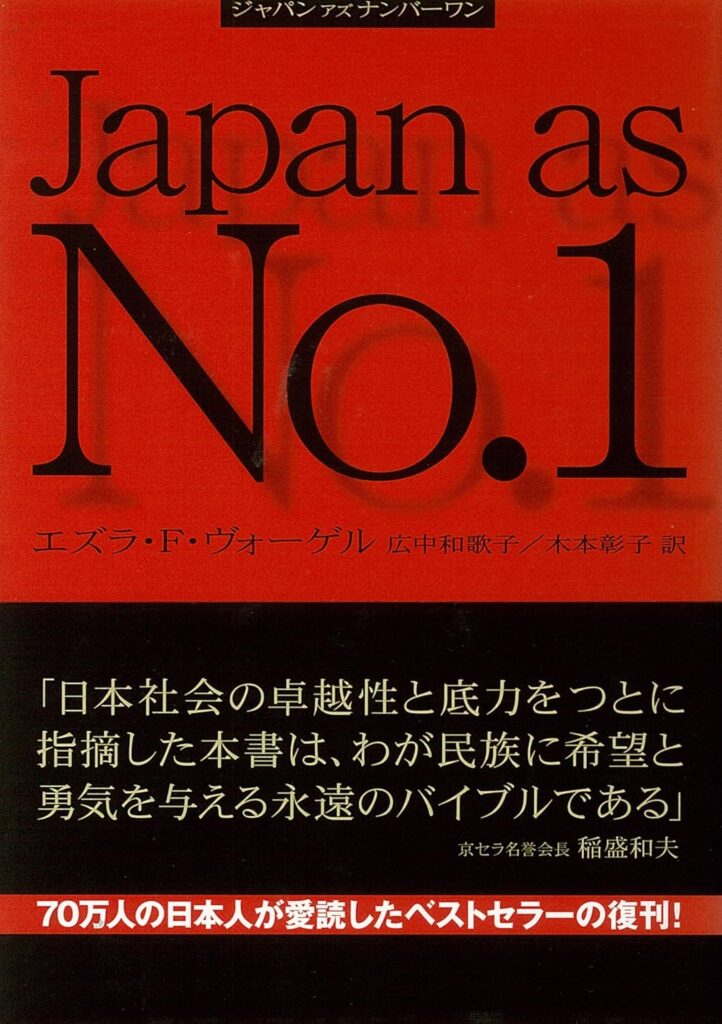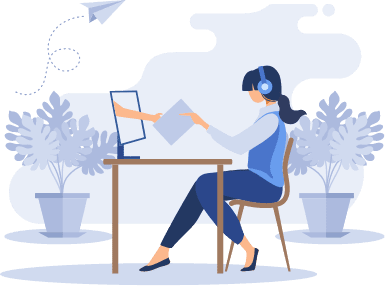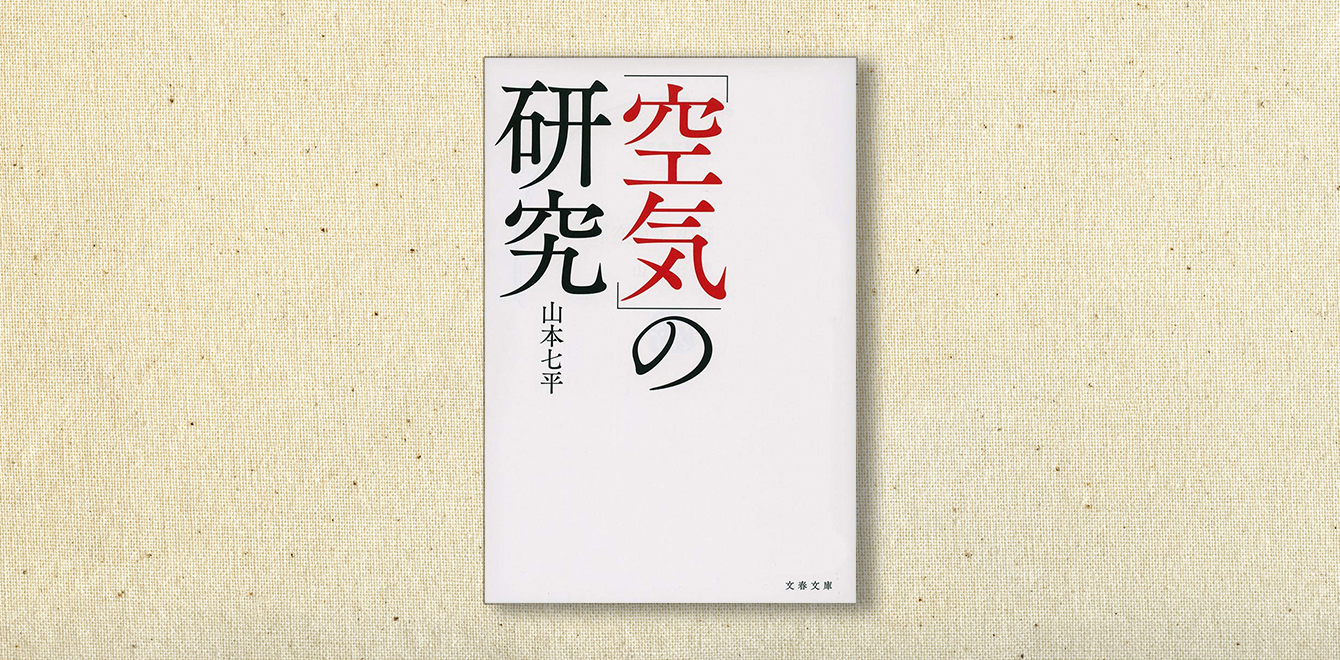
最近は「(場の)空気を読む」という言葉を聞かなくなって久しい気がしますが、一時期は「KY(場の空気が読めない / 空気を読め)」という言葉を頻繁に耳にした記憶があります。「KY」は2006年事から女子高生言葉として使われはじめ、自民党が他党に第1党を譲る大敗を喫した2007年夏の参院選後に早急な辞任を行わなかった(第一次)安倍内閣を「KY内閣」と称したことで爆発的な広がりをみせたといわれています。2007年には「ユーキャン 新語・流行語大賞」にノミネートされるほどの認知や広がりを獲得しました(他のノミネートは「産む機械」「お友達内閣」「かわいがり」「ワーキングプア」「モンスターペアレント」など)。
現在では「危険予知」の略称として「KY」という言葉が用いられ、厚生労働省が「KY活動」について発信するなど、場の「空気」に関連した「KY」は死語になっています。とはいえ今日ではかつての「KY」を代替するような言葉はあまり思いつかず、もっと間接的・歪曲的な言葉になっているか、あるいは変わらず「空気」という言葉が覇権を握っているかもしれません。
場の「空気」に類似した言葉としては、同調圧力、雰囲気(ムード)、「判断の基準」、「絶対的規範」などもありますが、それらは「空気」によってもたらされた作用や効果なので、「まことに大きな絶対権を持った妖怪である。一種の『超能力』かも知れない。」(『「空気」の研究』, 13頁)と説明される「空気」の正体や構造を捉えたものではありません。
本書『「空気」の研究』(初版 1977, 文庫版 2018, 文藝春秋 )は「空気」という日本に特有の現象を相対的に分析した日本人・日本文化論であり、現在の状況と照らし合わせながら読むと(例としてwebミーティングという仮想的な場には「空気」があるか否かなど )様々な発見がでてくると思いますし、初版が刊行された当時から変わらない部分も多くあると感じさせられます。
著者の山本七平さんは1921年にクリスチャンの両親の間に生まれ、戦中は砲兵見習い士官・野戦観測将校としてフィリピンのルソン島の戦闘に参加。ルソン島北端で終戦を迎えた後、マニラの捕虜収容場に移送され現地米兵の通訳なども担当。帰国後は福武書店での勤務を経て、聖書学を専門とする出版社の山本書店を創業。1970年にイザヤ・ベンダサンの筆名で『日本人とユダヤ人』を山本書店より刊行。同書は日本人論ブーム(特に外国人による日本人論)の火付け役ともいわれており、筆名では『日本教について あるユダヤ人への手紙』(1972, 文藝春秋)、『にっぽんの商人』(1975, 文藝春秋)などの著作も刊行されています。
外国人による日本論といえば、ルース・ベネディクト『菊と刀』(The Chrysanthemum and the Sword: Patterns of Japanese Culture, 1946, 邦訳1948 )や、エズラ・ヴォーゲル『ジャパン・アズ・ナンバーワン』(Japan as Number One: Lesson for America, 1979)などが代表的なものとして知られています。一方『日本人とユダヤ人』は、ベンダサンという筆名こそ外国人ですが、内容は山本と知人の外国人による合同執筆であり、外国人による日本論と言い切れない部分があるほか、後の版では山本七平名義に改められました。
『日本人とユダヤ人』はキリスト教文化と日本文化(および日本軍に従軍体験)という複数の観点を持つ境界的な日本人による日本人論という点では、内村鑑三『代表的日本人』(Representative Men of Japan, 1908 )と重なる部分もあります。加えて、後者は日本の偉人を海外に紹介するための本であり、禅を海外に紹介することを目的とした鈴木大拙『禅と日本文化』(Zen Buddhism and Its Influence on Japanese Culture, 1938, 邦訳1940)と同じく、原著は英語で執筆されていました。
『「空気」の研究』には「『空気』の研究」、「『水=通常性』の研究」、「日本的根本主義(ファンダメンタリズム)について」の3編が収録されています。3編の際立った共通項としては、山本さんの来歴を反映するように、キリスト教文化圏との比較や、日本軍を例にした「空気」の分析なども含まれています。
『水=通常性』の研究」では、「『空気』の研究」で分析された「空気」の支配や、「人工空気」の醸成によって個々人の価値観を一定方向に向けさせる戦略などの打開策としての「水」という概念、外から取り入れたものを消化・吸収するという日本文化の特徴を下地にした「酵素」の作用などのユニークな論点が提示されます。
「日本的根本主義」は、他の2編を踏まえての応用編というような位置付けで、内容も少々難解さを増すほか、「根源主義(ファンダメンタリズム)」と題されているように、より深く読み解くうえではアメリカのキリスト教原理主義についての予備知識も多少必要になります。
収録の3編はいずれも日本独特の慣習や文化、社会的特徴を相対的に分析するような内容で、マスメディアの扇動や、「空気」への従属(寛容性の喪失)など、オルテガが『大衆の反逆』で論じた内容と重なる部分が多くあります。また、「研究」というタイトルが付けられていますが表題作は『文藝春秋』誌での連載をまとめたもので、「『水=通常性』の研究」と同じく社会批評・評論としての趣が強くアカデミックな論考とは異なりますが、キリスト教、軍隊、日本文化と複数の観点を持つ山本さんの碩学性が大いに発揮されています。
全体の情報量は非常に多いほか、「『空気』の研究」の中盤から「『水=通常性』の研究」は抽象的かつユニークな概念での展開が怒涛ように展開されていきますが、全編をしっかり読もうとすると非常に手強い内容なので、ある程度の部分は流し読んでいく割り切りも必要になります。また、3本目の「日本的根源主義について」は他2編に比べるとかなり読みやすいという印象を受けました。
社会論としてはやや古めな本ですが、今に通ずる論点も非常に多くありますが、難解な部分も多くあります。とはいえ、明確な定義がないにも関わらず疑問を持たれることの少ない共通認識として日常空間に存在する「空気」はどのような効果をもたらしているのかを言語化し、把握あるいは客観視するような視座を得られるなど、気づきや発見が非常に多い内容になっています。
「空気」とは?
日常的に使っているにも関わらず、「それ」が何なのかが曖昧な状態にあるという用語は数多く、中でも「空気」はその代表格かと思われます。「空気」という用語は日常的に馴染んでいるため、私たちは無意識に「場の空気」「空気を読む/読めない」「空気が重い/悪い」「(何かを行う)空気じゃない」などの慣用句を使っています。
あまりにも馴染みすぎているので「空気」とは何かを考える機会を持つことは少ないと思いますが、「空気」が指すものはなんとなく理解できている……ような気になってしまうのが、「空気」の特徴かもしれません。
以前から私は、この「空気」という言葉が少々気にはなっていた。そして気になりだすと、この言葉は“絶対的権威”の如くに至る所に顔を出して、驚くべき力を振っているのに気づく。「ああいう決定になったことに非難はあるが、当時の会議の空気では……」「議場のあのときの空気からいって……」「あのころの社会全般の空気も知らずに批判されても……」「その場の空気も知らずに偉そうなことを言うな」「その場の空気は私が予想したものと全く違っていた」等々々、至る所で人びとは、何かの最終的決定者は「人でなく空気」である、と言っている。
(9-10頁)
山本さんは「空気」を人の価値観や選択を支配するものとして捉え、「まことに大きな絶対権を持った妖怪」や、「一種の『超能力』かもしれない」と例え、まず絶対的な権力を持つ存在や超常的なものとして「空気」の正体を考察します。また、「空気」の支配例としてあげられるのが『戦艦大和』(吉田満 監修構成, 『文藝春秋』, 1975年8月号)での「全般の空気よりして、当時も今日も(大和の)特攻出撃は当然と思う」という部分で、特攻出撃は無謀と反対するする人はデータなどの根拠に基づいた判断を行っているにも関わらず、「空気」が特攻出撃すべきという判断を下していると解説されます。
「空気」の支配的な力は、山本さんの見立てでは戦後においても存在しており、それはムードとも言いかえられるほか、「空気」が竜巻状になることでブームになると指摘され、「いずれにせよ、それらは、戦前・戦後を通じて使われる『空気』と同系統に属する表現と思われる」(14頁)と述べられます。
本書の初版発行から30年が経過した2007年に「KY」が流行語となったことを鑑みると、長年に渡ってなお、国内に限定されたものではあれど存在感を保ち続ける「空気」なるものの影響力や普遍性に驚かされるほか、浮き沈みの激しい株式市場に関するニュースやトピック、あるいはそれらの受容や語られ方を眺めていると、「空気」がポジティブ・ネガティブの両面で作用しているなと感じさせられることが多々あります。
「空気」は、絶対的な支配力を持つ「判断の基準」であり、我々は「論理的判断の基準と空気的判断の基準という二重基準のもとに生きている」(17頁)とされ、大和の出撃はその代表例として紹介されます。また、「空気」の支配で引き起こされた他の例として、関東大震災があります。

震災時では流言に惑わされた市民が自警団を結成して暴力行為に及んだ事例がありますが、論理的判断として流言とわかっていても「空気」的判断基準では自警団に加わらざるを得ないだけでなく、「KY」な判断をすれば、内通者や排除対象に肩入れする者と見なされ、身辺に危険が及ぶ可能性があるため流言を信じる「空気」、いわば同調を促す集団圧力が場を支配していきます(芥川龍之介「大震雑記」などを参照)。
重要なのは、「空気」は自然発生的なものと作為的な「人工空気」に細分化されるという点で、「人工空気」の例として本書で取り上げられるのは、排ガス規制(日本版マスキー法)に関する下りです。
排ガス規制・日本版マスキー法による規制が本格化した1973年頃は、1950年代後半から引き続き公害病が社会問題とされていた時期(本書ではイタイイタイ病が中心に取り上げられます)であり、公害問題に関する当時の論調や本格化するモータリゼーションとそれによって生じた問題や課題(それらについては、1974年に刊行された宇沢弘文『自動車の社会的費用』などを参照)を予備知識として持っていなければ読みにくさもありますが、メディアの報道やSNSでの話題に感化された世論( popular sentiment)の関心が熱を帯びることで「人工空気」が醸成され、「(人工)空気」的判断基準が特定の方向へと水路づけられていくというものです。
ややポジティブな水路付けの例としては、グッドニュースをより祝福的な「空気」に持っていくような演出的報道などがあります。その一方、ネガティブな部分では些細なスキャンダルを大げさに・繰り返し報道することで、(自己責任から)批判の対象にしても良いという「空気」を醸成し、悪意や敵意を表面化させるといったケースがあります。記憶に新しいものでは2004年の「イラク日本人人質事件」、近年では頻繁に発生するSNSでの「炎上」などがその典型例といえます。
人工的な「空気」は醸成過程もわかりやすく、さらには「空気」そのものも雲散霧消しやすく、絶対的な規範となりえない(24頁)とされますが、自然派生的な「空気」は絶対的な規範になる場合があり、感情移入が強力になるあまり、感情移入が無意識化・日常化する状態である「臨在感的把握」が規範形成の要因と指摘されます。
「臨在感的把握」は「物質から何らかの心理的・宗教的影響を受ける、言い変えれば物質の背後に何かが臨在していると感じ、知らず知らずのうちにその何かの影響を受ける状態」(26頁)であります。「臨在感」はある種の物神崇拝や、何かの代替物に対する依存状態で、それらに宿る・付随すると感じる超越的なものを認識したり、そこから様々な影響を受けることが「把握」となります。
日本では八百万の神的な物神崇拝や神棚、破魔矢や熊手といった縁起物、道祖神/お地蔵様など、「物質の背後に何かが臨在している」という考えが根付いており、その点が外国との比較で浮き彫りになります。この点は、一神教(モノティズム)的な世界観と神仏習合の混淆的信仰観(シンクレティズム)に基づく日本との大きな違いとなり、「絶対」的な対象は一神とする一神教の世界では他の全ては相対化・対立的な概念(正統-異端、聖-俗など)で把握される必要があり、旧約聖書の世界などは徹底的な相対化の好例(59頁)であると指摘されます。
相対化の徹底された世界では「石仏は石であり、金銅仏は金と銅であり、人骨は物質にすぎず、御神体は一種の石」(134頁)であり、それらは絶対的な神による被造物なので、それらに対して臨在感を抱くことはないため「空気」の支配が効果を発揮することはありません。とはいえ、一神教的な世界では日本の混淆的信仰観に基づく「空気」とは異なる道徳形態があり、その一例が『菊と刀』で論じられた「罪の文化」(「恥の文化」とされた日本と相対化された西欧の文化類型や道徳観)ともいえるでしょう。
規範的な「空気」と「臨在感的把握」
日本において「空気」の支配性が際立つのは、日本人(というより日本文化)は「臨在感的把握」に秀でた能力を育む土壌があると考えられているためです。本書の中で取り上げられる感情移入の対象の一例としては、教育勅語や御真影、不動明王の神符、御神体などがありますが、感情移入の対象は無数にありひとつの対象との関係が解消された際には、また別の対象(シンボル)が、感情移入の対象になると指摘されます。
石仏は石であり、金銅仏は金と銅であり、人骨は物質にすぎず、御神体は一種の石であり、天皇は人間であり、カドミウムは金属であると言うことで、これから脱却し得ない。もちろん、一見脱却したかの如き錯覚は抱きうる。だがそう錯覚したときその者は、別の対象を感情移入の対象にしたというだけ、簡単にいえば「天皇から毛沢東へ転向した」というだけであり、従って何らかの対象が自己の感情移入の対象になる限り、言わば、偶像すなわちシンボルと化すことができうる限り、対象の変化はあり得ても、この状態からの脱却はあり得ない。
(134頁)
本書の例では、古代墓地の発掘調査で骸骨が発掘され、日本人とユダヤ人の関係者が人骨を運搬していると、日本人は病的に疲弊する一方でユダヤ人は何の影響も受けなかったというもので、山本さんは墓地発掘の「現場の空気」にあてられ、心的影響から体調を崩したと分析されます。
ユダヤ人が影響を受けなかった理由には、人骨に何かが臨在するとはみなさない(「霊」がそこに留まらない)という文化的慣習が背景にあり、一方の日本人は「霊」は遺体・遺骨周辺に留まり、人間に干渉しうるという世界観を持ち、物質である骨への感情移入(臨在感的把握)から脱却できないために影響を受けたとされます。
「人工空気」の構築と大衆感情の水路付け
発掘調査の例は、「空気の一方向支配」(臨在感的把握の対象がひとつで単純化された状態)とされます。また、現実では多方向からの支配で金縛りになる状態があり、それが「空気」の支配とされ、複雑に絡み合った支配のうちある2極点の臨在感的把握を絶対化(善は善、悪は握と一元的に固定させる)するだけでも、「空気」に完全に支配された状態が生じると指摘され、その典型例として西南戦争(1877)があげられています。
官軍(政府)と賊軍(私学校党)の戦いとなった西南戦争では、「世論」の動向が重要視され、マスコミの利用が本格的に始まるなど、日本にとっての初めてとなる近代的な戦争であると山本さんはまとめられます。
「人工空気」の醸成でみたように、世論( popular sentiment)の関心を誘導するうえでは、マスメディアが大きな役割を担っており、農民徴募の兵士を使う官軍側は無関心層を「心理的参加」させるために戦意高揚記事が必要とされ、官軍の奮闘や敵味方を問わず負傷者を助ける慈悲深さと賊軍の残虐非道性(捏造記事)を新聞記事などで伝えたとされます。
当初は西郷側に同情的だったものも、また政府と西郷の間を調停してすみやかに停戦して無駄な流血をやめよと主張したもの、その上で西郷と大久保を法廷に呼び出して理非曲直を明らかにせよと上申していた者のも、すべて「もうそういうことの言える空気ではない」状態になってしまう。というより、おそらく、そういう空気を醸成すべく政府から示唆された者の計画的キャンペーンであったろう。
(40-41頁)
西南戦争を例に、山本さんは「『対立概念で対象を把握すること』の排除」が空気支配を維持するための原則のひとつ(42頁)とされます。対立概念の排除に関するくだりは、少々ややこしいのですが、「善」〈と〉「悪」という対立的な概念把握を行うことで、対象や概念は絶対的な基準を持つことはなく、それらは状況や立場、地域で変化しうるという柔軟な考えに至ります。
西南戦争を例にすると、官軍が絶対的な正義であるためには、西郷・私学校党側が〈賊〉軍という絶対悪である必要があり、官軍を支える世論や農民兵が同情を寄せたり西郷側の立場に立って考える余地を徹底的に排除する必要がありました。
「正義」と「悪」という二項に対して、それぞれを臨在感的に把握、いわば感情移入や一体化を行うことで、「正義」(政府)と「悪」(私学校党)が絶対的なものとして位置づけられ、残虐非道な「悪」に対する嫌悪と、「悪」を成敗する博愛的な「正義」に対する支持や称讃に没入するような「空気」が醸成されていくことで、世論において「正義」と「悪」を相対的に見ようとする観点を「KY」として排除するような、絶対的な価値基準が発生します。
「官軍〈は〉善」「賊軍〈は〉悪」という絶対化された(あるいは単一的)な基準では、「双方を『善悪という対立概念』で把握せずに、一方を善、一方を悪と規定すれば、その規定によって自己が拘束され、身動きができなくなる。さらに、マスコミ等でこの規定を拡大して全員を拘束すれば、それは、支配と同じ結果となる。すなわち完全なる空気の支配になってしまう」(43頁)という構造が生じます。対立関係を用いた絶対的価値観の形成・世論の水路付けという戦略は、戦争に限らず様々な事例に同様の構造を見出すことができ、「空気」による支配(世論への同調=自己意識の「大衆」化)を避けるための戦略のひとつが、構造を批判的に読むためのメディアリテラシーといえます。
「空気」による支配の克服
臨在感を歴史観点的に把握しなおすこと、対立概念として対象を把握するという2点が 「空気」の支配を克服するうえでの要点とされます。「『空気』の研究」の後半部(5章)以降は、克服の例として、公害問題や日中国交回復といった刊行当時のトピックや、教育勅語に最敬礼を行わなかったことを同僚教師や生徒から非難され社会問題化した内村鑑三不敬事件(1891年)に関連付け、御真影と教育勅語という絶対的価値基準が付与されていた当時の感情移入対象に対し、不動明王の神符と水天宮の影像を対立項として設定し、臨在感的把握を絶対から相対に変えることで「空気」の支配から逃れられるといった戦略が述べられます。
「『空気』の研究」の4章辺りまでは比較的読み進めやすいのですが、5章以降は抽象度がさらに増し、取り上げられる時代も、現代(公害問題)、近代(福沢諭吉や内村鑑三不敬事件)飛び飛びになり、7-8節は山本さんの専門領域のひとつである聖書を引いての解釈も入るためさらに難解さが増すことで前半部から続いてきたトーンが急激に変わっていきますが、「『空気』の研究」の最後に添えられる「水的発想」が、2本目の論考「『水=通常性』の研究」に繋がっていきます。
「空気」がなんらかの判断基準の根拠となったり、絶対的化された価値観、熱狂的な状態を生み出す一方、願望・期待への熱を冷ます「水」は、通常性や現実的なハードルを突き付けるという効果を持ちます。
ある一言が「水を差す」と、一瞬にしてその場の「空気」が崩壊するわけだが、その場合の「水」は通常、最も具体的な目前の障害を意味し、それを口にすることによって、即座の人々を現実に引き戻すことを意味している。
(78頁)
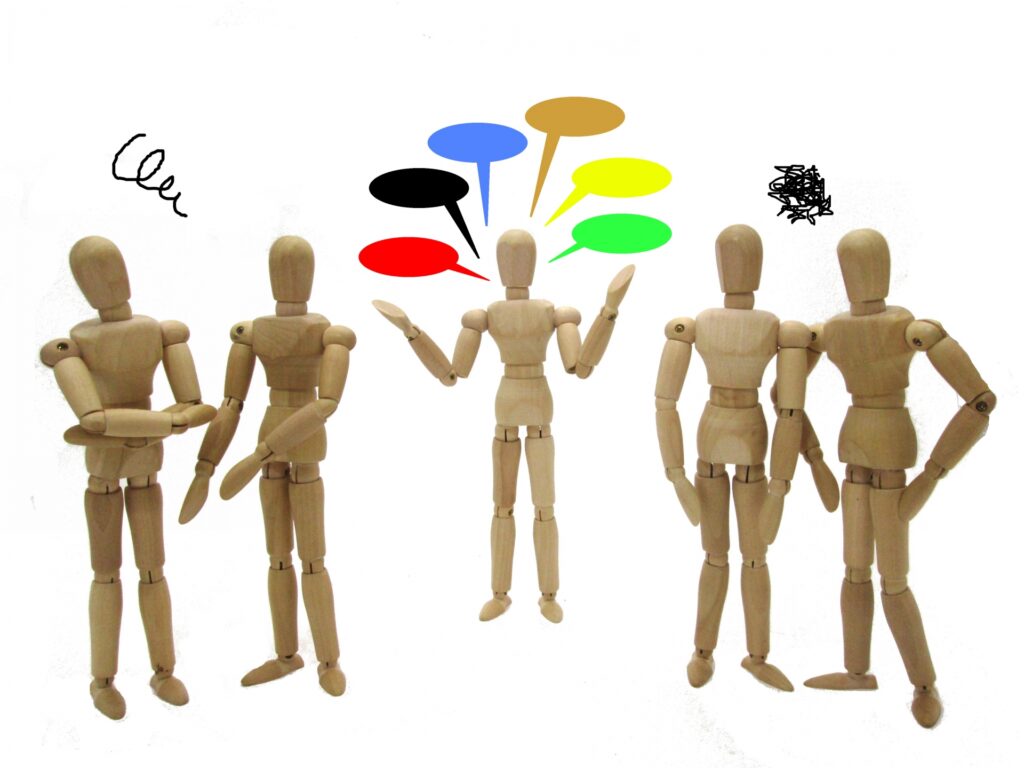
熱狂状態を冷ます〈空気の読めない〉一言としての「水」は比較的わかりやすいのですが、山本さんは連続した「水」らしきものを消化酵素に類したものに例え、それが形を崩しどこかに吸収され、名のみが残って実態が消えていくと述べます(79頁)。この部分は非常に抽象的ではありますが、後の議論で「酵素」の作用とよばれ、「通常性作用」(87頁)と定義されます。
「『水=通常性』の研究」はその後、外から取り入れたものを消化・吸収し、換骨奪胎する形で取り入れていく日本文化(例としてあげられるのは、体制全般ではなく家父長制的な価値観のみが取り入れられた「科挙なき儒教」)、「空気」の支配による拘束状態や自由の喪失、公害の原因公表に関する日本型組織の閉塞性なども論じられていきます。
なかでも、「資本の論理」(会社を守るために公害の原因を隠す)と「市民の論理」、「父と子の隠し合い」(「父は子の罪悪をかばい隠し、子は父の罪悪をかばい隠す」という意味の「子爲父隠(しいふいん)」を組織内での責任隠蔽に例えたもので、父が社長・子が重役といった例や、行政によるイタイイタイ病のカドミウム原因否定説など)など、「空気」の支配や「忖度」によって生じる、日本の悪習の分析などは現在にもあてはまるケースが多く、不正の内部告発などは「子爲父隠」に対する強烈な抵抗ともいえるでしょう。
「『空気』の研究」は初版発刊からもうすぐ50年になりますが、日本の社会・文化的な慣習に関する分析は現在もなお通用すると感心させられるばかりか、本書を読み進める際に頭に浮かんだのは。やはりオルテガ『大衆の反逆』であり、オルテガの指摘する「大衆」は「空気」に支配された層とも解釈することができます。
山本さんは日本独自の感覚として「空気」を分析し、それを外国語として訳す際に相当する語を検討し、ルーア(ヘブライ語)、プネウマ(ギリシャ語)やアニマ(ラテン語)が「空気」の概念に類似する(47頁)と指摘されるほか、プネウマの沸騰状態が宗教的狂乱状態や集団的異常状態を現出させるような記述も古代の記述に見られており、プネウマを「空気」に置き換えると現実味を帯びてくる(48頁)と指摘されます。
彼らは霊(プネウマ)といった奇妙なものが自分たちを拘束して、一切の自由を奪い、そのため判断の自由も言論の自由も行動の自由も失って、何かに呪縛されたようになり、時には自分たちを破滅させる決定をも行わせてしまうという事実を、そのまま事実として認め「霊(プネウマ)の支配」というものがあるという前提に立って、これをいかに考えるべきか、またいかに対処すべきかを考えているのである。
(48頁)
「空気」に相当する訳語や古代の記述を踏まえると、やはり「空気」は超常的なもの・霊的なものであり、ある程度の構造を分析・言語化できてもその特性は合理・論理性とは異なる次元に存在し、啓蒙や教育を受けた理性的な人間主体にも宗教的な作用を及ぼす という点で、主体は自律し、「大衆」が抱くような万能感を持つものではなく、超常的ものからの影響かを逃れがたいという、いわば「空気」を読む/従属する可能性があることを自覚し、謙遜的な精神性(オルテガのいう「貴族」に相当) 持つことが、「『空気』の支配」を「読解(デコーディング)する」に繋がると思います。
そういう点では「空気」の支配に対峙するうえでは、オルテガを含め保守思想を学ぶことが重要なるほか、世論を扇動する「人工空気」の動向を注視するうえでは「ネガティブ・リテラシー」(耐える力、情報をやりすごし、不用意に発信しない力)や「ネガティブ・ケイパビリティ」(「理解」や「理由」を早急に求めず、あいまいさに耐えること)などが重要になってくると思われます。この2つの概念や、「世(せ)論」(大衆感情popular sentiment)と「輿(よ)論」(公的意見public opinion)をより詳細に知りたいという方は佐藤巧己さんの『あいまいさに耐える――ネガティブ・リテラシーのすすめ』(岩波書店, 2024)などをご参照ください。
関連投稿
人気記事
まだデータがありません。